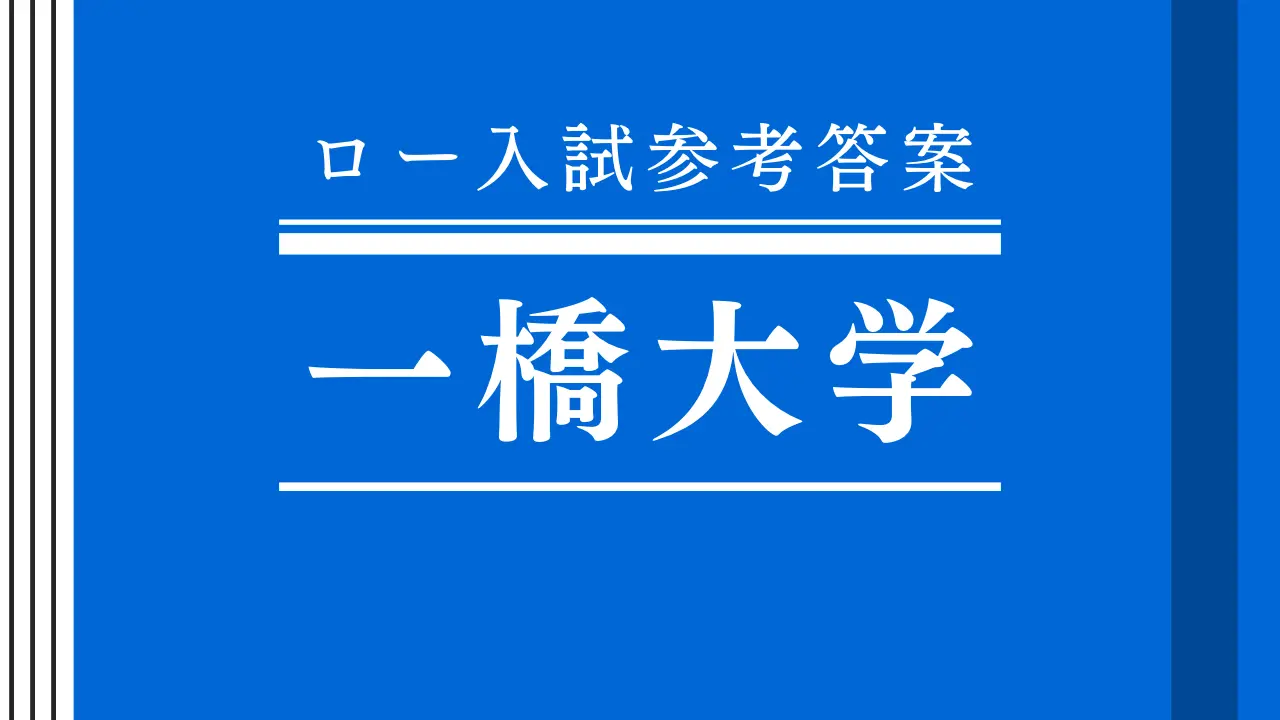
2025年 刑法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2025年 刑法
第1問
1. Xがガソリンをまき散らした行為(以下「第1行為」という。)につき、現住建造物等放火罪(108条1項)が成立するか。
2. 「住居」とは、起臥寝食する場所として、日常利用されているものを意味し、昼夜間断なく人がいることは要しない。A一家は翌日戻ってくる予定であったから、A 方宅は、「現に人が住居に使用」する「建造物」にあたる。
3. Xは、新聞紙に所携のライターで着火したものを入口ドアに向けて投げるつもりであったが、タバコの灰が入口ドア付近に落下し(以下「第2行為」という。)、ガソリンに引火したことにより、A方宅が全焼している。
第1行為のみを実行行為とみる限り、第1行為は「放火」行為といえ、これにより目的物が「焼損」しているから客観的構成要件を満たすものの、甲はその客観的危険性を認識していないので、未必的な故意(38条1項本文)すらなく、現住建造物等放火罪は成立しない。
では、第1行為の時点で、第2行為を通じた結果発生の現実的危険が生じたとして、第2行為の「実行に着手」(43条本文)したといえないか。実行の着手が認められれば、そこには第2行為経由の焼損の危険と第1行為自体による焼損の危険が併存しており、第1行為自体による焼損の危険の現実化として因果関係が肯定され、一連の実行行為により焼損させる認識により、故意も認められうるから問題となる。
⑴「実行に着手」とは、その文言と実質的処罰根拠より、①構成要件該当行為に密接し、②既遂結果発生の現実的危険性を有する行為をいうと解する。行為者の計画も根拠に入れ、(a)構成要件該当行為を確実かつ容易に行うための準備的行為の必要不可欠性、(b)準備的行為以降の計画遂行上の特段の障害の存否、(c)両行為の時間的場所的近接性などを総合考慮して判断する。
⑵ガソリンは引火しやすいからガソリンをまいておけば、後は火を近づけるだけで確実かつ容易に本罪を遂行することができるので、本件行為は必要不可欠であった。また、準備的行為以降の計画遂行上の特段の障害はなかったし、新聞紙にライターで着火した者を入口ドアに向けて投げる前に、気持ちを落ち着かせるためにタバコを吸っていただけであるから、両行為の時間的場所的近接性も認められる。
よって、第1行為の時点で、第2行為の実行に着手したといえる。
4. また、「焼損した」とは火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立に燃焼を継続する状態に達したことをいうところ、A方宅は全焼しているから、「焼損」したといえる。
5. 第1行為自体による焼損の危険の現実化として因果関係も認められる。タバコの灰が物置小屋の入口ドア付近に落下してガソリンに引火しているところ、ガソリンの揮発性の高さからすれば、第1行為には微細な発火物が触れることでガソリンに引火する現実的危険性が内包され、かかる危険が現実化したものと評価できるからである。
6. ここで、軽い犯罪事実の認識で重い犯罪事実を実現した場合、重い犯罪で行為者を処断することはできない(38条2項)。
Xは、A一家が全員引っ越していなくなるものと思い込んで行為に及んでいる。かかる認識を前提とすると、A一家が帰ってくることはないということになるから、一時旅行などの場合と異なり、現住性を認めることはできない。すなわち、Xに、現住性の認識はなく、非現住建造物等放火罪(109条1項)の認識であった。
そうすると、非現住建造物等放火罪という軽い犯罪事実の認識で、現住建造物等放火罪という重い犯罪を行っているから、甲を現住建造物等放火罪で処断することはできない。
7. では、同行為に非現住建造物等放火罪が成立しないか。
⑴非現住建造物等放火罪に対応する客観的犯罪事実は物理的には存在しないため、規範的にみてこれが存在するといえば、罪刑法定主義に反し得る。しかし、38条2項は、直接には重い罪の成立を否定するものだが、構成要件が重なり合う場合には軽い犯罪が成立することを許容する規定と解すことができる。そのため、構成要件に重なり合いが認められる限度で、軽い罪の成立を認めることができる。
非現住建造物等放火罪と現住建造物等放火罪とはいずれも公共の安全を保護法益とし、行為態様も全く同一であるから、構成要件に重なり合いを認めることができる。
⑵また、Xが予測した因果の流れは、新聞紙を投げることによる焼損であり実際と異なるが、以下の理由から故意も肯定できる。
故意責任の本質は、犯罪事実の認識によって、規範の問題に直面し、反対動機が形成できるのに、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難である。犯罪事実は、刑法上構成要件として与えられるところ、行為者が事前に予見した因果経過と実際の因果経過とが、危険の現実化の範囲内で符合しているならば、認識と客観が構成要件的評価として一致しているといえるから、行為責任を問える。
甲が予見したのは、新聞を投げる行為の危険が焼損として現実化する因果経過といえ、上記実際の因果経過と、行為の「焼損」の危険が現実化したという範囲で符合するので故意も認められる。
⑶よって、Xに非現住建造物等放火罪(109条1項)が成立する。
第2問
1. XがA店に入店した行為は、「正当な理由」なく「建造物」に管理権者の意思に反する立ち入りをしているから「侵入」したといえ、建造物侵入罪(130条前段)が成立する。
2. Xがエーゲ海産の塩パック(以下、「本件塩パック」という。)をポケットの中に入れた行為につき、窃盗罪(235条)が成立するか。
⑴「他人の財物」とは、他人の所有物をいうところ、本件塩パックはAの所有物である。
⑵「窃取」とは、占有者の意思に反して、財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいう。Xは本件塩パックを素早く着用していたジャケットのポケットの中に入れており、意思に反する占有移転ということができる。もっとも、Xは未だ店内におり、追跡可能性があるから、占有移転が完了したとは言えないのではないか。
本件塩パックは、30グラムしかなく、ポケットの中に完全に収まっていて、ポケットが膨らんでいる状態でもなかったため、外見上、何かがポケット内に収まっているようには見えなかった。したがって、ポケットに入れた時点で占有は移転したといえる。
⑶また、ギリシャ料理を作るのに凝っており、どうしても本件塩パックが欲しく窃盗を行っているので、故意、不法領得の意思に欠けるところもない。
⑷よって、窃盗罪が成立する。
3. XがBに対しナイフを突きつけて「動くな」と申し向けた行為につき、強盗罪(236条1項)が成立するか。
⑴上述の通り、窃盗が既遂に達しているため窃盗の既遂後に脅迫を加えた場合に強盗罪が成立しうるかが問題となるも肯定すべきである。すなわち、強盗の故意のもとにまず財物を窃取し、次いで被害者に暴行・脅迫を加えてその奪取を確保した場合も成立すると解する。
⑵「脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足る程度のものである必要がある。
Xは25歳の男性であるのに対し、店員Bは63歳女性であって、Xは体格において勝っており、そのようなXが刃渡り6センチメートルのナイフという殺傷能力の一手程度認められる凶器を、対抗しうる武器を所持しないBに突きつけ、小さな声で「動くな」申し向ける行為は、相手方の反抗を抑圧する程度の「脅迫」といえる。
⑶ これにより、Bの反抗が抑圧され、Xは店を出て本件塩パックの占有を確保したと言えるから、本件塩パックを「強取」したといえる。
⑷故意、不法領得の意思にかけるところもないから、強盗罪が成立する。
4. XがCにナイフを取り出し、突進した行為につき、2項強盗罪(236条2項)が成立するか。
⑴「財産上…の利益」は、財産的利益一切をいい、債務免除や支払い猶予を得るなどの消極的利益も含むが、1項との均衡から、具体的直接的な利益に限定されると解する。
Xの本件塩パックの返還を免れる利益は、「財産上…の利益」といえる。
⑵Xは上述のナイフを向けて突進しており、刺さるどころによってはCの生命の侵害に至りかねない。Cは警備員であって柔道の経験があるといっても対抗できる武器を有していなかったことを踏まえると、ナイフを取り出して突進する行為は相手方の反抗を抑圧するに足る程度の「暴行」といえる。
⑶財産上…の利益「得」たというためには、財物の移転と同視し得る確実性を要するから、現実に財産上の利益を取得すること、すなわち、債権者による当該債務の追及が事実上不可能若しくは著しく困難になることを要する。財物の返還を免れる利益に関しては、返還請求権の行使を相当期間不可能ならしめるものに限り、財産上の利益を「得」たものと評価できると考える。
これまでも複数回万引きに成功していることからすると、Aに監視カメラが設置されていることを踏まえても、一度Aを出て帰宅すれば、被害品の即時の返還を求めることは相当困難なものとなる。そのため、財産上の利益を「得」る現実的危険が生じたといえる。
一方で、CはXを組み伏せて塩パックを取り戻しているから、本件塩パックの返還請求権の行使を相当期間不可能ならしめるには至っていない。
よって、未遂にとどまる。
⑶以上より、2項強盗罪の未遂罪(243条、236条2項)が成立する。
5. したがって、Xには、①建造物侵入罪、②窃盗罪、③強盗罪、④2項強盗罪未遂罪が成立する。②は③に吸収され、④とは、被侵害利益の共通性及び時間的場所的近接性に鑑み包括一罪となる。これは①と牽連犯(54条1項後段)となる。
以上





