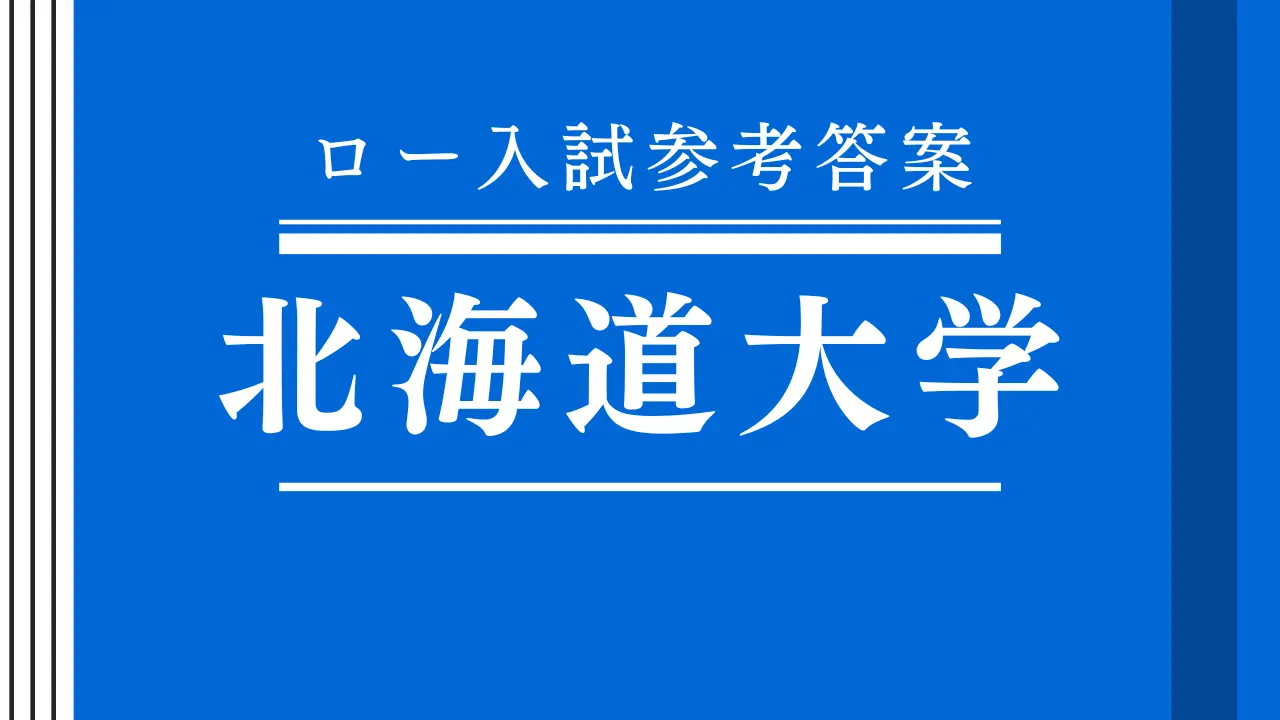
2023年 憲法 北海道大学法科大学院【ロー入試参考答案】
2/29/2024
The Law School Times【ロー入試参考答案】
北海道大学法科大学院2023年 憲法
第1問
1. 公職選挙法(以下「法」という。)138条1項は個別訪問を禁止しているところ、同規定は憲法21条1項に反し、違憲ではないか。
⑴ 憲法21条1項は「表現の自由」としての政治活動の自由を保障するところ、法138条1項はこれを制限するものであるため、憲法21条1項の保障する権利を制約するものと認められる
⑵ もっとも、政治活動の自由も絶対無制約ではなく、「公共の福祉」のための必要かつ合理的制約に服する。
判例は、法138条1項について、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害(①戸別訪問が買収、利害誘導等の温床になり易く、②選挙人の生活の平穏を害するほか、③これが放任されれば、候補者側も訪問回数等を競う煩に耐えられなくなるうえに多額の出費を余儀なくされ、④投票も情実に支配され易くなる等)を防止し、もって選挙の自由と公正を確保することを目的としているものであると位置づけた上で、上記のような目的は正当であり、それらの弊害を総体としてみるときには、戸別訪問を一律に禁止することと禁止目的との間に合理的な関連性があり、さらに戸別訪問の禁止によって失われる利益は、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的・付随的な制約にすぎない反面、禁止により得られる利益は、戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を防止することによる選挙の自由と公正の確保であるから、得られる利益は失われる利益に比してはるかに大きいとして、猿払事件において用いられた、いわゆる猿払基準を援用することにより、法138条1項は憲法21条1項に違反するものではないとしている。
猿払基準により、戸別訪問により政党や候補者の掲げる政策や候補者の人柄、能力について相手方が知る機会を広げるといった、政治活動の自由としての重要性を間接的・付随的制約であるという理由により低く評価することには批判も小さくなかった。
これに対し、伊藤正己補足意見は、戸別訪問は選挙という政治的な表現の自由が最も強く求められるところで、その伝達の手段としてすぐれた価値をもつものであり、これを禁止することによって失われる利益は、議会制民主主義のもとでみのがすことができないとした上で、戸別訪問の禁止は、選挙運動を行う者に選挙運動という一種の競争を公平に行わせるための戸別訪間禁止というルールを一律に遵守するよう強制することによって公正な選挙の実現を確保するためのものであると理解し(選挙のルール論)、法138条1項による制約は、選挙の公正の確保という目的との間に合理的関連性を有しているため、憲法21条1項に違反しないとしている。
伊藤裁判官は戸別訪問の禁止により害される政治活動の自由を「これを禁止することによって失われる利益は、議会制民主主義のもとでみのがすことができない」として、戸別訪問禁止により害される利益を高く見積もった上でなお、戸別訪問を権利自由の制限という権利の論理ではなく、競走の公平・公正の確保という「制度の論理」たる上記ルール論をもって、ルール設定につき国会の裁量の幅広く、その立法裁量に委ねられているところが大きいと理解したものである。
⑶ 以上より、法138条1項は、憲法21条1項には違反しない。
2. 同法239条1項3号は法138条1項違反につき罰則を定めているところ、同規定は憲法31条に違反しないか。
⑴ 憲法31条は、法文上は刑事手続の法定を定めるにとどまるが、刑事手続の適正や、実態の法定・適正をも保障するものと解される。
⑵ 法138条1項は、前述の目的を有すること、構成要件の明文上も具体的危険の発生を要件としていないことから、戸別訪問罪を選挙の自由と公正に対する抽象的危険犯であると解されるところ、実際には行為の主体(行為者)、客体(相手方)の相違によってそのようなおそれのない場合がありることから、危険の存否や程度を無視して一律に戸別訪問行為を処罰する視定は、罪刑法定主義ひいては憲法31条に違反するものと解すべきとする立場もある。
しかし、上記選挙のルール論からすると、法が、現実に買収などの不正行為を誘発するという弊害を生ずる危険が存在するかどうかにかかわりなく、選挙運動としての戸別訪問を一律に禁止して違反者を処罰することとしているのは、戸別訪問行為が常に右のような法益侵害の危険を随伴するものと考えているからではなく、選挙運動という一種の競争を公平に行わせるためのルールをすべての選挙運動者に一律に及ぼすためであると解される。そうすると、ルールに違反した以上処罰をうけることとされていても、それが憲法31条に違反するとはいえない。
⑶ したがって、法138条1項及び239条1項3号は、憲法31条に違反しない。
3. よって、法138条1項及び239条1項3号は、合憲である。
第2問
1. Y個人に対する責任追及
衆議院議員であるYによる発言は、国会議員としての職務を行うにつきされたものであることが明らかであることから、仮に本件発言がYの故意又は過失による違法な行為であるとしても、国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員であるY個人はその責任を負わない、すなわち公務員の個人責任は否定されるべきだから、国会議員の行為が「議院で行った演説、討論又は表決」(憲法 51条)に該当するかを問わず、国会議員が「職務」上の行為について個人的に賠償責任を負うことはない。
よって、XのYに対する請求は認められない。
2. 国家賠償請求
⑴ 憲法 51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。」とする。その目的は、議員の職務の執行の自由を保障することにある。免責される「責任」は、一般国民ならば負うべき法的責任を意味し、政治的・道義的責任を含まない。
確かに、憲法51条は、法的責任の免除を定めているにすぎず、行為の違法性が阻却されるわけではない。もっとも、委員会における質疑等は、多数決原理による統一的な国家意思の形成に密接に関連し、これに影響を及ぼすべきものであり、あらゆる面から質疑等を尽くすことも国会議員の職務ないし使命に属するものであるから、質疑等においてどのような問題を取り上げ、どのような形でこれを行うかは、国会議員の政治的判断を含む広範な裁量にゆだねられている事柄とみるべきである。そして、憲法51条も、一面では国会議員の職務行為についての広い裁量の必要性を裏付けているものと解される。
そこで、判例は、国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や用を低下させる発言があった場合に、当該発言が「違法」(国賠法1条)であると認められるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解している。
⑵ 確かに、YはCが女性患者に破廉恥な行為をしている旨や、薬物を常用している等、真偽が明らかでなくCに対して不名誉な事実を摘示し、衆議院議員として適当とは言い難い発言を行っている。しかし、Yは、医療法の一部を改正する法律案の審議に際し、患者の人権を擁護する見地から問題のある病院に対する所管行政庁の十分な監督を求める趣旨で、A市のB病院の問題を取り上げて質疑を行ったものであり、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものとまでは認められない。そうすると、Yの発言は、「違法」とはいえない。
⑶ よって、国に対する国家賠償請求も認められない。
以上





