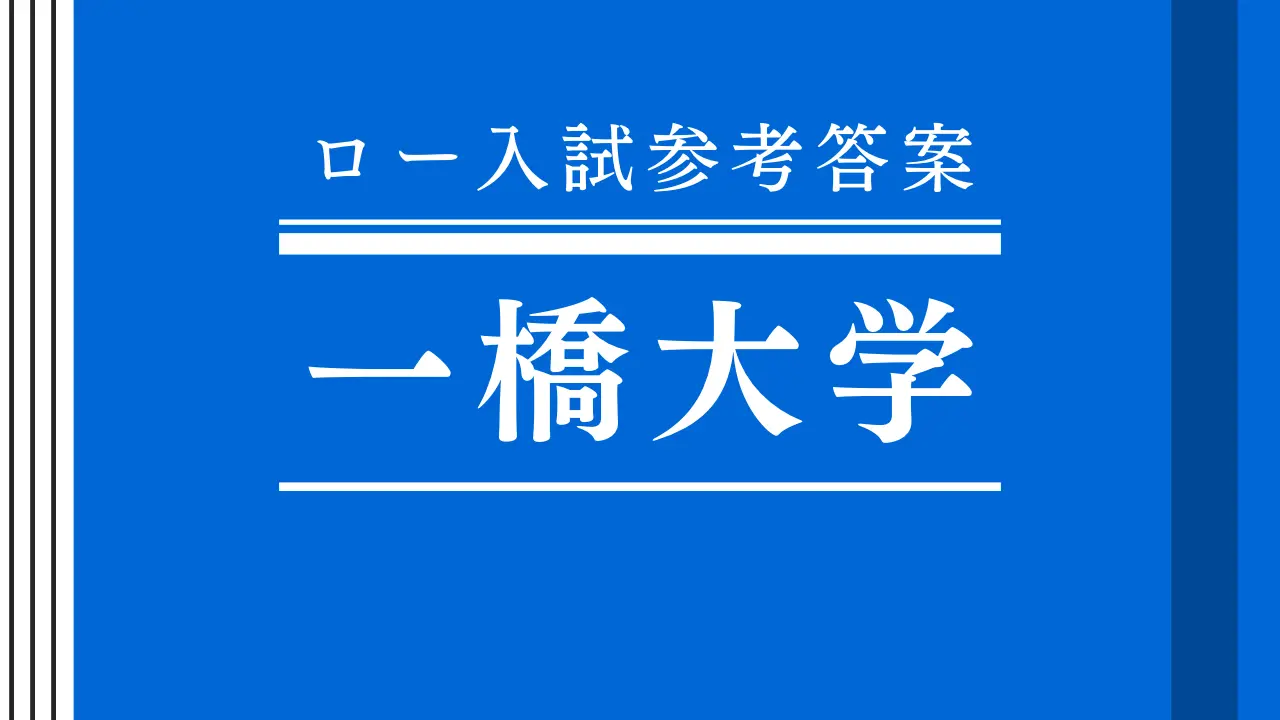
2025年 刑事訴訟法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2025年 刑事訴訟法
小問1
1. 本件では、Aは強盗致傷罪(刑法240条前段)の共謀共同正犯(刑法60条)として公訴提起されている。この起訴状に記載された訴因(公訴事実)が、刑事訴訟法(以下「法」)256条3項の要求する特定・明示の要件を満たしているか。共謀の日時・場所が具体的に記載されていない点、及び共犯者の一部が「氏名不詳者」とされている点が問題となる。
2.訴因の特定・明示の要請(法256条3項)
法256条3項は、「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」と規定する。
この規定の趣旨は、審判対象を明確にし、裁判所に審判を促す(審判対象画定機能)とともに、被告人に防御の範囲を告知し、有効な防御権行使を保障する(防御権保障機能)点にある。
したがって、訴因の特定は、他の犯罪事実から区別(識別)でき、かつ、被告人が防御の準備をなしうる程度に具体的であることを要する。
3. 共謀共同正犯の場合、訴因として特定すべき事実は、共謀の事実及び共謀に基づく実行行為である。
もっとも、法256条3項が「できる限り」と規定しているように、特定・明示の程度は、事案の性質や捜査の状況、防御の必要性等を考慮して、合理的に判断されるべきである。特に共謀の事実については、その性質上、日時・場所等が明確に判明しない場合もあり得る。判例も、共謀の日時・場所等が詳細に特定されていなくても、他の記載事項と総合して、いかなる犯罪事実であるかが具体的に認識でき、被告人の防御に不利益を生じさせない限り、訴因の特定に欠けるものではないとする。
4. ⑴ 本件訴因では、実行行為について、日時、場所、方法、被害者、被害品及び傷害結果が具体的に特定されており、実行行為に関する特定としては十分である。
⑵ア 本件訴因は、「Bおよび氏名不詳者らと共謀の上」と記載するのみで、共謀がなされた具体的な日時・場所を特定していない。
しかし、実行行為が上記の通り特定されている以上、共謀はそれに付随するものであり、他の犯罪事実から区別できる程度に特定されていると考えられる。 また、被告人Aの防御の観点からは、共謀の具体的内容が不明確であれば、アリバイの主張や共謀への不関与の主張が困難になる可能性がある。しかし、本件では共謀の相手方としてBが明示され、実行行為が詳細に特定されていることから、Aとしては、Bとの関係や実行行為期間中の自身の行動について防御を準備することは可能であると考えられる。
イ 共謀の相手方として「氏名不詳者ら」と記載されている点についても、特定の問題が生じうる。氏名不詳者を共犯者とすることは、捜査の結果、氏名が判明しなかった場合にやむを得ない措置として許容される。本件でも、アルバイトとして動員された者が氏名不詳であったとされており、捜査を尽くしても判明しなかったものであるから、「できる限り」特定したものと解するべきである
5. 以上の検討から、本件訴因の記載は、他の犯罪事実から区別(識別)でき、かつ、被告人が防御の準備をなしうる程度に具体的であるといえ、法256条3項にいう訴因の特定・明示の要件を欠くとはいえないと解される。したがって、本件訴因の記載は適法である。
小問2
1. はじめに
公訴提起後における勾留は、公訴提起前における勾留と比して、以下のような相違点がある。
2. 勾留の主体と手続
⑴ 起訴前勾留は、捜査段階における処分であり、検察官の請求に基づき、裁判官が決定する(法207条1項、204条、205条)。勾留状は裁判官が発付する(法207条5項)。
原則として、逮捕された被疑者に対してのみ請求できる「逮捕前置主義」が採用されている(法207条1項本文)。これは、より短期間の身体拘束である逮捕を経ずに、いきなり長期間の勾留を認めるべきではないとの配慮に基づく。
⑵ 起訴後勾留は、公訴提起後の被告人に対する処分であり、受訴裁判所(公判を担当する裁判所)が職権で、または検察官の請求に基づき行う(法60条1項、280条1項)。勾留状は裁判長または受命裁判官が発する(法64条1項)。
起訴後勾留については、起訴前の逮捕・勾留を経ている必要はなく、逮捕前置主義は適用されない。
3. 勾留期間
(1) 起訴前勾留における勾留期間は、原則として検察官が勾留請求した日から10日間である(法208条1項)。ただし、「やむを得ない事由」があるときは、検察官の請求により、裁判官が合計10日間を限度として延長できる(同条2項)。したがって、原則として最長20日間となる。
(2) 起訴後勾留の期間は、公訴提起があった日から2か月である(法60条2項)。その後は、「特に継続の必要がある場合」には、1か月ごとに決定をもって更新できる(同項)。
4. 釈放制度(保釈)
⑴ 起訴前勾留には、保釈(法88条以下)の制度はない(207条1項ただし書参照)。勾留されている被疑者が釈放されるのは、勾留の理由または必要性がなくなったとして勾留が取り消された場合(法87条、207条1項)や、勾留期間が満了した場合、不起訴処分となった場合などである。
⑵ 起訴後は、被告人またはその弁護人等は保釈を請求することができる(法88条1項)。
5. 接見交通権への制限(接見指定)
⑴ 捜査機関(検察官、検察事務官、司法警察職員)は、「捜査のため必要があるとき」は、裁判官に対し、弁護人等との接見の日時、場所、時間を指定するよう請求できる(法39条3項)。これは、被疑者が弁護人等を通じて罪証隠滅等を図ることを防止し、適正な捜査の遂行を確保するためである。
⑵法39条3項が「公訴の提起前に限り」と規定する通り、 裁判所は起訴後において職権で接見指定を行うことはできない。これは、起訴後は捜査段階とは異なり、被告人の防御権の保障がより強く要請され、また、罪証隠滅のおそれについても相対的に小さいと考えられるためである。
6. 公訴提起前における勾留は、公訴提起前における勾留と比してこのような違いが認められる。 以上





