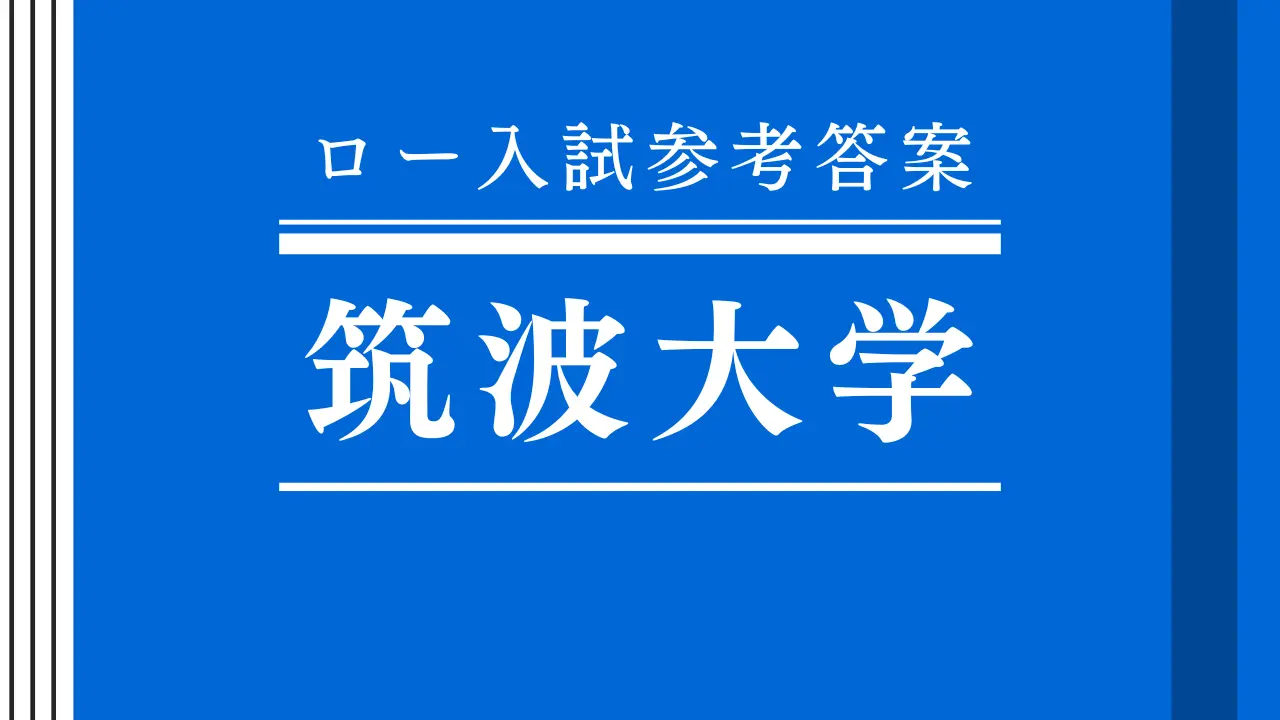
2025年 民法 筑波大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
筑波大学法科大学院2025年 民法
第1問(1)
1. DのEに対する、共有持分権に基づく丙建物の収去および甲土地の明渡し請求は認められるか。
2. Aの死亡により、DはAを相続し、甲土地の3分の1の持分権を取得している(882条、887条1項)。そして、Eは、甲土地上に丙建物を所有して甲土地を占有している。
3. もっとも、Dは、共同相続人であり、甲土地の3分の2の共有持分権を有するCから甲土地を賃借しているから、Eの甲土地の占有は、占有権原に基づくものと言えるのではないか。
⑴ここで、土地の賃貸借は管理行為(252条1項)であり、5年を超えない土地賃貸借は、多数持分権者が単独で行いうると解される(252条4項柱書、同項2号)。一方で、5年を超える土地賃借権の設定については明文の規定はない。各共有者は共有物の全部について、 持分に応じた使用をすることができる(249条1項)ことからすると、共有者の一部の者が、共有者の協議に基づかないで共有物を第三者に賃貸した場合に、それを承認しなかった他の共有者は、当該第三者に対して、当然にはその明渡しを請求できない。もっとも、5年を超える賃貸借は、処分と同程度に土地使用の制限になることからすると、処分の場合に準じて考えるべきである。すなわち、持分権を超える貸借については他人物賃貸借として捉える。
⑵本問では甲土地の賃借期間は30年であり、5年を超えるものであるから、Dの3分の1の持分部分については他人物賃貸借となると解する。
よって、Dの持分につき占有権原を対抗できない。
4. したがって、DのEに対する請求は認められる。
第1問(2)
1. HのCに対する所有権(206条)に基づく丁建物の収去および乙土地の明渡し請求は認められるか。
Hは、乙土地を所有しており、Cは、乙土地上に丁建物を所有して乙土地を占有している。
2. そこで、Cは法定地上権(388条前段)の成立を主張してこれを拒むと考えられる。かかるCの反論は認められるか。
⑴Cは乙土地上に丁建物を建築しているから、抵当権設定時である2028年4月25日には、土地及び建物が存在しており、Cは乙土地のDの持ち分を買い取り、丁建物にC名義の所有権保存登記がされているから、「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合」といえる。
そして、2028年4月25日に抵当権が設定されて、2029年7月15日に抵当権が実行され、Hへの所有権移転登記がされているので、「その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至った」といえる。
⑵もっとも、設定当時、抵当権が第2順位であったことから、第1順位の抵当権者が設定時に把握した担保価値を保護する必要があるのではないか。
ここで、更地の価値を把握すべく第1順位の抵当権が設定されているときに法定地上権を認めてしまうと、土地の担保価値が下落し、第1順位抵当権者にとっては、意外な結果となってしまう。また、抵当権設定当時、建物所有者は何らかの土地利用権を有していたはずである。そこで、法定地上権は原則として成立しないと解する。もっとも、第2順位抵当権実行時に、第1順位抵当権が消滅しているのであれば、第1抵当権者を保護する必要はないから、法定地上権を認められる。
2028年5月10日に、Bが甲土地および乙土地に有していた抵当権の登記が抹消されている。Gが抵当権を実行したのは、2029年5月15日のことであるから、第1順位抵当権者を保護する必要はなく、Cのための法定地上権を認めることができる。
3. したがって、Cの反論が認められ、HのCに対する請求は認められない。
第1問(3)
1. HのEに対する所有権に基づく丙建物の収去および甲土地の明渡し請求は認められるか。
2. Eは土地上に登記された建物を所有しており2026年9月10日に丙建物について登記を備えているから、対抗要件を備えている(借地借家法10条1項)と主張して、Hの主張を拒むことが考えられる。もっとも、その登記名義はEではなく、Eの長男であるFの名義なので、近親者名義の建物登記にも対抗力が認められるか問題となる。
他人名義の登記簿の記載からは当該建物の真の所有者が建物の所有者であることを推知することはできないから、これに借地権の対抗力を認めると、取引上の第三者の利益を害する。また、他人名義の建物登記によっては、自己の建物所有権すら第三者に対抗できないから、自己の建物所有権を対抗し得る登記のあることを前提としてこれを賃借権登記に代えようとする借地借家法の保護は得られないと解するのが自然である。そこで、近親者名義の建物登記には対抗力が認められないと解する。
よって、Eの反論は認められない。
3. したがって、Hの請求が認められる。
第2問
1. XはYに対して、数量に関する契約不適合責任(562条以下)を追及する。
⑴「目的物」が、「数量に関して契約の内容に適合しない」とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、一定の面積・容量・重量・員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められているときに、数量が不足している場合をいう。
⑵本問では、Yは「ブリ10キロ」を指し示しているから、一定の重量があることを売主が契約において表示している。そして、ブリは1キログラムあたり20,000円との札が貼られているので、10キログラムでは20万円となり、数量を基礎に代金額が算定されているといえる。
そして、10キログラムを購入したにもかかわらず、重量は実際には8キロしかなかったのであるから、数量が不足しているといえる。
よって、数量に関する契約不適合があるといえる。
2.⑴次に、XはYに対して、債務不履行責任(564条、415条1項、416条1項)に基づく損害賠償請求として、①不足分相当額であるブリ2キロ分の代金4万円と、②不足分の10食分をマグロステーキを無償で提供している分の代金と③精神的苦痛の損害賠償を請求する。
上記の通り、ブリ10キロを購入したのに実際には8キロ分しか入っていなかったので、数量に関する契約不適合があり、「債務の本旨に従った履行をしない」といえる。
また、Yは魚市場の店員として正確に計量をしなければならないから、損害のリスクは売主側で負っていたといえる。よって、Yに債務不履行についての帰責性が認められる(同条但書)。
したがって、損害賠償をすることができる。
⑵では、①から③のいずれについて請求することができるか。
ここで、416条2項は、1項が定める相当因果関係の原則の例外を定め、当事者間の公平を図るものである。そこで、特別事情の予見可能性については、債務不履行時までに債務者がその事情を予見すべきであったことと解する。
①は通常損害として認められるが、②③は、特別損害(416条2項)にあたるから、その予見可能性が問題となる。
Xはなじみの水産業者Yに営業日最後のランチメニューとして、ブリの照り焼きを通常価格の半額でご予約のお客様に提供すること、ブリの手照り焼きを70食作るためには、10キロ前後のブリが必要であることを伝えている。そのような重要な機会であることをYは認識しており、そこで数量が足りなければ何か代替措置を取ることになること、また、江戸時代から続いた老舗の料亭の最後の日に、客との約束を守れなければ精神的苦痛を感じることを予見すべきであった。
したがって、②③については、特別損害として請求することができる。
3. もっとも、契約不適合責任は期間制限に服する(566条)。
「買主がその不適合を知った時」とは、売主に対し契約不適合責任を追及し得る程度に確実な事実関係を知った時をいうところ、Xが契約不適合を知ったのは2024年12月31日であり、Xが請求した2025年1月5日であるから、「1年以内にその旨を売主に通知しない時」に当たる。
もっとも、売主はが適正な重量を測って買主に渡す義務を負っているにもかかわらず、注意を怠ったといえ、「重大な過失」によってこれを「知らなかった」といえる。
よって、期間制限には服さず、XはYに対して請求できる。
4. したがって、Xの請求は認められる。
以上





