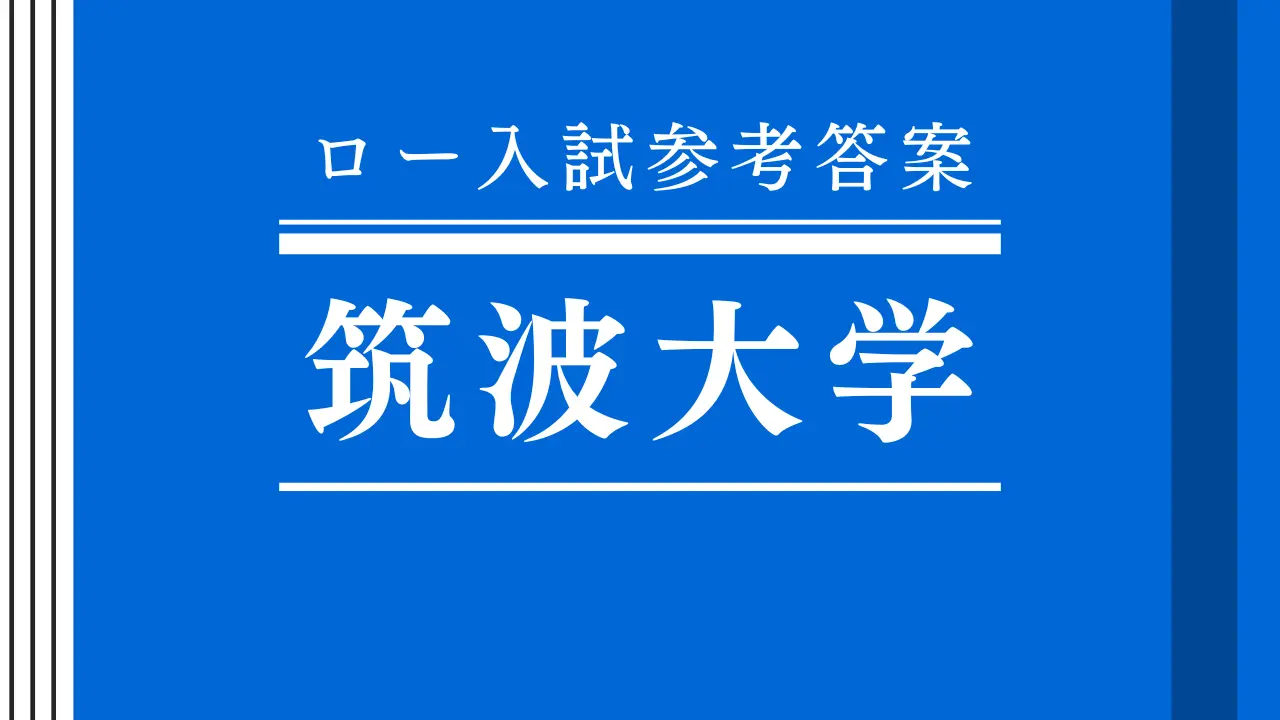
2021年 民事法 筑波大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
筑波大学法科大学院2021年 民事法
民法
第1問
設問⑴
1. CはDに対する丙部分の所有権(民法(以下、法令名略)206条)に基づく妨害排除請求権として所有権移転登記手続請求を求めることはできるか。
⑴ 丙部分は甲土地に含まれており、現在、甲土地全体についてD名義の所有権移転登記がなされている。そのため、Cに丙部分の所有権があれば上記請求を求めることができる。
⑵ もっとも、丙部分を含む甲土地はもともと所有していたAからDが売買契約(555条)により取得した土地であり、丙部分をCが取得した経緯はない。そこで、Cは、丙部分の時効取得(162条1項)を援用することにより丙部分の所有権を取得することができないか。
ア まず、丙部分は2000年7月1日からBが占有し、その後Bの子であるCが相続(887条1項882条)し2004年3月から継続して占有している。Cは、Bから相続により占有を承継したといえるところ、どちらを時効の起算点にするかはその承継人の選択に従って決することができる(187条1項)。
イ そこで、本件について、まずBが占有を取得した2000年7月1日を起算点として選択した場合について検討する。
(ア)Bは占有時点において、丙部分が乙土地に含まれないことを知っていたため、自己が丙部分の所有者ではないことを知っていたといえる。そのため、取得時効の適用条文は善意無過失を要求する162条2項ではなく、同条1項となる。
そして、Cは2020年7月1日時点において丙部分を駐車場として利用し占有しているから、Bの占有開始時点から20年占有していたことが推定でき(186条2項)これを覆滅させる事情もない。
また、「所有の意思」「平穏」「公然」は推定され(168条1項)、駐車場として舗装しながら継続的に使用しており、これらの推定を覆滅させる事情もない。
したがって、2020年7月1日に162条1項の取得時効が成立する。
(イ) もっとも、DはAから2016年5月1日に甲土地を購入し所有権移転登記を完了している。そこで、Cは丙部分の時効取得を時効完成時点の所有者たるDに登記なくして対抗することができるか。
この点について、時効による権利の取得は原始取得であるため、時効完成時の所有者は物権変動の当事者ではない。
しかし、一方の権利取得の結果として他方が権利を失うという関係は権利移転の場合と同様のため、物権変動の当事者と同視することができる。
そこで、時効取得者は時効取得を時効完成時の所有者に対して登記なくして対抗できると解する。
したがって本件において、CはDに対し登記なくして丙部分の所有権の時効取得を対抗することができる。
ウ 次に、Cが相続を受け占有が承継された時点である2003年8月1日時点を時効の起算とした場合について述べる。
(ア) まず、善意は186条1項で推定される。
また、丙部分はBが生存の時点から自己の自動車の駐車場として利用しており、駐車場として利用されていることにつきAも何も述べてこなかった。そのため、Bから占有を承継したCが自己が丙部分の所有者であると誤信したことにつき過失があったとはいえない。
そのため、起算点を2003年8月1日にした場合には、時効の適用条文は162条2項となる。
そして、前述の通り「所有の意思」「平穏」「公然」は推定され、覆滅する事情もない。
また、Cは2013年8月1日時点も丙部分を駐車場として利用しており、占有している。
したがって、2013年8月1日に、Cの丙部分についての取得時効が成立する。
(イ) もっとも、時効完成後にDが甲土地の所有権を取得し、所有権移転登記をなしているところ、CはDに登記なくして丙部分の時効取得を対抗することができるか。
この点について、時効取得による権利取得は原始取得であるが、時効完成後の第三者との関係では、元所有者から、それぞれ時効取得者、第三者への二重譲渡があった場合と同視することができる。
そこで、時効取得者と時効完成後の第三者は、対抗関係に立つといえ、時効取得者は登記なくして取得を対抗することはできないと解する。
そのため、登記を有していないCはDに対して丙の時効取得を対抗することができない。
2. 以上を踏まえると、Bが占有を開始した2000年7月1日を時効の起算点とした場合のみ、Cは丙部分の所有権の取得時効をDに対抗することができ、上記請求が認められる。
設問⑵
1. CはDに対する丙部分の所有権(206条)に基づく妨害排除請求権として所有権移転登記手続請求を求めることはできるか。
⑴ まず、前述の通り、CがDに丙部分の所有権を主張できれば、上記請求は認められる。
⑵ そこで、Cが丙部分を時効により取得できるかについてみる。
ア Bが占有を開始した2000年7月1日を時効の起算点としてみると、時効が完成するのに20年要するところ、まだ20年経過していないためそもそも時効による取得ができない。
イ 次にCが占有を開始した2003年8月1日を起算点とすると、前述の通り2013年8月1日に取得時効が完成する。
そして、Cの時効完成後に、DがAから甲土地の所有権を取得して所有権移転登記をなしているところ、前述の通り、時効完成者と時効完成後の第三者は対抗関係に立つため、登記を有していないCはDに対して丙部分の時効による取得を対抗することができない。
2. 以上より、Cはいずれの場合でもDに対して丙部分の時効による取得を対抗することができないため、上記請求は認められない。
設問2
1. DはAに対して保証人の求償権(459条1項)に基づいて1050万円の支払請求をすること考えられるが、かかる請求は認められるか。
⑴ まず、DはAから、AがCから1000万円の融資を受ける際の連帯保証人になってくれという依頼を受けてCとの間で保証契約を締結しているため、Dの保証は「債務者の委託を受けて保証した場合」といえる。
そして、DはAの代わりに「自己の財産をもって」AのCに対する債務の弁済として利息を含む1050万円を支払ってかかる債務を消滅させている。
したがって、DのAに対する1050万円の求償権が生じたており、上記請求を行うことができる。
⑵ もっとも、Aは甲土地を売却しており、めぼしい財産が存在しないため、上記請求をしたとしても金銭回収の見込みは薄い。
2. そこで、DはFに対して、DのAに対する1050万円の金銭債権を被保全債権として、AからEへの甲土地の売買契約を詐害行為として裁判所に取消を求める(424条の5柱書)とともに、甲土地を自己に返還請求(424条の6第2項)をすると考えられる。かかる請求は認められるか。
⑴ まず、上記のとおり、被保全債権としてDのAに対する1050万円の債権が存在するためDは「債権者」である。
そして、詐害行為は被保全債権の発生原因より後である必要があるところ、被保全債権が生じたのはDがCに1050万円支払った2021年11月5日であり、Dが詐害行為として指定するEF間の甲土地の売買契約は2021年9月1日と被保全債権の発生より前である。もっとも、求償権の発生原因は連帯保証契約の締結と考えられるところ、連帯保証契約の締結は2020年11月1日であり、詐害行為より前である。そのため、詐害行為は被保全債権の発生原因より後に行われたといえる。
そして前述の通り、債務者たるAにはめぼしい財産がなく無資力といえるから、Dは自己の1050万円の債権を保全する必要があるといえる。
また、Aは甲土地という財産をEに売却するという財産的行為を行っており、かかる行為により得られる金銭はすべてB名義の口座にいくことになり、DがAから直接に債権を回収することはできなくなりDを害する行為といえる。そして、Aも自身にめぼしい土地が甲土地しかなく、かかる行為を行えば、連帯保証人の地位にいるDが債権回収の見込みがなくなる点で害することも当然認識していたといえる。したがって、「債権者を害することを知ってした行為」といえる。
そして、Aから甲土地を受益したEは、AからA社の経営が悪いこと、万が一のためにB名義の口座に振り込んでほしい旨伝えられている。この時連帯保証契約の存在などについて知らされていないもののAの経営状態悪化の点からAに債権者がいること、金銭を振り込む相手方がAではなくBということから、このような行為をすればAの債権者を害することをEは知っていたといえる(424条1項但書)。
したがって、Eに対して「詐害行為取消請求をすることができる場合」にあるといえる。
そして、FはEからAの甲土地売却の経緯について聞いているため、転得時にFもAの債権者を害することについて知っていたといえる(424条の5第1号)。
よって、Dの上記詐害行為取消請求は認められる。
⑵ また、現在Fは詐害行為により得た甲土地を所有しているため、Dの甲土地の返還請求も認められる。
民事訴訟法
設問
1. Xの第2訴訟における相殺の抗弁の主張は許されるか。民事訴訟法(以下、略)142条に反しないかが問題となる。
⑴ 142条の趣旨は、判決の矛盾、被告の応訴の煩及び訴訟不経済を回避する点にある。この点、たしかに相殺の抗弁は、攻撃防御方法にすぎず「訴えを提起」に当たらない。しかし、第2訴訟における相殺の抗弁に係る債権は、すでに第1訴訟において請求されている債権と同一債権である以上、審理が重複する。また、相殺の抗弁には、既判力が生じる(114条2項)から判決の矛盾抵触のおそれがあることも否定できない。したがって、142条の趣旨が妥当するから本件でも相殺の抗弁は142条に反し許されないとも思える。
⑵ しかし、本件のように相殺の抗弁が後から出された場合に142条に反するとすると、相殺の抗弁を主張するためには、前訴の訴えを取り下げる必要がある。しかし、これには相手方の同意が必要(261条2項本文)であり、相殺の抗弁の可否は相手の同意に依存することになってしまう。もっとも、これでは、相殺の有する簡易決済機能及び担保的機能が害されてしまう。
⑶ そこで、相殺の抗弁が後訴でなされている場合には、相殺の上記機能を重視して、相殺の抗弁の主張は142条に反しないと考えるべきである。
⑷ 以上より、本件では、第1訴訟に係る債権の残部について第2訴訟で相殺の抗弁がなされているが、かかる相殺の抗弁の主張は142条に反せず許される。
以上





