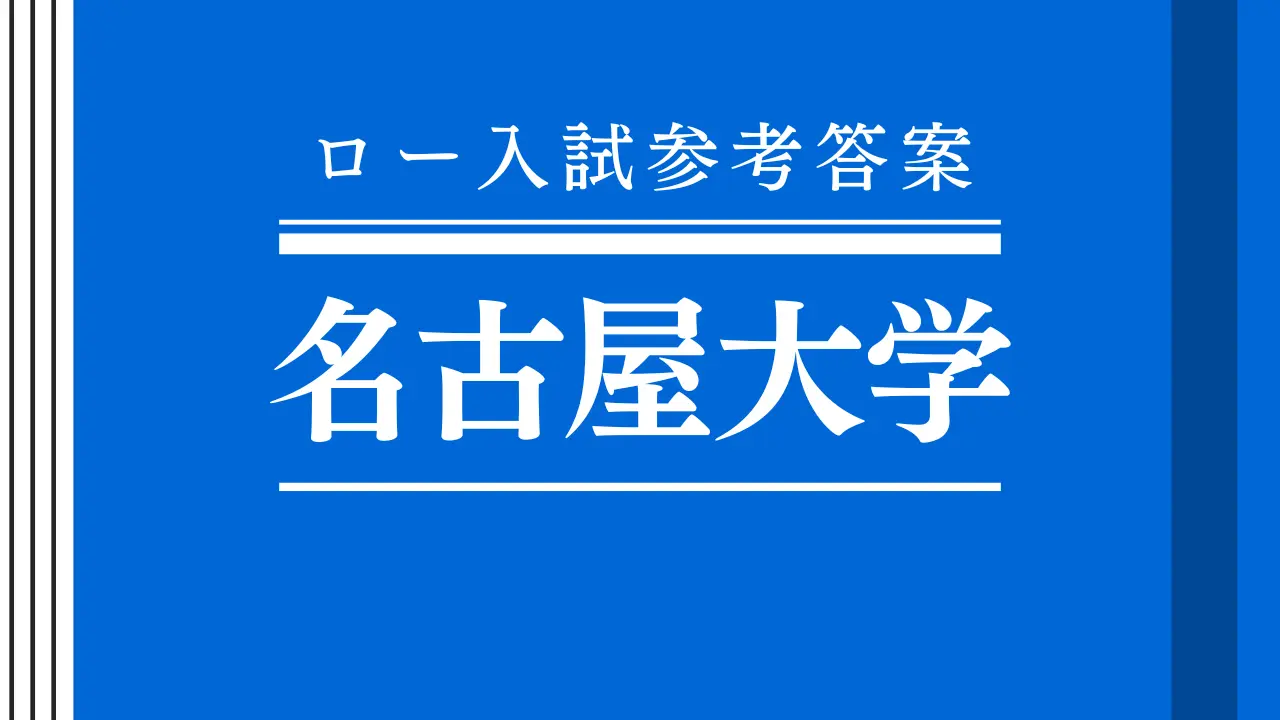
2024年 行政法 名古屋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/26/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
名古屋大学法科大学院2024年 行政法
設問Ⅰ⑵
法律の留保の原則とは、行政の行為のうち一定の範囲のものについて、その行為の着手に当たり法律の承認を要求する原則である。そして、侵害留保説とは法律の留保の原則の適用範囲を国民の権利自由を権力的に侵害する行政に限定するとするものであり、国民に権利を与え、又は義務を免じるものについては適用範囲外とするものである。
同説の根拠としては、法律の留保の原則の趣旨が国民の代表からなる議会の事前承認を義務付けることで、国民の権利自由を保護することにあるところ、国民の権利を制約し義務を課す侵害行政については自由主義的見地から法律の根拠を要求すべき一方、国民や公衆に便益を与える給付行政については、法律で縛ることなく行政の自由度を高めておく方が、むしろ国民の利益になることにある。同説に対する批判としては、行政作用は全て国民の意思に基づきなされるべきであるから、給付行政も議会の事前承認を得るべきであるとするものがある。
設問Ⅲ
1. 本件指導・指示は、「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に当たるか。
⑴「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
そこで、公権力性、法効果性を有する場合に処分性が認められると考える。そして、公権力性は法が認めた優越的地位に基づき、行政庁が法の執行としてする権力的な意思活動であるかによって判断し、紛争の成熟性も加味して決する。
⑵公権力性について、処分性を肯定する見解からは、法27条の指導や指示は従わなければならない旨が規定されており(62条1項)、C市に優越的地位が認められると主張する。
しかし、指導や指示と言った強制力の弱い言葉が使われ、また、27条1項の規定は強制し得るものと解釈してはならないとされていることから(同条3項)、C市の法が認めた優越的地位に基づく権力的な意思活動とは言えず、本件指導・指示に公権力性は認められない。
⑶次に、法効果性について、処分性を肯定する見解からは、本件指導・指示に応じなかった場合、生活保護が変更、停止又は廃止されてしまう可能性があり(62条3項)、また生活保護が廃止されてから指導・指示の効力を争うのでは原告の権利救済に欠けるのであり、本件指導・指示の時点で紛争が成熟しているといえるため、法効果性も認められるという主張する。
しかし、62条3項は生活保護の変更、停止又は廃止をすることができる旨が定められており、必ずしも廃止等がされるとも限らず、また廃止等の段階で初めて弁解の機会を与えていること(同条4項)から、法は廃止等で初めて紛争が成熟すると考えていると考えられ、本件指導・指示の段階でA及びBが取消訴訟を提起するのを認める必要性は小さい。よって、本件指導・指示に法効果性も認められない。
2. 以上より、本件指導・指示は、処分に当たらない。
以上





