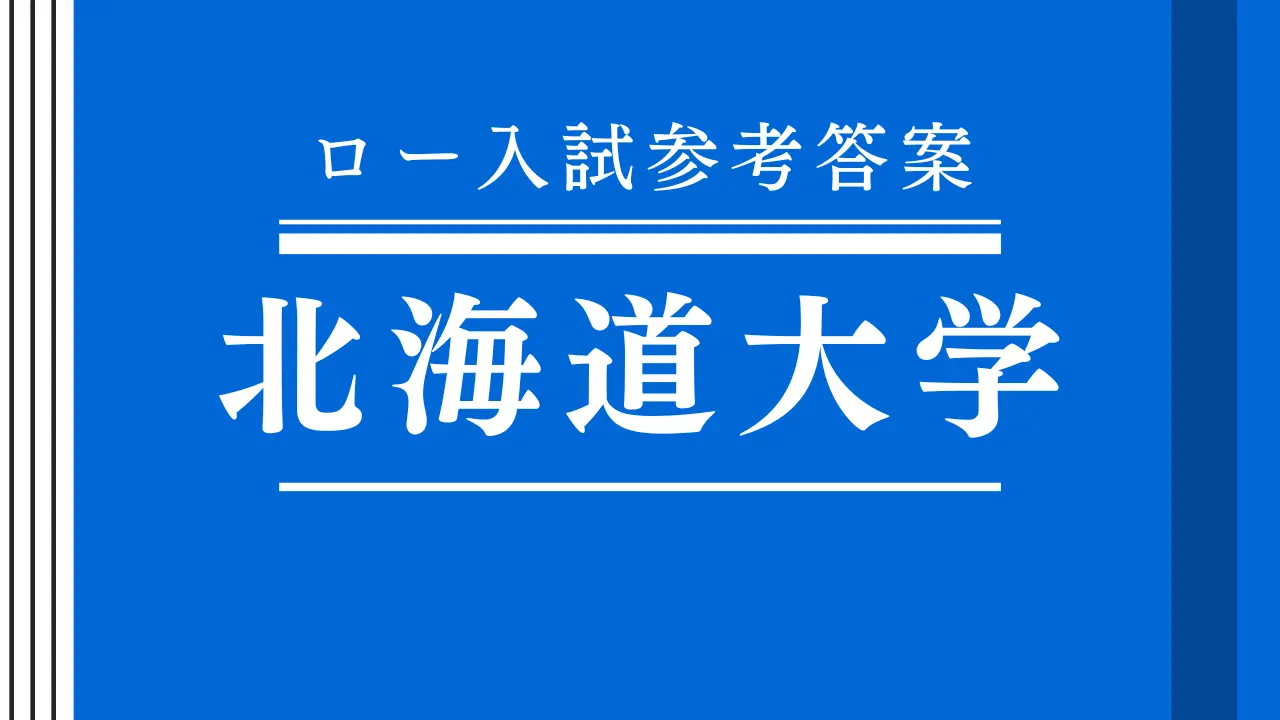
2022年 刑法 北海道大学法科大学院【ロー入試参考答案】
10/26/2023
The Law School Times【ロー入試参考答案】
北海道大学法科大学院2022年 刑法
第1問
1. Xに殺人罪(刑法(以下略)199条)と同意殺人罪(202条)のいずれが成立するか。
⑴ AはXが用意した毒物を自ら嚥下して死亡しているが、AはXが一緒に心中してくれると信じており、2人で死ぬことを前提として毒物を自ら嚥下している。このような作木がある場合にAの「承諾」(202条)があるといえるか。
ア ②の立場からは、いわゆる法益関係的錯誤説による説明が考えられる。かかる見解は、被害者が自殺すること自体は理解しているような動機の錯誤がある場合にまで自殺意思を無効にするのは妥当ではないとして、法益侵害の有無・程度など法益に関する錯誤がある場合に限って同意を無効とすべきであるとする説である。
本件では、Xが一緒に心中した場合としなかった場合のいずれにおいても生命という法益を侵害されることにつき、Aに錯誤はない。
よって、法益に関する錯誤はなく、②の立場によるとAの有効な「承諾」があるといえ、Xに同意殺人罪が成立することになる。
イ しかし、動機の錯誤にも程度があり、些細な錯誤のみならず、意思決定の過程において重大な動機の錯誤があった場合にまで同意を有効としうる上記説は妥当でない。また、動機の錯誤と法益に関する錯誤とを完全に区別しうるかについても疑問である。
そこで、①の立場に立つべきである。①の立場からは、いわゆる重要な錯誤説による説明が考えられる。かかる見解は、被害者の意思決定に重要な影響を与えるような重要な錯誤がある場合には同意を無効とすべきとする説である。
本件では、AはXに対し心中することを提案し、それに対しXは頷いて一緒に心中するように見せかけている。また、Aは「一人で死ぬのは嫌よ」と述べたのに対し、Xが「生まれ変わったら一緒になろうね」等と述べることでAと一緒に心中するように見せかけたことによって、AはXが一緒に心中すると信じて死亡するに至っている。AはXと不倫関係にあったのに加え、自殺することは苦痛を伴うため、Xが一緒に心中してくれるか否かは、自殺意思の決定において重要な影響を与えるものであるといえる。よって、かかる事項につき重要な錯誤があった。
したがって、Aには有効な「承諾」があるとは言えず、同意殺人罪は成立しない。
⑵ そこで、殺人罪の成否について検討する。Xは、Aに一緒に心中するかのように見せかけ、Aの錯誤を利用してAを殺害しようと考えている。そして、Aに毒物を差し出してAをして毒物を嚥下させ、死亡させている。
そこで、間接正犯が正犯たりうるかが問題となる。
ア 正犯とは、自ら実行行為をなす者をいうところ、特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思のもと、他人を道具として一方的に支配・利用していた場合には、間接正犯も正犯たりうると解する。
イ 本件では、Xは、Aから妻と離婚し自分と結婚することを執拗に迫られ、Aが心中を提案してきたのを契機に、Aを死亡せしめてAとの関係を精算しようと考えているため、Xには殺人という特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思がある。また、Xは、Xも一緒に心中してくれるものと誤信したAに毒物を差し出して死亡させており、他人たる被害者Aを道具として一方的に支配・利用していたといえる。
よって、正犯たりうる。
2. 以上より、Xの行為に殺人罪が成立し、Xはかかる罪責を負う。
第2問
1. 小問⑴
Xが、Dに対してご振込の事実を秘して30万円の払戻しを請求して現金30万円を受け取った行為につき、詐欺罪(246条1項)が成立するか。
⑴ 「欺」く行為とは、錯誤に向けられた財物交付の基礎となる重要な事実を偽る行為をいう。
本件では、確かに、Xは積極的にDに対して錯誤に落ち入れようとする言動を発するなどの作為を行っていない。そこで、かかる不作為も実行行為にあたるか。
ア 実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為をいうところ、不作為によっても法益侵害は可能であるから、不作為も実行行為たりうると解する。もっとも、自由保障の見地から、不作為が作為と構成要件的に同価値である場合に限り、不作為も実行行為たりうると解する。具体的には、法的作為義務が存在し、かつ作為の可能性・容易性が認められることが必要と解する。
イ 本件で、自己の口座に誤振込みがあった場合には誤振込みがあった旨を告げる信義則(民法1条2項)上の作為義務があると解される。そして、係員に告知することは可能かつ容易である。
よって、Xの不作為も詐欺罪の実行行為にあたり、誤振込みのあった預金の受取人が通帳名義人本人であるかは交付の基礎となる重要な事実であるといえ、かかる事実を偽ったとして「欺」く行為にあたる。
⑵ そして、Dはかかる「欺」く行為により、錯誤に陥っている。
⑶ 「交付した」とは、錯誤に基づく瑕疵ある意思に基づいて、財物の占有を終局的に移転させることをいう。本件では、誤振込みされた財物たる30万円の占有がQ支店にあるかが問題となる。
ア 占有の有無の判断は、占有の意思と占有の事実の両側面を総合して判断する。
イ 本件で、確かにX名義の口座に預金が存在して、Xはキャッシュカードを保有して事実上払戻しが可能である。しかし、Xには誤振込み預金に対する正当な受取権限はない。また、Xは元々残高が0円であって30万円の払戻しは不可能だったのであるから、Xが誤振込み預金を占有する事実も意思もない。かかる誤振込み預金は、本来Bに正当な払戻権限があるものであり、誤振込みの状態においてはQが事実上支配し、占有の意思を有していると解するべきである。
よって、DがXに払い戻した行為は、「交付した」といえる。
⑷ また、Qには30万円という財産上の損害が生じている。
⑸ 以上より、Xの上記行為に詐欺罪が成立し、Xはかかる罪責を負う。
2. 小問(2)
XがATMから誤振込金30万円を引き出した行為につき、窃盗罪(235条)が成立しないか。
⑴ Xの口座残高は0円であり、30万円はAが誤振込みをしたものに違いないから、Xが引き出した現金30万円は「他人の財物」にあたる。
⑵ 「窃取した」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有支配下に移転させることをいう。
前述の通り、誤振込み預金に関しての占有は銀行にあると解するべきであり、本件における30万円の占有はQにある。
よって、Xによる30万円の引き出し行為は、他人たるQが占有する財物をQの意思に反して自己の占有支配下に移転する行為といえ、「窃取した」といえる。
⑶ また、主観的構成要件要素として、不可罰的な使用窃盗との区別及び毀棄隠匿罪との区別の見地から、いわゆる不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞う意思および物の経済的用法に従って利用処分する意思)が必要と解する。
本件で、誤振込み預金を引き出す行為は、正当な権限がなければできない行為である。また、XはCに対する借金を返すために引き出しており専ら毀棄隠匿目的ではない。
よって、上記の振る舞う意思および利用処分意思があるといえ、不法領得の意思が認められる。
⑷ 以上より、Xの上記行為に窃盗罪が成立し、Xはかかる罪責を負う。
3. 小問⑶
XがATMを使用してR支店のCの口座に振替送金した行為につき、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)が成立するか。
⑴ ATMは、「人の事務処理に使用する電子計算機」にあたる。
⑵ Xは、実際には自己の預金ではなく誤振込みによるものであるのに、30万円の預金残高があるとみせかけ、ATMを操作してCに同30万円を振替送金しているところ、「不正な指令を与え」て、「財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録」を作ったといえる。
⑶ そしてXは、Cに対する30万円の債務を免れ、「財産上不法の利益を得」たといえる。
⑷ 以上より、Xの上記行為に電子計算機使用詐欺罪が成立し、Xはかかる罪責を負う。
第1問
1. Xに殺人罪(刑法(以下略)199条)と同意殺人罪(202条)のいずれが成立するか。
⑴ AはXが用意した毒物を自ら嚥下して死亡しているが、AはXが一緒に心中してくれると信じており、2人で死ぬことを前提として毒物を自ら嚥下している。このような作木がある場合にAの「承諾」(202条)があるといえるか。
ア ②の立場からは、いわゆる法益関係的錯誤説による説明が考えられる。かかる見解は、被害者が自殺すること自体は理解しているような動機の錯誤がある場合にまで自殺意思を無効にするのは妥当ではないとして、法益侵害の有無・程度など法益に関する錯誤がある場合に限って同意を無効とすべきであるとする説である。
本件では、Xが一緒に心中した場合としなかった場合のいずれにおいても生命という法益を侵害されることにつき、Aに錯誤はない。
よって、法益に関する錯誤はなく、②の立場によるとAの有効な「承諾」があるといえ、Xに同意殺人罪が成立することになる。
イ しかし、動機の錯誤にも程度があり、些細な錯誤のみならず、意思決定の過程において重大な動機の錯誤があった場合にまで同意を有効としうる上記説は妥当でない。また、動機の錯誤と法益に関する錯誤とを完全に区別しうるかについても疑問である。
そこで、①の立場に立つべきである。①の立場からは、いわゆる重要な錯誤説による説明が考えられる。かかる見解は、被害者の意思決定に重要な影響を与えるような重要な錯誤がある場合には同意を無効とすべきとする説である。
本件では、AはXに対し心中することを提案し、それに対しXは頷いて一緒に心中するように見せかけている。また、Aは「一人で死ぬのは嫌よ」と述べたのに対し、Xが「生まれ変わったら一緒になろうね」等と述べることでAと一緒に心中するように見せかけたことによって、AはXが一緒に心中すると信じて死亡するに至っている。AはXと不倫関係にあったのに加え、自殺することは苦痛を伴うため、Xが一緒に心中してくれるか否かは、自殺意思の決定において重要な影響を与えるものであるといえる。よって、かかる事項につき重要な錯誤があった。
したがって、Aには有効な「承諾」があるとは言えず、同意殺人罪は成立しない。
⑵ そこで、殺人罪の成否について検討する。Xは、Aに一緒に心中するかのように見せかけ、Aの錯誤を利用してAを殺害しようと考えている。そして、Aに毒物を差し出してAをして毒物を嚥下させ、死亡させている。
そこで、間接正犯が正犯たりうるかが問題となる。
ア 正犯とは、自ら実行行為をなす者をいうところ、特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思のもと、他人を道具として一方的に支配・利用していた場合には、間接正犯も正犯たりうると解する。
イ 本件では、Xは、Aから妻と離婚し自分と結婚することを執拗に迫られ、Aが心中を提案してきたのを契機に、Aを死亡せしめてAとの関係を精算しようと考えているため、Xには殺人という特定の犯罪を自己の犯罪として実現する意思がある。また、Xは、Xも一緒に心中してくれるものと誤信したAに毒物を差し出して死亡させており、他人たる被害者Aを道具として一方的に支配・利用していたといえる。
よって、正犯たりうる。
2. 以上より、Xの行為に殺人罪が成立し、Xはかかる罪責を負う。
第2問
1. 小問⑴
Xが、Dに対してご振込の事実を秘して30万円の払戻しを請求して現金30万円を受け取った行為につき、詐欺罪(246条1項)が成立するか。
⑴ 「欺」く行為とは、錯誤に向けられた財物交付の基礎となる重要な事実を偽る行為をいう。
本件では、確かに、Xは積極的にDに対して錯誤に落ち入れようとする言動を発するなどの作為を行っていない。そこで、かかる不作為も実行行為にあたるか。
ア 実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為をいうところ、不作為によっても法益侵害は可能であるから、不作為も実行行為たりうると解する。もっとも、自由保障の見地から、不作為が作為と構成要件的に同価値である場合に限り、不作為も実行行為たりうると解する。具体的には、法的作為義務が存在し、かつ作為の可能性・容易性が認められることが必要と解する。
イ 本件で、自己の口座に誤振込みがあった場合には誤振込みがあった旨を告げる信義則(民法1条2項)上の作為義務があると解される。そして、係員に告知することは可能かつ容易である。
よって、Xの不作為も詐欺罪の実行行為にあたり、誤振込みのあった預金の受取人が通帳名義人本人であるかは交付の基礎となる重要な事実であるといえ、かかる事実を偽ったとして「欺」く行為にあたる。
⑵ そして、Dはかかる「欺」く行為により、錯誤に陥っている。
⑶ 「交付した」とは、錯誤に基づく瑕疵ある意思に基づいて、財物の占有を終局的に移転させることをいう。本件では、誤振込みされた財物たる30万円の占有がQ支店にあるかが問題となる。
ア 占有の有無の判断は、占有の意思と占有の事実の両側面を総合して判断する。
イ 本件で、確かにX名義の口座に預金が存在して、Xはキャッシュカードを保有して事実上払戻しが可能である。しかし、Xには誤振込み預金に対する正当な受取権限はない。また、Xは元々残高が0円であって30万円の払戻しは不可能だったのであるから、Xが誤振込み預金を占有する事実も意思もない。かかる誤振込み預金は、本来Bに正当な払戻権限があるものであり、誤振込みの状態においてはQが事実上支配し、占有の意思を有していると解するべきである。
よって、DがXに払い戻した行為は、「交付した」といえる。
⑷ また、Qには30万円という財産上の損害が生じている。
⑸ 以上より、Xの上記行為に詐欺罪が成立し、Xはかかる罪責を負う。
2. 小問(2)
XがATMから誤振込金30万円を引き出した行為につき、窃盗罪(235条)が成立しないか。
⑴ Xの口座残高は0円であり、30万円はAが誤振込みをしたものに違いないから、Xが引き出した現金30万円は「他人の財物」にあたる。
⑵ 「窃取した」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有支配下に移転させることをいう。
前述の通り、誤振込み預金に関しての占有は銀行にあると解するべきであり、本件における30万円の占有はQにある。
よって、Xによる30万円の引き出し行為は、他人たるQが占有する財物をQの意思に反して自己の占有支配下に移転する行為といえ、「窃取した」といえる。
⑶ また、主観的構成要件要素として、不可罰的な使用窃盗との区別及び毀棄隠匿罪との区別の見地から、いわゆる不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞う意思および物の経済的用法に従って利用処分する意思)が必要と解する。
本件で、誤振込み預金を引き出す行為は、正当な権限がなければできない行為である。また、XはCに対する借金を返すために引き出しており専ら毀棄隠匿目的ではない。
よって、上記の振る舞う意思および利用処分意思があるといえ、不法領得の意思が認められる。
⑷ 以上より、Xの上記行為に窃盗罪が成立し、Xはかかる罪責を負う。
3. 小問⑶
XがATMを使用してR支店のCの口座に振替送金した行為につき、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)が成立するか。
⑴ ATMは、「人の事務処理に使用する電子計算機」にあたる。
⑵ Xは、実際には自己の預金ではなく誤振込みによるものであるのに、30万円の預金残高があるとみせかけ、ATMを操作してCに同30万円を振替送金しているところ、「不正な指令を与え」て、「財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録」を作ったといえる。
(3) そしてXは、Cに対する30万円の債務を免れ、「財産上不法の利益を得」たといえる。
⑷ 以上より、Xの上記行為に電子計算機使用詐欺罪が成立し、Xはかかる罪責を負う。
以上





