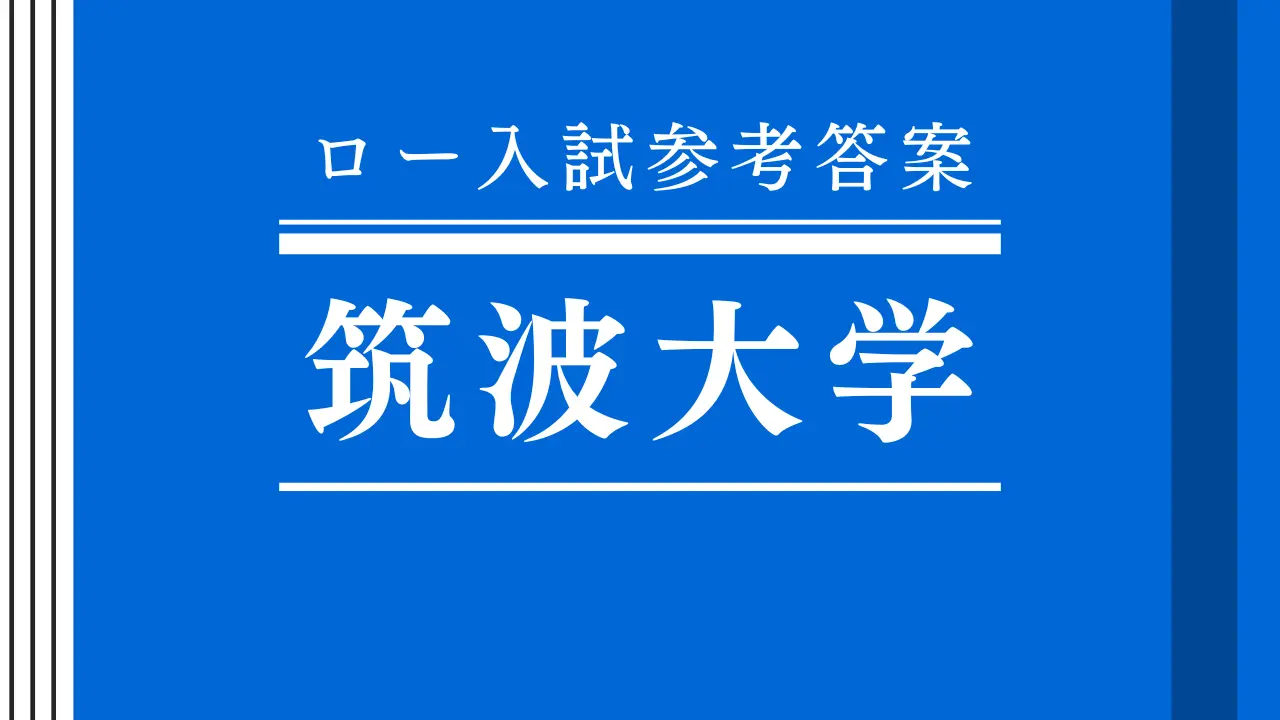
2025年 刑法 筑波大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
筑波大学法科大学院2025年 刑法
1. 甲の罪責
⑴Aを殺して現金を奪おうと考え、びょうを発射させた行為につき、Aに対する強盗殺人罪(236条1項、240条後段)が成立するか。
ア まず、上記行為は現金という財物の奪取に向けられたものであり、かつ、Aの反抗を抑圧する程度の有形力の行使であり「暴行」にあたるため、甲は「強盗」にあたる。
イ もっとも、甲はAを殺して現金を奪おうと考えているところ、殺意のある場合も240条の適用があるかが問題となる。
(ア)そもそも、240条は犯罪学的にみて強盗の機会に犯人が死傷の結果を生じさせる場合が多いことに着目して規定された犯罪類型である。そして、犯人が殺人の故意を有するという事態は、犯罪学的にみてきわめて多い事態であるといえる。そこで、240条は、殺人の故意がある場合も含む規定であると解する。240条が「よって」という文言を用いていないのも、かかる趣旨であると解する。
(イ)したがって、殺意のある場合も240条の適用はあると解する。
ウ 次に、240条の第一次的な保護法益は生命・身体であると解されるため、既遂時期は生命・身体の侵害時点であると解されるところ、本件では、甲は金品の奪取に至っていないものの、甲がAを殺害した時点で既遂となる。
エ よって、甲の上記行為につき、Aに対する強盗殺人罪が成立する。
⑵次に、上記行為につき、Bに対する強盗殺人罪が成立するか。客観的構成要件については、上記の通り充足している。
ア もっとも、甲はAを殺す旨の認識しかなかった。かかる場合にも、Bに対する強盗殺人罪の故意(38条1項本文)が認められるか。
(ア)故意の本質は、規範に直面して反対動機の形成が可能であったにもかかわらず、あえて行為に及んだことに対する強い道義的非難にある。そして、かかる規範は、構成要件の形で一般国民に与えられている。そうだとすれば、認識していた犯罪事実と発生した犯罪事実とが構成要件レベルで一致する場合には、故意が認められると解する。
(イ)本件でみるに、甲は「人」を殺す認識で「人」を殺している以上、、認識していた犯罪事実と発生した犯罪事実とが構成要件レベルで一致しているといえ、Bに対する殺人の故意も認められる。
イ もっとも、甲はA1人を殺すことの認識・認容しかない。にもかかわらず、複数の故意犯が成立しうるか。そもそも、故意を構成要件範囲で抽象化する以上、故意の個数は観念できないはずである。そこで、発生した犯罪事実の数だけ故意犯が成立すると解する。
⑶以上より、A、Bに対する強盗殺人罪が成立し、両者は観念的競合(54条1項前段)となる。
2. 丙の罪責
⑴甲の強盗殺人行為により、死体を物陰に運び、行為に用いられた凶器の指紋を拭き取った行為は、「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅」する行為にあたる。よって、証拠隠滅罪(104条前段)が成立する。
⑵もっとも、丙は甲という「親族」のために証拠隠滅罪を犯している。そのため、刑が任意的に免除されうる(105条)。
3. 乙の罪責
⑴乙がCを殴り倒し、失神させた行為に、事後強盗罪致傷罪(238条、240条前段)が成立するか。
ア 乙が無断で自転車を発車させた時点で、自転車の占有移転が認められるから、乙は「窃盗」にあたる。そして、乙は「財物を得てこれを取り返されることを防」ぐ目的で、Cを殴り倒し、失神させているところ、これは相手方の反抗を抑圧する程度の有形力の行使であり、「暴行」にあたる。
イ また、上記行為によりCは失神しており、「強盗」たる乙が「人を負傷させたとき」(240条前段)にあたる。したがって、事後強盗致傷罪の客観的構成要件を充足する。
ウ もっとも、乙は甲が仲間を連れて自身を捕まえに来たと勘違いしている。そこで、責任故意(38条1項本文)が阻却されないか。
(ア)本件では、客観的には「現在の危難」は生じておらず、緊急避難(37条1項)は成立しない。もっとも、違法性を否定する事実を誤認している場合、規範に直面する余地を欠いていたといえる。したがって、かかる場合には、事実の錯誤として責任故意が阻却されると解する。本件では、乙の認識を基準として、緊急避難(37条1項)の要件を満たしていることを誤認している必要があると解する。
(イ)まず、「現在」とは、法益侵害が現に存在しているか、間近に迫っていることをいう。そして、乙は甲が人殺しも厭わない粗暴な人間であると認識しているところ、その甲が自身を捕まえに来たと誤認している。そのため、法益侵害が間近に迫っているといえる。
(ウ)次に、緊急避難の成立には、避難の意思が必要と解する。そして、避難の意思は、現在の危難を意識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態をいう。本件では、甲の接近、および暴行、殺人等を意識しつつこれを避けようとするために自転車を窃取し、逃走を継続するためにCに対して暴行を行っている。そのため、避難の意思が認められる。
(エ)加えて、「やむを得ずにした」という要件は、当該避難行為をする以外に手段がなかった場合に認められる。本件では、乙が甲の接近により焦っていたこと、その場にいては暴行、殺人の被害者になる可能性があったことから、「やむを得ずにした」といえる。
(オ)最後に、乙は生命を侵害される恐れがあった一方、乙の行為で生じた害は、自転車という財産および、Cの身体に対する侵害に限られる。そのため、「生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった」といえる。
(カ)よって、甲は緊急避難の要件を満たしていたことを誤認していたといえる。したがって、責任故意が阻却される。
エ 以上より、乙は何らの罪責をも負わない。
以上





