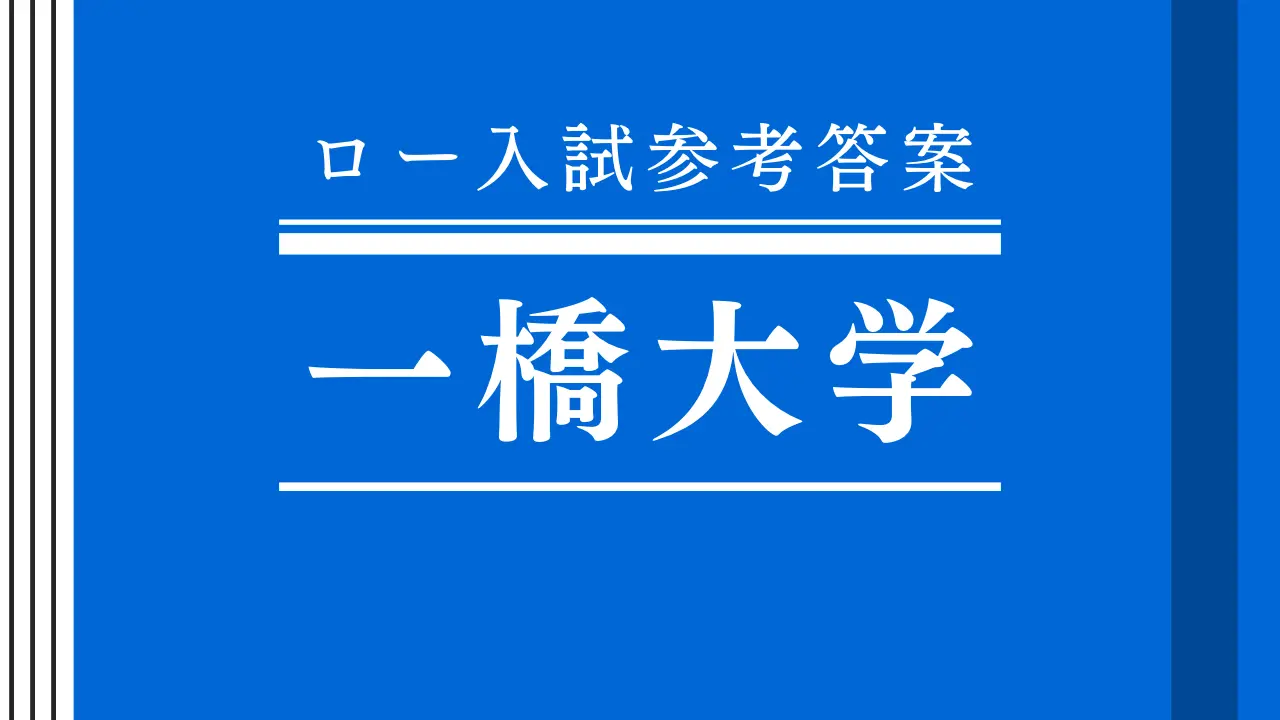
2024年 民法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2024年 民事系/民事訴訟法
第1問(1)
1. BのAに対する、β債権を自働債権、α債権を受働債権とする相殺(505条1項本文)は認められるか。
まず、両債権は履行期にある金銭債権であるから、相殺適状にある。
2. もっとも、「差押え後に取得した債権による相殺」として「差押権者に対抗することができない」(511条1項本文)のではないか。
差押えの効力が発生するのは差押命令送達時(民事執行法145条5項)である。Cがα債権を2023年10月2日に差し押さえており、10月4日に送達しているから、差し押さえの効力は10月4日に発生している。
一方、Bが自働債権を取得したのは同年10月5日である。Bが自働債権を取得したのは差し押さえの効力発生後に取得した後であるから、Bのする相殺は、「差押え後に取得した債権による相殺」に当たる。そのため、原則として「差押権者に対抗することができない」(511条1項本文)。
3. また、差押え後に取得した債権であっても、その債権が「差押え前の原因に基づいて生じたもの」である場合には、相殺することができる(511条2項本文)ものの、でβ債権は、売掛代金債権であり、差押え前にβ債権の発生原因が形式的・客観的に存在していたわけではないから、511条2項に基づいて相殺が認められることもない
4. よって、BのAに対する相殺の主張は認められない。
第1問(2)
1. BのAに対する、β債権を自働債権、α債権を受働債権とする相殺(505条1項本文)は認められるか。
2. Aは2023年10月2日にCに対してα債権を譲渡しており、法4条1項による譲渡の登記を行っているから、民法467条2項の第三者対抗要件は備えている。ここで、Bに対する証明書の交付および通知又は承諾(法同条2項)はなされていないから民法467条1項の債務者対抗要件を備えていない。
そこで、469条にいう「対抗要件」が、債務者対抗要件を言うか問題となるも、第三者を保護すると言う同条の趣旨から、「対抗要件」は、第三者対抗要件をいうと解する。よって、Aは、同条に言う対抗要件を2023年10月2日に具備したといえる。
3. Aは2023年10月2日にCに対してα債権を譲渡しており、Bがβ債権を取得したのは同年10月5日であるから、「対抗要件具備時よりも前に取得した譲渡人に対する債権」(469条1項)とはいえず、相殺できないのが原則である。
また、「前の原因に基づいて生じた債権」(同条2項1号)とは言えない。
4. 以上より、BのAに対する相殺の主張は認められない。
第2問(1)
1. DのBに対する使用者責任(715条1項)に基づく損害賠償請求権は認められるか。
2. ⑴AはB社の従業員であるから、「他人を使用する者」にあたる。
⑵Aは、私用のために運転しているときに本件事故を起こしたが、「事業の執行について」といえるか。
相手方の信頼保護の観点から、行為の外形から判断して、職務の範囲内の行為に属するものと認められる場合をも包含すると解すべきである。
AはBの社名とロゴが入ったBが所有する車を営業のために用いることは日ごろから認められていたが、私用で使うことは禁止されていた。そこで事業の執行についてとはいえないとも思える。もっとも、車には社名とロゴが入っていたから、外見からすると職務の範囲内であると判断される。
よって、「事業の執行について」といえる。
⑶そして、AはCに100万円の「損害」を生じさせている。
⑷したがって、Bは使用者責任を負う。
3. ⑴ここで、Bとしては内縁の夫Cの過失を考慮し、過失相殺(722条2項)をすべきと主張する。そこで、過失相殺において内縁の夫の過失を考慮できるのか問題となる。
過失相殺制度の趣旨は、損害の公平な分担にある。被害者側に過失があるとき、被害者が経済的にも一体をなす者に損害賠償請求をすることはまずない。そうすると、共同不法行為(719条1項)として、加害者に、被害者側の過失による損害の賠償債務を連帯して負わせるよりも、被害者にその不利益を負わせるほうが公平といえる。また、実質的に分割責任とすることで、求償関係を一回的に解決できる点で合理的である。そこで、被害者と身分上ないし生活関係上一体となすと認められる関係にある者の過失を考慮できると解する。
⑵内縁の夫婦は、婚姻の届出はしていないが、男女が協力して夫婦としての共同生活を営んでいるものであり、身分上ないし生活関係上一体をなす関係にあるとみることができる。
したがって、内縁の夫Cの過失を考慮し、過失相殺をすることができる。
4. 以上より、本件事故のAとCの過失割合は8:2であるので、100万円のうちBは80万円の部分につき、損害賠償の責任を負う。
第2問(2)
1. AはBに対して、Dに支払った賠償金の全部または一部の支払を求めることができるか。
2. 被害者に賠償をした被用者から使用者に対する求償権が認められるか問題となる。
使用者責任の根拠は、報償責任と危険責任にあるから、使用者は、被用者との関係においても、損害を負担すべきである。また、使用者からの求償(715条3項)が、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されることとの均衡から、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度について、逆求償も認められる。
3. 以上より、AのBに対する求償は、信義則相当と認められる限度において認められる。
以上





