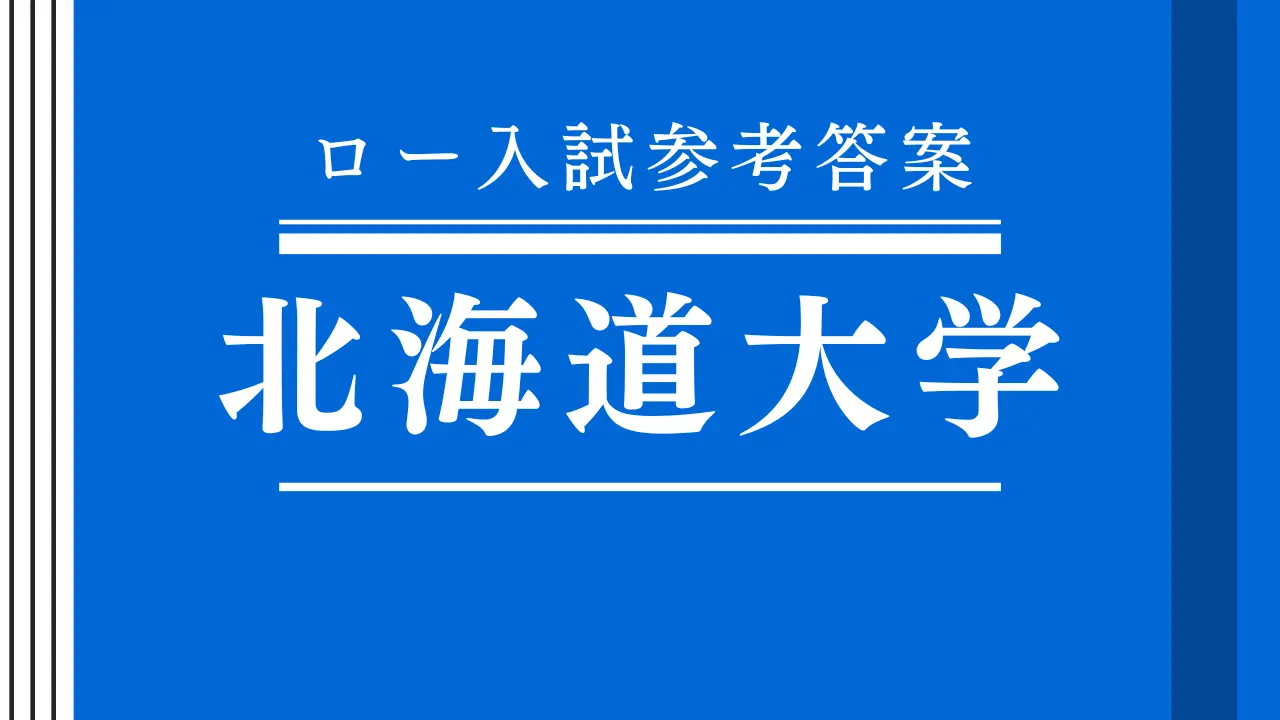
2023年 刑法 北海道大学法科大学院【ロー入試参考答案】
2/29/2024
The Law School Times【ロー入試参考答案】
北海道大学法科大学院2023年 刑法
第1問
1. Yは、とっさに短刀を取り出して鞘から抜き、死んでもいいと思いながらAの胸部に強く突き刺しており、これによりAは死亡した。このYの行為につき殺人罪(199条)は成立するか。
⑴ 本行為は、「人を殺した」ものにあたる。また、Yは、死んでもいいと思っていることから、殺人罪の故意も認められる。したがって、殺人罪の構成要件を充足する。
⑵ もっとも、正当防衛(36条1項)が成立し、違法性が阻却されないか。
ア 「急迫」とは法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に推し迫っていることをいうから、侵害の急迫性が認められるためには、法益侵害の危険が具体的に切迫していることが必要である。
本件において、Aは、運転してきた自動車をJ組事務所の前に止めるやいなや、自動車を降りてYのところに向かってきて、「お前、Xのところのガキか」と言って、Yの胸倉をつかんで投げ飛ばした。さらにAは転倒したYの頭部を執拗に足げりにしていた。このようなAの行為から、Yの生命身体に対する「急迫不正の侵害」が存在していたものと認められる。
イ Yは、Aの上記行為に身の危険を感じて、自分の生命身体を守るために本行為に及んだものであり、本行為は「防衛のために」行ったものといえる。
ウ 「やむを得ずにした行為」とは、防衛手段として必要最小限度のものであることをいい、防衛行為と侵害行為の危険性や代替手段の有無から総合的に判断される。
本行為は、短刀(刃体の長さ15cm)を用いたものであり、Aを死亡させる危険性の高い行為である。Yは、このような本行為を小刀を示すなどの警告行為を行うことなく行っている。そうすると、Aによる侵害行為が比較的強度の暴行であることを考慮しても、Aの同行為は素手によるものであることから、本行為は防衛手段として必要最小限度のものであるということができない。
エ したがって、本行為に正当防衛は成立せず、違法性は阻却されない。
⑶ Yは、殺意を有している以上、過剰性の認識も認められるため、責任故意が阻却されることもない。
⑷ よって、Yの行為につき殺人罪が成立する。これは、以下の通りXと共同正犯(60条)となる。もっとも、過剰防衛(36条2項)にはあたることから、任意的に刑が減免される。
2. 上記1の行為につきXに殺人罪の共同正犯(60条、199条)が成立するか。
⑴ 前述のように上記1の行為は「人を殺した」ものにあたるところ、XとYは「共同して犯罪を実行した」といえるか。
ア 共同正犯の本質は、自己の犯罪として法益侵害を共同惹起することにある。そこで、「共同して犯罪を実行した」というためには、①共謀、②正犯意思、③①に基づく実行が必要であると解する。
Xは、J組の子分であるYに対し、Aとの口論の経過を説明した上で、「お前が事務所の前で待っとけ。Aにやられたら、これで刺せ。殺してもいい」と言って、Yに上記短刀を持たせたものである。そうすると、XとYは、殺人罪の実行について合意したものといえ、殺人罪の共謀が認められる。
Xは、Aが自分のところに殴り込みに来ることを予想し、その場合には、徹底的に痛い目に合わせてやると考え、Yに対して上記のような殺害指示を行ったものであるから、正犯意思、すなわち、自己の犯罪として実行する意思も認められる。
上記1の行為は、上記共謀の内容通りのものであるため、上記共謀に基づくものといえる。
⑵ もっとも、Xについても、Yと同様、過剰防衛が成立して任意的に刑が減免されないか。
ア 共同正犯は、狭義の共犯とは異なるため、違法性・責任は連帯しないと解する。もっとも、客観的事由については共通するため、主観的事由についてのみ個別の検討を要するものと解される。
イ Xは、Aが自分のところに殴り込みに来るかもしれないと予想していることから、Aによる侵害に「急迫」性が認められないのではないか。
(ア)36条の趣旨は、緊急状況のもとで国家による救済が期待できない場合に、私人による防衛行為を例外的に許容することにある。そこで、侵害の予期の程度・侵害の回避可能性・侵害に臨んだ状況など、先行事情を含む行為全般の事情を総合して、防衛行為が上記趣旨に照らし許容されるものといえないときには、侵害の急迫性が認められないと解する。
(イ)Xは、上記の通りAによる侵害を予想した上で、Aを積極的に加害する意思をもってYに上記殺害指示を行っている。そうすると、Xについては、上記1の行為は、法36条の趣旨に照らし許容されるものといえないときには、侵害の急迫性が認められない。
ウ したがって、Xについては、過剰防衛すら成立せず、刑の減免は認められない。
⑶ よって、Xには、殺人罪の共同正犯が成立する。
第2問
1. Xが自己の所有する物置小屋(幅1.5m・高さ1.5m・奥行1mの木製)に火を放った行為につき自己所有に係る非現住建造物放火罪(109条2項)が成立しないか。
⑴ Xの行為は「放火」(同条1項参照)にあたる。これにより物置小屋は全焼しており、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物を…焼損した」といえる。また、物置小屋の中にあった灯油に引火して物置小屋は激しく燃え上がったこと、Xは消火器を使おうとしたが、使用方法を確認していなかったために作動させることができなかったこと、折悪しく突風が噴き出したために燃え上がった炎から大量の火の粉が付近の住宅に降りかかったことから、付近の住宅に延焼させる可能性があった。しかし、迅速な消化活動が行われ、物置小屋が全焼下に留まり、大事には至っていないことから、「公共の危険」が生じたとは言えないのではないか。
この点につき、放火罪の公共危険罪たる性格を考慮に入れれば、公共の危険の発生とは、必ずしも108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険も含まれる。
本件では、住民が避難する騒動となり、住民の生命、身体に対する危険があり、不特定多数人の生命・身体に危険が生じたといえる。よって、「公共の危険」が生じたものと認められる。
⑵ もっとも、Xは、万一に備えて消火器を用意した上で、当日は小雨が降っており、風も吹いていなかったことから、住宅等に燃え移るおそれはないと確信して本行為に及んだものである。そうすると、Xには、公共の危険の認識がないため、本罪の故意が認められないのではないか。公共の危険の認識の要否が問題となる。
この点、公共の危険は構成要件要素ではなく、処罰条件に過ぎないことから、公共の危険の認識は不要であると解される。
したがって、Xに本罪の故意が認められる。
2. よって、Xには、自己所有に係る非現住建造物放火罪が成立する。
以上





