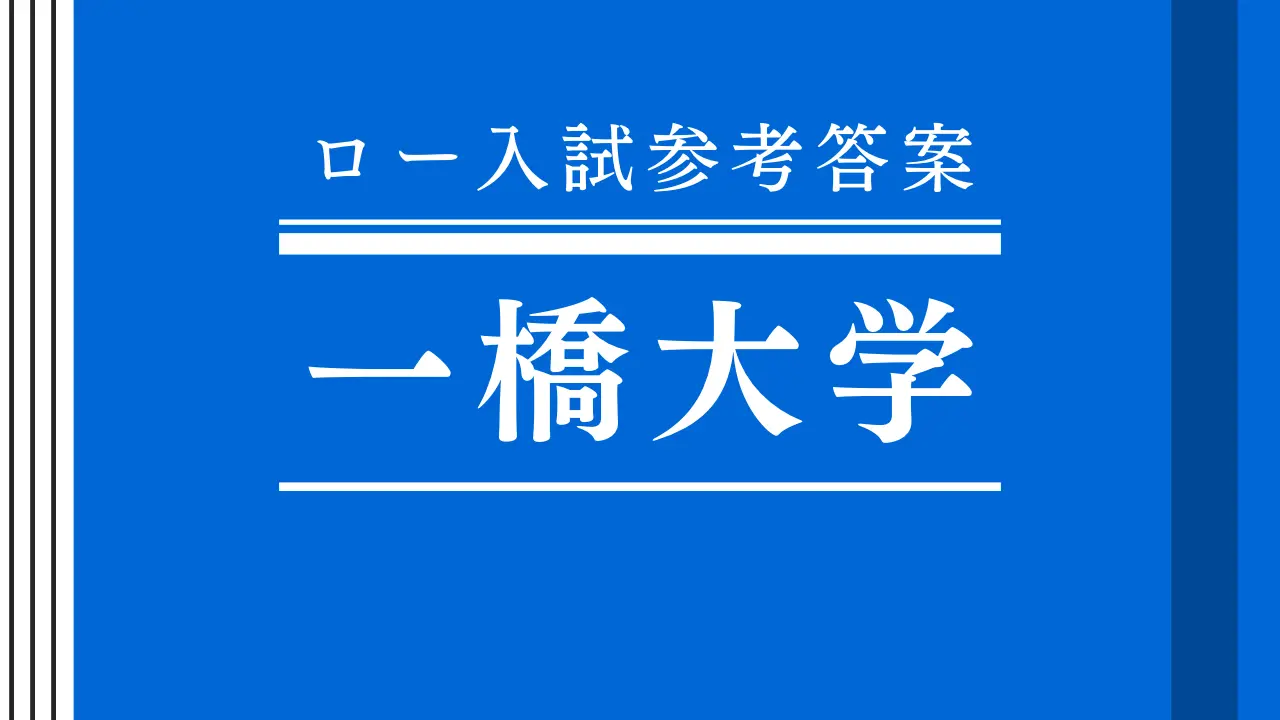
2023年 民事系/民法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2023年 民事系/民法
民法 第1問
第1(問(1))
1. Bに対して
⑴ まず、AはBに対し、①の金銭債権を有するか。
ア ①の債権は、民法(以下、略)121条の2第1項に基づく原状回復請求権であると考えられる。これをみるに、AとBが締結した金銭消費貸借契約は、Bが未成年であることを理由に取り消されている(5条1項、2項)から、その効力は遡及的に無効となり(121条)、「無効な行為」となる。そして、AはBに対し、かかる金銭消費貸借契約に基づき500万円を貸し付けているから、Bは「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」にあたる。したがって、AはBに対し、121条の2第1項に基づく原状回復請求として金銭の返還請求ができる。
イ もっとも、Bは未成年であり「行為の時に制限行為能力者であった者」(121条の2第3項)にあたる。したがって、Bは「現に利益を受けている限度」においてのみ返還義務を負うことになる。そのため、Bはすでに浪費してしまった50万円については返還義務を負うことはなく、預金口座に預金してある残りの450万円についてのみ返還義務を負う。
ウ 以上より、AはBに対し450万円の限度で①の債権を有する。
⑵ 次に、AはBに対して、➁の金銭債権を有するか。
ア ➁の債権は利息契約に基づく利息請求権である。そして、同債権の成立には、元本債権の成立が必要となるところ、本件では、元本契約である500万円の金銭消費貸借契約は、既に取り消され遡及的に無効となっている。したがって、AはBに対し、利息の支払いを請求することはできない。
イ 以上より、AはBに対し➁の債権を有しない。
2. Cに対して
⑴ AはCに対して、①の金銭債権を有するか。
ア この点、まず、Cは、AとAB間の500万円の消費貸借契約について保証(446条1項、2項)する合意をしているが、AB間の消費貸借契約は取り消されているから、保証債務の附従性からCの保証債務も消滅し、AはCに対して①の債権を有しないのが原則である。
イ もっとも、AC間の保証契約において、主債務が取り消された場合の原状回復債務をも保証することがその内容として定められていた場合には、原状回復債務も保証債務に含まれることとなる。そのため、かかる場合には、AはCに対し、Bに対してと同様に45万円の限度で金銭債権を有することになる。
ウ また、仮に、Cが、Bが未成年者であることを知って保証契約を締結した場合には、449条が適用され、CはAと独立の債務を負担したものと推定されるため、かかる推定が覆らない場合には、AはCに対し、500万円全額について、①の金銭債権を有することになる。
(2)次に、AはCに対して➁の金銭債権を有するか。
ア まず、Cが、Bが未成年者であることを知らなかった場合には、保証債務は附従性で消滅することになり、CはAに対し➁の金銭債務を負わない。したがって、かかる場合には、AはCに対し➁の金銭債権を有しない。
イ しかし、Cが、Bが未成年者であることを知っていた場合には、449条の適用によって、利息契約を含む同一の内容の独立の債務を負担したことが推定され、かかる推定が覆らない限り、CはAに対し利息契約に基づく250万円の支払い債務を負うことになる。したがって、かかる場合には、AはCに対して➁の債権を有することになる。
第2(問(2))
1. Bに対して
⑴ まず、AはBに対して①の金銭債権を有するか。
ア ①の債権は、121条の2第1項に基づく原状回復請求権であると考えられるが、BはAと締結した金銭消費貸借契約は、Aによる詐欺を理由に取り消され(96条1項)、遡及的に無効となり(121条)、「無効な行為」となる。そして、AはBに対し、かかる金銭消費貸借契約に基づき500万円を貸し付けているから、Bは「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者」にあたる。そのため、BはAに対し、原状回復義務として500万円の返還義務を負う。なお、詐欺による取消の場合には、121条の2第3項の適用はなく、BはAに対し500万円全額の支払い義務を負う。
したがって、AはBに対し①の金銭債権を有する。
⑵ 次に、AはBに対して➁の金銭債権を有するか。
ア これをみるに、Bは金銭消費貸借契約を詐欺により取り消しており、それによって利息契約も無効になるため、AはBに対して➁の債権を有しない。
2. Cに対して
⑴ Aは、Cに対して、①の金銭債権を有するか。
ア CはAとAB間の金銭消費貸借契約を保証する合意をしているところ、かかる保証契約の内容として取り消された場合の原状回復債務までを保証することが定められていた場合には、AはCに①の債権を有することになる。そうでない場合には原則通り、保証債務は主債務が取り消されたことによって附従性により消滅し、AはCに対し①の債権を有しないこととなる。
イ なお、CはAB間の消費貸借契約がAの詐欺によるものであることを知っていたから449条が類推適用されないかが問題となるも後述の通りこれは認められない。
⑵ AはCに対して➁の金銭債権を有するか。
ア まず、主債務の消滅によって、保証債務も消滅するから、利息支払債務についても消滅することになるのが原則だから、原則として、AはCに対し➁に債権を有しない。
イ そして、CはAB間の消費貸借契約がAの詐欺によるものであることを知っていたから449条が類推適用され、Cは独立の債務として利息の支払義務を負わないかが問題となる。この点、449条の趣旨は、主債務者が制限行為能力者であることを知りながらあえて契約した保証人の犠牲のもと債権者の保護を図る点にあるところ、詐欺の場合には、自ら詐欺を行った債権者の保護を図る必要はないため、449条の類推適用は認められない。
したがって、本件でも449条は類推適用されず、Cは独立の債務として利息の支払義務を負うことはない。
民法 第2問
第1(問(1))
1. CのBに対する本問請求は、売買契約(555条)に基づく甲土地の引渡し及び所有権移転登記手続請求である。かかる請求は認められるか。
⑴ これをみるに、CはAと甲土地を1500万円で購入する合意をし、代金1500万円を支払った。なお、甲土地は、AではなくBの所有の土地であるが、売買契約は有効でありCはBから甲土地の権利を取得しAに移転する義務を負う(561条)。
そして、Aは「死亡」(882条)し、唯一の相続人である母のBがAを相続(896条本文)した。そのため、Bは、他人物売り主の地位すなわち相続することになるため、Cの上記甲土地の引渡し及び所有権移転登記手続債務をも相続することになる。
⑵ もっとも、これに対し、Bから、BはAC間の他人物売買契約の目的物の所有者であり、かかる地位に基づいて他人物売買による所有権の移転を拒むことができると反論することが考えられる。
この点、相続という偶然の事情によって相手方が利する結果となるのは妥当でないから、相続によって他人物売主の地位と所有者の地位は融合せず併存すると考える。そして、他人物売買の目的物の所有者は、売主からの所有権移転の要請を拒絶することができるところ、所有者が売主の地位を相続したとしても所有者には何ら帰責性がないから、これを理由に所有権移転を強制されることはない。したがって、所有者が売り主の地位を相続した場合でも所有権の移転を拒むことができる。
よって、本件では、甲土地の所有者であるBは、売り主であるAの死亡によってかかる地位を相続したとしても、所有権の移転を強制されることはなく、所有者の地位に基づいて所有権の移転を拒むことができる。
⑶ 以上より、Bの反論が認められるから、Cの上記請求は認められない。
第2(問(2))
1. Cの甲土地の引渡し及び所有権移転登記手続請求が認められない場合、CはBに対して、履行不能に基づく損害賠償請求(415条1項)ができないか。
本件では、Bは、上記の通りAを相続しているため、BはAC間売買の売り主としての地位も相続している。そして、甲土地の売買契約は、Bが所有権の移転を所有者の地位に基づいて拒絶したことにより、Bの甲土地の引渡し及び所有権移転登記手続「債務の履行が不能である」といえる。そして、かかる履行不能「によって」、かかる債務の履行がされないことによる「損害」が生じている。また、Bの免責を相当とすべき事情もないから、「債務者」B「の責めに帰することができない事由」(同項但書)もない。したがって、CはBに対し、履行不能に基づく損害賠償請求ができる。
以上





