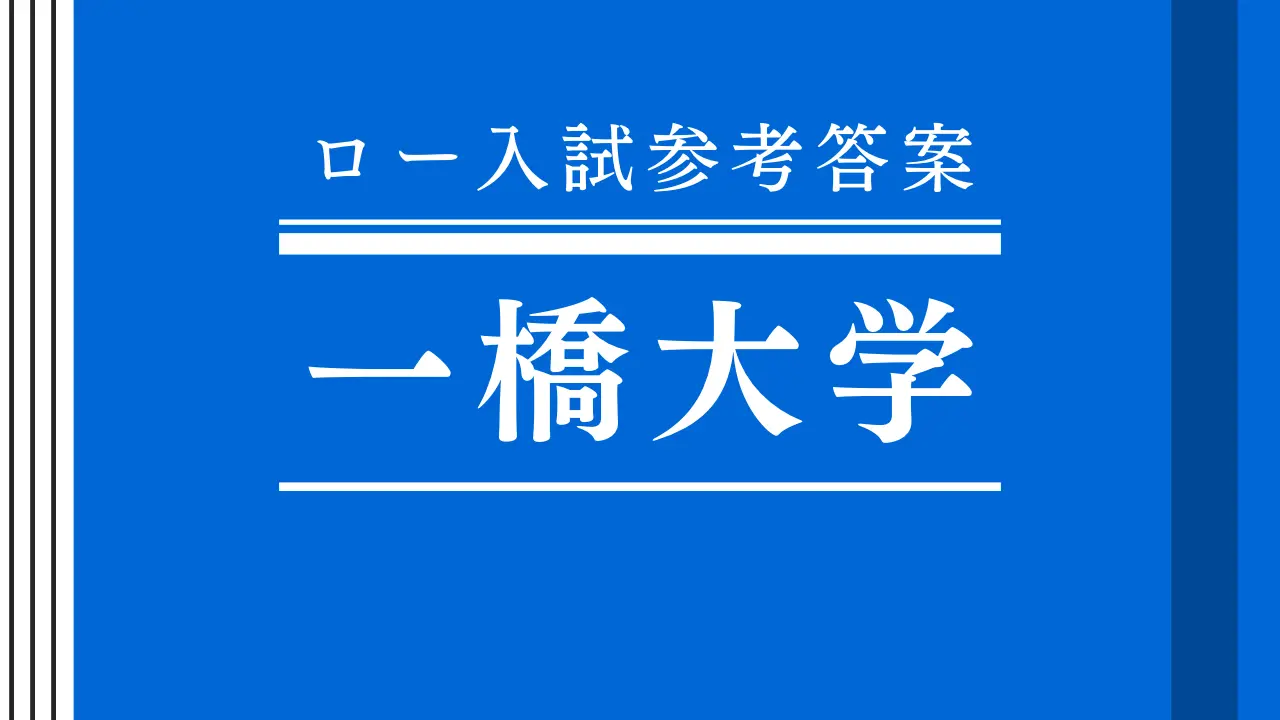
2022年 刑事系/刑法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2022年 刑事法/刑法
第1問
1. BがCを刃物で脅し、AがA車でCをA所有の倉庫に連れて行った行為につき、恐喝未遂罪の共同正犯(刑法(以下略)60条、250条・249条1項)が成立するか。
⑴ まず、Bは刃渡り30cmもの大型の包丁をCに突きつけて「おとなしくしろ」と語気鋭く叫び、CをA所有の倉庫に移動させている。計画では、CをA所有の倉庫に連れて行った後、倉庫内で改めてBがCに包丁を付きつけて金を出すように迫り、Cに金を渡させるというものであるところ、上記時点で恐喝罪(刑法(以下略)249条1項)の「実行に着手」(43条1項本文)したといえるか。
ア 未遂犯の処罰根拠は、構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起させた点にある。そこで、実行の着手時期は、構成要件的結果発生の現実的危険が生じた時点で認められると解する。
イ 本件では、AらがCをA所有の倉庫に連れて行った上で(第1行為)、改めてBがCを脅して金を渡させる(第2行為)という計画であるところ、Cが暴れたり逃走したりすることが想定されるため、第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠である。また、Cを倉庫に連れて行く方法は車であるから密室である上、倉庫はA所有で他人が入り込むなどのおそれも少ないため、第1行為に成功すればそれ以後の計画を遂行する上で障害となる特段の事情はない。そして、BがはじめにCを脅した場所から倉庫まではわずか5kmの距離であり、車で移動することからすると移動にかかる所要時間も20分程度と考えられるため、第1行為と第2行為の時間的・場所的近接性もある。
これらの事情に照らせば、第1行為の時点でCが現金を交付するという構成要件的結果発生の現実的危険が生じたといえ、恐喝罪の「実行に着手」したといえる。
⑵ もっとも、Xは、自ら上記行為をしたわけではないところ、共謀共同正犯として罪責を負うか。
ア 共同正犯の処罰根拠は、結果に対して物理的・心理的因果性を及ぼした点にある。かかる因果性は実行行為以外の方法によっても認められうる。そこで、共謀共同正犯も共同正犯たりうる。具体的には、共謀、共謀にも基づく実行行為、正犯意思があれば、共同正犯にあたると解する。
イ 本件では、A・B・X間で、Cから金を巻き上げることにつき共謀している。また、前述の計画に基づきBがCを脅し、A車でCを倉庫へ連れて行っている。そして、Xは助手席に乗ってA・Bと共に何ら異議を述べずに移動しており、正犯意思もあるといえる。
よって、共謀共同正犯が成立する。
⑶ 以上より、第1行為時点で、Xに恐喝未遂罪の共同正犯が成立する。
2. その後、Aは単独でCに対してドライブ代をよこせ、出さないとどうなるかわかっているなどと更に申し向けて、1万円の交付を受けているが、この時点でXに恐喝罪の共同正犯が成立しないか。
⑴ まず、前述の計画ではBが脅して現金の交付を受けるものであったところ、共謀の射程外として、新たな共謀がない以上、Xに上記罪は成立しないのではないか。
前述した共同正犯の処罰根拠から、共謀の射程は、共謀の因果性が実行行為に及んでいる場合に認められる。
本件計画では倉庫にCを連れてきた後はBが更に脅して交付を受けるというものであった。しかし、Aは自ら計画を提案するなど首謀者的地位にあり、計画とは違って、BではなくAがCを脅すということも十分にありうる。また、Cという同一の被害者に対する恐喝という点では計画と異ならない。さらに、Cから金をまきあげるという犯意も継続しており、当初の共謀による行為と時間的場所的近接性も認められる。よって、共謀の因果性はAの実行行為に及んでいるといえる。したがって、共謀の射程内である。
⑵ もっとも、Xは、A・Bに対して「車の中で・・・目を覚ませ」などと説得し、計画の中止を提言しているところ、以後のAの行為につき罪責を負わないのではないか。
ア 前述の共同正犯の処罰根拠に照らし、結果に対する物理的・心理的因果性が遮断されれば共犯関係の解消が認められると解する。
イ 本件で、確かに、Xは、A・Bに対して上記の様に提言し、BはXに同調し、Aもまた計画の中止に同調している。しかし、Aはしぶしぶ同意したにすぎず、Aは首謀者であり以後もCに対して恐喝行為をする可能性があるにも関わらず、Aに対して以後恐喝行為をしないように注意を促したり、畏怖しているCを自宅に送迎したりすること無く、Aに対してCを自宅に送迎するように言い残しただけで立ち去っている。そのため、未だ因果性が遮断されたとはいえない。
よって、共犯関係の解消は認められない。
⑶ 以上より、恐喝罪の共同正犯が成立する。
3. また、AがCをA車に乗せて倉庫に連れて行った行為は、一定の場所からの脱出を不可能ないし著しく困難にして人の場所的移動の自由を奪う行為としての「監禁」に該当するため、かかる行為につき監禁罪(220条)が成立し、前述と同様に、Xに同罪の共同正犯(60条)が成立する。
4. 以上より、Xに①恐喝罪の共同正犯、②監禁罪の共同正犯がそれぞれ成立し、併合罪(45条)となる。
第2問
Yの罪責
Yが、2月3日以前にAのバイクにまたがった姿を動画に収めたハードディスクに穴を開けてデータを破損させた行為につき、何らかの罪責を負わないか
1. まず、物の効用を害したとして、器物損壊罪(刑法(以下略)261条)の成否が問題となるが、成立しない。なぜなら、当該物は「他人の物」(261条)とは言えず、また、差押えを受けていないため、「差押えを受け」た「自己の物」(262条)にも該当しないからである。
2. 次に、証拠隠滅罪(104条)の成否が問題となるも、成立しない。なぜなら同罪は、期待可能性の欠如を考慮して、対象となる証拠物を「他人の刑事事件に関する」物に限定しているところ、Yは「他人」に当たらないからである。
3. では、公務執行妨害罪(95条1項)が成立しないか。上記行為が「暴行」にあたるかが問題となる。
⑴ 「暴行」とは、直接・間接を問わず公務員に向けられた不法な有形力の行使をいう。本件では、家宅捜索に立ち会っていたYが、自己所有のハードディスクにドリルで穴を開けて押し入れの奥に投げ込んだに過ぎず、公務員たる警察官の面前で行われた有形力の行使とはいえない。よって、直接的にも、間接的にも、公務員に対して不法な有形力が行使されたとは言えない。
⑵ したがって、上記行為は「暴行」には当たらず、同罪は成立しない。
4. また、威力業務妨害罪(234条)が成立しないか。「業務」に公務が含まれるかが問題となる。
⑴ 強制力を行使する権力的公務は自力排除力を有しているため、あえて同罪で保護する必要はない。そこで、「業務」には、かかる権力的公務は含まれず、日権力的公務のみが含まれると解する。
⑵ 本件で、警察官の捜索という公務は強制力を行使する権力的公務であり、「業務」に含まれない。
よって、同罪は成立しない。
5. 以上より、Yは何ら罪責を負わない。
Xの罪責
1.
⑴ 前提として、Bが、取調べの際にYから2月3日に沖縄の観光地で撮影した写真を見せてもらったことがある旨の供述をした行為につき、犯人隠避罪(103条)が成立する。なぜなら、かかる行為は、Xから逮捕・勾留されているYのアリバイを工作することで保釈させることを狙いとしてされた指示を受けて行ったものであり、場所を提供して匿うという「蔵匿」以外の方法により、官憲による発見・身柄の拘束を免れさせる一切の行為といえ「隠避」にあたるからである。
⑵ また、BはYの友人で「親族」(105条)ではないから、刑が任意的に免除されることもない。
2. また、参考人たるBの虚偽の供述につき、Bに証拠偽造罪(104条)が成立するか。
⑴ 虚偽供述は偽証罪(169条)に限って処罰するのが刑法典の建前である以上、虚偽供述は原則として「偽造」に当たらないと解する。ただし、単に虚偽供述をしたにとどまらず、捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作・具体化させ、それを供述調書の形式にする行為は、「偽造」にあたると解する。かかる場合には前述の建前が妥当しないからである。
⑵ 本件では、虚偽供述をもとにした供述録取書が取調官によって作成され、Bが署名・押印をしているが、取調官は虚偽の供述であることは認識しておらず、Bも取調官の指示に従って署名・押印をしたに過ぎないと思われるから、取調官と相談しながら虚偽の供述内容を創作・具体化したとまでは言えない。
⑶ よって、「偽造」に当たらず、同罪は成立しない。
3. では、XがBに対して上記の指示をし、うその供述を行わせた行為につき、犯人隠避罪の教唆(61条1項・103条)が成立しないか。
⑴ 「教唆」とは、未だ犯罪の実行を決意していない他人をそそのかして当該他人に犯意を誘発させることをいうところ、Xは、前述の通りBに対して上記の指示をし、うその供述を行わせている。BはXから指示を受けるまで参考人として写真を見せてもらったことがある旨の事実と異なる供述をすることを企図していなかったため、Xの上記指示は未だ犯罪の実行を決意していない他人たるBをそそのかして犯意を誘発させたとして「教唆」にあたる。
よって、犯人隠避罪の教唆(61条1項・103条)が成立する。
なお、BはXの舎弟であり、Bの犯人隠避はXの指示によるものであるが、その他にXの正犯性を基礎付ける事情はないため、共同正犯(60条)には当たらない。
⑵ もっとも、XはYの弟であり「親族」にあたるところ、105条により刑が任意的に免除されないか。
ア 105条は、親族間の情愛ゆえに103条の罪を犯した場合に期待可能性が低いことを考慮した規定である。しかし、他人を教唆する行為は他人を巻き込む点で期待可能性が低いとはいえない。よって、105条の適用はないと解する。
イ 本件では、Xは他人であるBに対して教唆をしているため、105条が適用されることはない。
ウ よって、刑が免除されることはない。
4. 以上より、Xの上記行為に犯人隠避罪の教唆が成立し、Xはかかる罪責を負う。
以上





