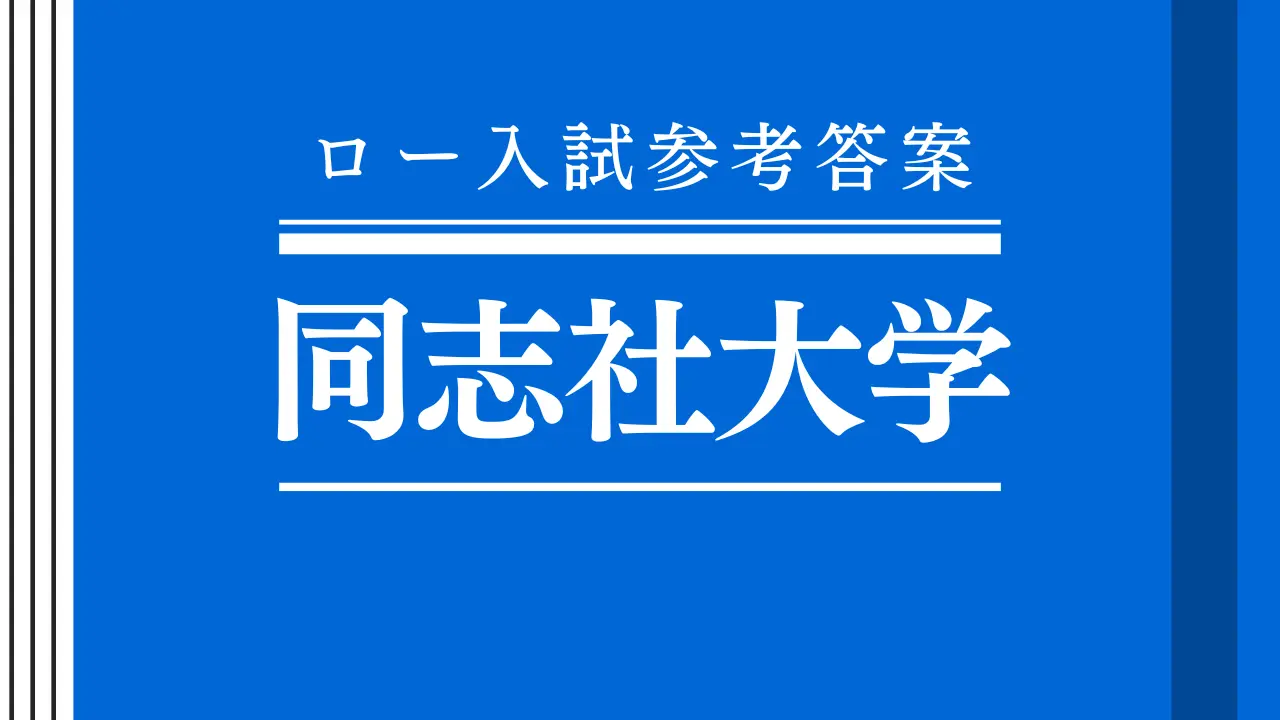
2025年 刑法 同志社大学法科大学院【ロー入試参考答案】
3/23/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
同志社大学法科大学院2025年 刑法
1. Xの罪責を検討する前提として先行してMの罪責を検討する。
⑴Mが本件ハンドバックを持ち帰った行為につき、窃盗罪(235条)が成立するか。
ア まず「他人の財物」とは、他人が占有する他人の所有物をいうところ、本件ハンドバックがこれに当たるか、占有の有無が問題となる。
イ この点、占有とは、財物に対する事実的支配をいい、占有の事実と占有の意思を総合して判断する。
ウ まず、本件ハンドバックはBが置き忘れたものであるが、Bが占有を続けている事情はないからBに占有は認められない。
次に、上記行為はAが歩き出してべンチから約30メートル離れたときに行われたものであるから、被害品である本件ハンドバックとAとの間には、時間的場所的近接性がある。加えて、被害品はハンドバックであり、その大きさ、軽さから、移動は容易である。そうするとAの占有の事実は一定程度認められる。一方で本件ハンドバックはBが置き忘れたもので、Aはその存在には気づいていなかったのであるから、占有の意思は全くなかったと言える。そして、このような場合には、Aの本件ハンドバックに対する占有を保護すべき要請は強くなく、Aの占有は認められない。
最後に公園は公衆が立入ることができる場所であるから、公園の管理者の占有も及んでいない。
よって本件ハンドバックに占有者は存在せず、これは「他人の財物」にはあたらない。したがって、上記行為は窃盗罪の客観的構成要件を充足せず、同罪は成立し得ない。
⑵では、Mの上記行為に占有離脱物横領罪(254条)が成立するか。
ア 本件ハンドバックはBの物であるが、Bの意思によらずにその占有を離れ、未だ何人の占有にも属していない物で、他人の委託に基づかずにMが占有するに至った物であるから、「占有を離れた他人の物」といえる。
「横領」とは、所有者でなければできないような処分をする意思、すなわち不法領得の意思を発現する行為をいう。
Mは、本件ハンドバックを持ち帰ることによって、本件ハンドバックの所有者でなければできない処分をしているから「横領した」といえる。
イ 次に、本件行為時において、Mに同罪の故意が認められるかを検討する。
(ア)XおよびMは上記行為時に、本件ハンドバックがAがベンチに座る前にBが置き忘れたものであったことを知らなかった。もっとも、XおよびMは上記の占有に関する事情のうち、それ以外の事情は全て認識していた。そうすると、XおよびMの主観において、Aには本件ハンドバックへの占有の事実が認められ、占有の意思を否定する事情もないため、本件ハンドバックはAの占有物として、「他人の財物」にあたる。そして上記行為はこれを「窃取」するものであるから、Mには上記行為について窃盗罪の故意が認められる。
(イ)ここで、Mは窃盗罪の故意で占有離脱物横領罪に該当する行為をしているが、この場合に占有離脱物横領罪についての故意が認められるか。
故意責任の本質は犯罪事実の認識によって規範に直面し、反対動機が形成できるのに、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難にある。そして、規範は構成要件として与えられているのであるから、構成要件に該当する事実の認識を欠く場合、反対動機を形成できず、原則として故意は阻却される。もっとも、主観と客観とで、構成要件に実質的な重なり合いが認められるのであれば、その限度で反対動機を形成できるから、かかる限度で故意が認められると解する。構成要件は一定の法益を侵害する一定の行為の類型なので、保護法益の共通性と行為態様の共通性が重なり合いの判断基準となる。
窃盗罪の保護法益は占有であり、占有離脱物横領罪は所有権であるが、占有が侵害されると背後にある本権も侵害される関係にあるから、両罪は保護法益の共通性が認められる。また、行為態様も同質であるから、軽い占有離脱物横領罪の範囲で構成要件的な重なり合いが認められ、同罪の故意が認められる。
(ウ)また、Mには不法領得の意思も認められる。
ウ もっとも、Mは「十四歳に満たない者」(41条)であり、刑事責任を負わないから、Mの上記の行為には犯罪は成立し得ない。よって、上記行為に犯罪は成立しない。
2. 次に、X が、Mに指示して、本件ハンドバックを取ってこさせた行為にいかなる犯罪が成立するか。
⑴まず、XがMを利用したことによる間接正犯が成立するか問題となるも、XがMに対して「ベンチに座っている女の人が立ち去ったら、ベンチの下に置いてあるバックを取っておいで」という指示に対して「嫌だ」と言い、ご褒美を買ってもらえることから、しぶしぶ了承することになっており自分で犯罪の実行を判断していること、Mは13歳で是非弁別能力があること、Xの指示の態様は優しくMの意思を制圧する程度のものではないことの各点を考慮すると、XがMを一方的に利用支配したとはいえない。よって、間接正犯は成立しない。
⑵次にXとMの間に占有離脱物横領罪の共同正犯(60条)が成立するか。Xは何ら実行行為を行っていないため、「共同して犯罪を実行した」といえるか、共謀共同正犯の成否が問題となる。
ア 文理上、「2人以上共同して」その中の誰かが「犯罪を実行した」ときは、共犯者は「全て正犯とする」と読める。また、60条が一部実行全部責任を負わせる根拠は、相互利用補充関係にある共犯者が、一体となって結果に対して因果性を及ぼし特定の犯罪を実現する点にあり、この理は共謀共同正犯の場合にも妥当する。そこで、①共謀と、②共謀に基づく実行行為が認められれば、「共同して犯罪を実行した」として共謀共同正犯が成立すると考える。
イ Xの指示に対し、Mは「わかった」と返事をしているので、意思連絡が認められる。また、Xはハンドバックを自分のものにしてしまおうという意思がある。そして、XはMに対し、 親子という優越的な地位に基づいて、具体的に指示を与えていることから、犯罪に対する重大な寄与が認められる。よって、正犯性も認められるから、①共謀が認められる。
また、②共謀に基づく実行行為も認められる。
⑶なお、Mは刑事未成年である(41条)から責任阻却事由が認められるが、責任は個別に判断するから、Xの責任は阻却されず、共謀共同正犯の成立を妨げない。
⑷したがって、Xの上記行為には占有離脱物横領罪が成立しMと共謀共同正犯となる。
以上





