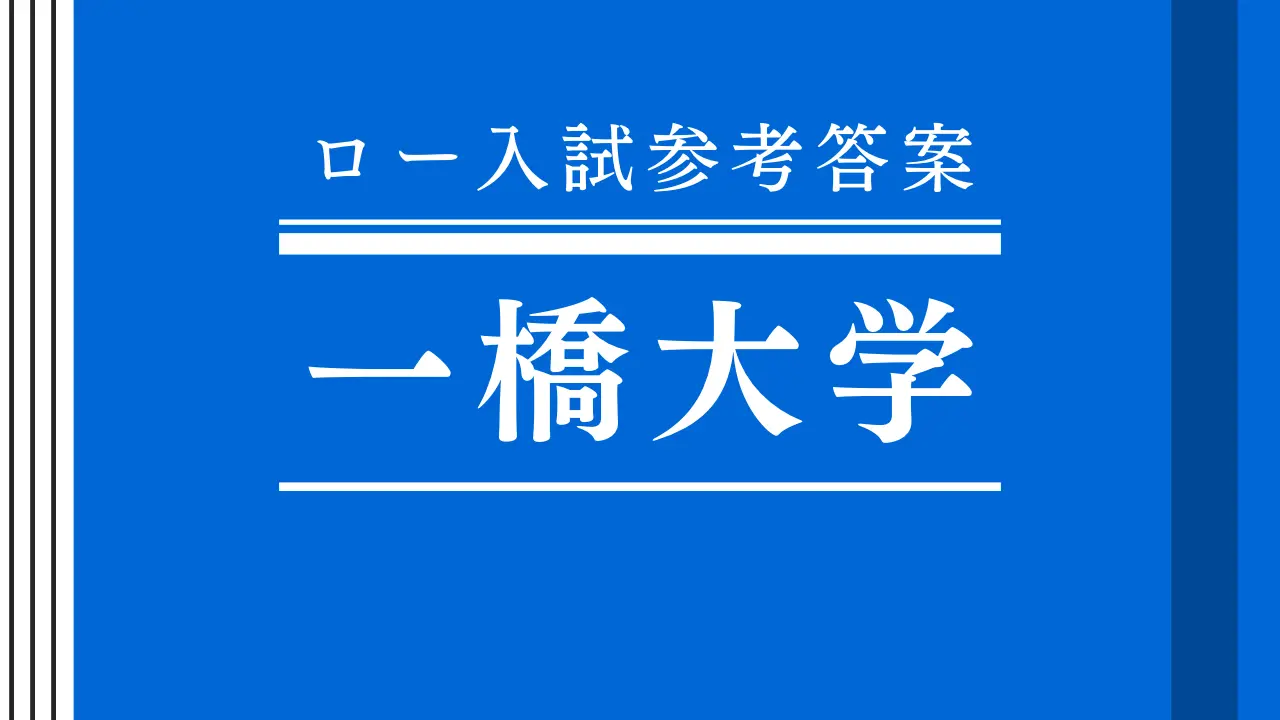
2024年 刑法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2024年 刑法
第一問
1. ⑴XYの罪責を検討する前提として、XYが路上でAを殴打した行為(以下「第一行為」という。)と川原でXがAを殴打した行為(以下「第二行為」という。)の行為の一個性が問題になる。
⑵この点、行為は主観と客観の統合体であることから、一連の行為か別個の行為かどうかの判断は両行為の時間的場所的接着性、意思の連続性、行為態様等の総合考慮で決するべきである。
⑶確かに、第二行為は第一行為が起こってから10分ほど歩いた川辺において行われており、行為の時間的場所的接着性は認められる。もっとも、Xは第二行為の後、Aが旧友であることに気づき、一旦「ごめんな」と述べ和解に至っている。よって、攻撃意思は一度途切れており意思の連続は認められないから、以下両行為は別個の行為として検討する。
2. Xの罪責
⑴第一行為について、Aに対する傷害罪(刑法(以下法名略)204条)が成立しないか。
ア 「暴行」(208条)とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいう。本件で、第一行為はXとYがAの顔面や腹部を手拳で数発殴打することにより、人の身体に不法な有形力を行使しているから「暴行」が認められる。
イ 「傷害」とは人の生理的機能に侵害を与えることをいうところ、Aは全治一か月の顔面打撲の怪我を負ったのであるから、「傷害」結果が発生している。
ウ ここで、上記傷害結果は第一行為と第二行為のいずれによって発生したか明らかでないため、利益原則が適用される。本件では暴行の態様が軽く犯情面でXに有利となる第二行為によって傷害結果が生じたものと考える。
エ それを前提として、第一行為と上記傷害結果の因果関係が認められるか、第二行為という介在事情が存在することから問題となる。
この点、因果関係の有無は、条件関係の存在を前提に、全ての客観的事情を基礎として行為の危険が結果として現実化したか否かによって判断する。
本件において、第一行為がなければ、XはAが小学校時代の同級生であったことに気づくこともなく、第二行為も存在しなかったのであり、傷害結果が生じることもなかったのであるから、事実的因果関係すなわち条件関係は認められる。もっとも、傷害結果は第二行為によって生じたのであるから、介在事情の結果に対する寄与度は高かった。また、第二行為の動機は小学生時代のAに対する怨恨であり、第一行為によってこれが誘発されることもないし、第二行為の結果が拡大したという関係にもない。したがって、介在事情の異常性を判断するまでもなく、第一行為には、第二行為を介在して上記傷害結果を発生させる危険が含まれておらず、危険の現実化は認められない。
よって、第一行為と傷害結果の間に因果関係は認められない。
オ もっとも、Xは暴行罪の故意(38条1項)が認められる。
カ よって、第一行為には暴行罪が成立する。
⑵また、第二行為はXがAの顔面を手拳で1発殴打するという「暴行」によって、上記の傷害結果をAに生じさせたものであるから、Xの同行為には傷害罪が成立する。
3. Yの罪責
⑴第一行為について、Xとの傷害罪の共同正犯(60条)が成立しないか。
ア 共同正犯の処罰根拠は、自己及び共犯者の行為を介して法益侵害を共同惹起し、結果との因果性を有する点にある。 そこで、共同正犯に該当するか否かは、①共謀、②共謀に基づく実行行為があるかで判断する。 そして、①の検討には、正犯意思と意思連絡の存在を考慮要素とする。
イ 本件で、XYは言葉を介してAを殴打することを示し合わせたわけではないが、XがYのほうを見て頷くとYも頷き返し、同時に殴り掛かったというのであるから、前記頷き合いによってAに対する暴行罪についての黙示の意思連絡があったといえる。また両者共に殴打しており正犯意思の存在が推認されるから、暴行罪の共謀の存在が認められる。
加えて、かかる共謀に基づいて第一行為という暴行罪の実行行為を行っているから①②をともに充足する。
ウ また、Yについても利益原則の観点から第二行為によって傷害結果が生じたと解すべきであるから、上記と同様に第一行為と上記傷害結果の因果関係は認められない。
エ 以上より、Yには第一行為につき暴行罪が成立し、甲と共同正犯となる。
⑵第二行為についてもYにXとの傷害罪の共同正犯が成立するか。共同正犯の要件は上記のとおりであるところ、第二行為が上記共謀に基づくものと言えるか問題となる。
ア 共犯の処罰根拠が上記のとおりであることからすれば、共謀の射程は実行行為が共謀と因果性を有しているといえる場合に認められる。
イ 本件では、第二行為と上記の共謀内容は、行為態様が拳での殴打という点において共通している。もっとも、第二行為は近所の川原での小学生時代の怨恨を動機とするX単独の暴行であるが、上記の共謀内容は町での激情によるXY共同の暴行であり、両者には共謀と実行行為の因果性を否定する程度の重大な齟齬があると言える。よって、第二行為と上記共謀は因果性を有するとは言えず、第二行為は上記共謀に基づく実行行為ではいためYは第二行為について責任を負わない。
4. 罪数
上記のとおり、Xには暴行罪の共同正犯と傷害罪が成立し、両者は併合罪(45条)となる。なぜなら両罪は保護法益を同じくするが、第一行為と第二行為は行為態様や発生した場所が異なり、上述の通り意思の連続も認められないため、包括一罪と解するべきではないからである。
一方、Yには暴行罪の共同正犯が成立する。
第二問
1. Xが本件財布を管理事務所内にある自分のロッカーに移動させた行為について、業務上横領罪(253条)が成立しないか。
⑴「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務で、相手の委託に基づいて物を管理・保管する事務のこという。
本件で、Xは市立公園の管理事務所事務員という地位に基づいて、継続的にこれに勤務している。そして、届けられた遺失物を委託に基づき保管する事務を行うのであるから、これに該当する。
⑵「占有」とは、濫用のおそれのある支配力をいうが、本件でXは市立公園の管理事務所の職員として本件財布を遺失物として預かり管理することにより、事実上占有していたのであるから「占有」が認められる。
⑶本件財布はAが何者かから窃取したものであり、少なくともXの所有物ではないため、「他人の物」といえる。
⑷「横領」とは不法領得の意思を発現する一切の行為をいう。
そして、横領罪の法定刑が器物損壊罪よりも重く設定されているのが、横領罪に利欲犯的性質が認められていることを踏まえれば、不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、その物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思をいうと考えるべきである。
本件では、Xは財布が自分の好みのデザインであり、使い古された感じがかえって渋みを増していたため一目ぼれしてしまったのであり、自由に財布を眺めていたいという思いがまさり、気が済んだら財布を遺失物保管箱に戻すかどうかも決めないまま財布を管理事務所内にある自分のロッカーに移動させたというのであるから、その財布のデザイン的価値という経済的用法に従って、権限なく所有者でなければできない排他的占有を行っているから、不法領得の意思が認められる。
⑸よって、Xの上記行為に業務上横領罪が成立する。
2. 次に、XがAから本件財布が盗品であると告げられた後もこれを占有していたことをもって、盗品等保管罪(256条2項)が成立しないか。
⑴盗品等保管罪の処罰根拠は本犯助長的性質を有することであるから、「保管」とは窃盗犯人等から委託を受け、盗品等の占有を得て管理することをいうと解する。
本件において、Xは窃盗犯人Aから「盗品」(256条1項)たる財布を預かるように委託され、それに基づいて財布の占有を得て管理していたのであるから、「保管」が認められる。
⑵もっとも、本問において、Xは保管の途中でAからの電話によって本件財布の盗品性を認識したのであるから、これを預かった時点では財布が盗品であることは知らなかった。このような場合にも盗品等保管罪の故意(38条1項)が認められるのか。
この点、そもそも盗品等罪の保護法益は本犯被害者の被害物への正常な回復追求権の行使を保全することにあり、同時に本罪の本犯助長的性格を考慮することにある。
そうだとすれば、保管を行っている間は被害者の追求権を侵害している以上、本罪は継続犯であると考えるべきである。そのため、占有開始時に財物が盗品であることを知らなくとも、途中で知った時点から上記保護法益は妥当し本罪は成立すると考える
⑶上述のとおり、Xが本件財布が盗品であると認識した時点から同罪の故意が認められる。
⑷よって、Xの上記行為に盗品保管罪が成立する。
3. 上記の横領行為や保管行為に証拠隠滅罪(104条)が同時に成立しないか問題となる。
この点、犯人の自己の証拠隠滅については期待可能性がないため同罪は成立しないところ、行為者の主観によって期待可能性を判断することは不明確であり、客観的な基準によるべきである。よって、他人の犯罪の証拠であっても、同時に自己の犯罪の証拠である場合には一律に期待可能性がないとして、証拠隠滅罪は成立しないと解する。
本件では、本件財布がX自身の証拠でもあるから、上記の行為に同罪は成立し得ない。
4. 罪数
Xには業務上横領罪と盗品等保管罪が成立して、両罪は併合罪(45条)となる。
以上





