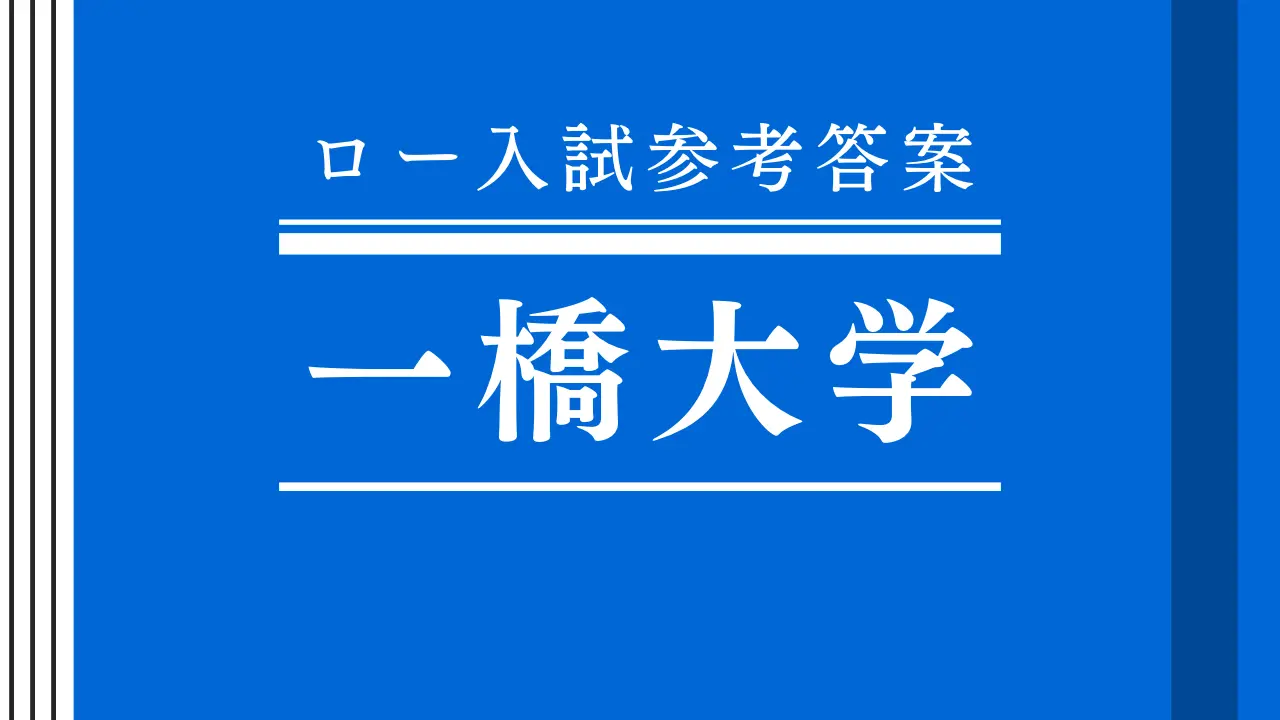
2023年 刑事系/刑法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2022年 刑事系/刑法
刑法 第1問
第1(第1問)
1. Xの罪責については、Aに対しての共犯の成否が問題となるため、まず、Aの罪責を検討する。
⑴ AがB衣料品店の商品10点(以下、「本件商品」という)を持ち去った行為に窃盗罪(刑法(以下、略)235条)が成立しないか。
ア 「他人の財物」とは、他人が所有し、かつ占有する財物をいう。本件では、本件商品はB衣料品店の所有物である。また、B衣料品店の支店では、支店長が鍵を管理しており、営業日の店の解錠及び施錠は支店長の職務となっていた。そのため、D支店の管理支配権は、D支店の支店長にあるといえ、D支店に置かれていた本件商品の占有もD支店の支店長にあるといえる。したがって、本件商品は、D支店の支店長という他人が所有し、かつ占有する財物といえ「他人の物」にあたる。
イ 次に、「窃取」とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して、自己又は第三者の占有に移す行為をいう。本件では、Aは、本件商品を支店長らには無断でその意思に反して、鞄に詰めてCビルを後にしており、「窃取」したといえる。
ウ そして、Aには、窃盗罪の故意(38条1項本文)があり、権利者排除意思及び利用処分意思を内容とする不法領得の意思も認められる。
エ 以上より、Aの上記行為に窃盗罪が成立する。
2. 次に、Xの罪責を検討する。
⑴ Xが、AがEに発見されるのを防ぐために、Eに連絡しEを警備員室に戻した行為についてXの上記窃盗罪と共同正犯(235条、60条)が成立しないか。
ア 共同正犯の処罰根拠は、法益侵害結果に対して因果性を及ぼす点にあるから、「共同して犯罪を実行した」(60条)といえるには、共謀に基づく実行行為が必要である。そして共謀とは、①特定の犯罪を共同実行する旨の意思連絡が、②正犯性を備えた者らの間で交わされた状態をいう。
これをみるに、XはAを助けるために、上記行為を行っているが、AはXの上記行為を認識しておらず、XAの間に意思連絡が認められない(①不充足)。
したがって、Xに窃盗罪の共同正犯は成立しない。
⑵ では、上記行為に窃盗罪の幇助犯(235条、62条1項)が成立しないか。
ア まず、上記の通り、AはXの行為を認識していないところ、正犯と共犯との間に意思の連絡がない場合でも幇助犯が成立するかが問題となる。
ここで、共犯の処罰根拠は、法益侵害結果に対して因果性を及ぼす点にあるから、「幇助」とは、正犯行為を物理的もしくは精神的に促進し又は容易にする行為をいい、これを満たす限り正犯と共犯との意思連絡がなくとも幇助犯は成立する。
これをみるに、Xは上記行為によって、D支店の入居しているフロアを巡回中であったEを警備員室に呼び戻し、AがEに発見されるのを防いでおり、かかる行為は、Aが本件商品をD支店から持ち出すことをEによって阻止されることを事前に防ぎ、Aによる正犯行為を物理的に容易にしたものといえ、「幇助」にあたる。
イ もっとも、XはAがD支店の支店長から降格したことを知らずに支店長であると思って上記行為に及んでおり、Aが支店長として占有する本件商品を所有者に無断で視点から持ち出すという業務上横領罪の幇助(253条、62条1項)を行う認識であったため、窃盗罪の幇助故意が認められないのではないか。
この点、故意責任の本質は、規範に直面し反対動機が形成可能であったのにもかかわらず、あえて行為に及んだことに対する道義的非難である。そして、行為者の認識した犯罪と現に発生した犯罪の構成要件に重なり合いがある場合は、行為者はその限度で構成要件該当事実の認識があり規範に直面したといえるからかかる限度で故意犯が成立すると考える。
これをみるに、上記の通り本件では客観的にはAが行った犯罪は窃盗であるところ、Xは業務上横領罪を幇助する意思で上記行為を行っている。この点、両罪の保護法益は、少なくとも財物の所有権という点では共通であるし、行為態様も所有者の意思に反する領得行為という点で共通している。したがって、両罪には実質的な重なり合いが認められ、Xには重なり合う単純横領罪(252条1項)の限度で故意が認められる。
以上より、Xには単純横領罪の幇助の故意が認められるところ、窃盗罪の幇助の故意は認められない。したがって、Xには、窃盗罪の幇助犯は成立しない。
ウ もっとも、上記の通り、窃盗罪と業務上横領罪の構成要件は、単純横領罪の範囲で符合するから、窃盗罪の構成要件が実現された場合には、それと重なり合う単純横領罪の客観的構成要件該当性が認められる。そしてXには、上記の通り幇助の故意も認められるから、Xの上記行為に単純横領罪の幇助犯が成立する。
⑶ 以上より、Xには単純横領罪の幇助犯が成立する。
刑法 第2問
第1(設問)
1. Xが、ウェブサイトにA警察署の警察官が酩酊した挙句、殴り合いのけんかをしたと自ら想像した虚偽の情報を掲載したことに偽計業務妨害罪(233条後段)が成立しないか。
⑴ Xは、自らの運営するウェブサイトにA警察署の警察官が酩酊した挙句、殴り合いのけんかをしたと自ら想像して作り出した客観的真実に反する情報を掲載しており「虚偽の風説を流布し」たといえる。
⑵ そして、同罪の保護法益は、業務活動そのものにあるところ、かかる趣旨から「人」には、自然人のみならず法人などの団体も含まれるためA警察署も「人」にあたる。
⑶ さらに、同罪の保護の対象となる「業務」に警察官による公務が含まれるか問題となるも、威力による妨害の場合と異なり、偽計による妨害は、強制力によって妨害を排除することが容易でないため、対象となる業務が権力的業務か否かに関わりなく公務も「業務」に含まれると考える。したがって、本件でもA警察署の業務は「業務」にあたる。
⑷ そして、上記Xの行為によって、A警察署への市民信頼が棄損され、A警察署に苦情が殺到したり、不信感を持った市民がA警察署への協力を拒むなどしてA警察署の業務が円滑に行われなくなるおそれがあり、上記行為は、A警察署の業務を「妨害し」たといえる。なお、本件では、実際にA警察署に苦情が寄せられたり、マスメディアで報じられたりすることはなかったが、本罪は、抽象的危険犯であるからウェブサイトに虚偽の風説が記載され係る情報が不特定多数の者に認識される状態であった以上、犯罪の成立は否定されない。
⑸ 以上より、Xに偽計業務妨害罪が成立する。
2. Xが、ウェブサイトにA警察署に爆弾が仕掛けられたという架空の情報を掲載したことに偽計業務妨害罪が成立しないか。
⑴ これをみるに、Xは上記情報をウェブサイトに掲載することで、A警察署の所員を錯誤に陥れており「偽計を用い」たといえる。
⑵ そして、それによって、A警察署は1日がかりで多くの警察署員が署内に爆弾がないか隅々まで点検することになり、A警察署の通常の業務が妨害されたといえる。したがって、A警察署という「人の業務」を「妨害し」たといえる。
⑶ 以上より、上記行為に偽計業務妨害罪が成立する。
3. 以上の通り、Xには2つの偽計業務妨害罪が成立し、両罪は、被害者を同じにし、同一のウェブサイトに書き込むもので行為態様も共通するから、包括一罪となる。
以上





