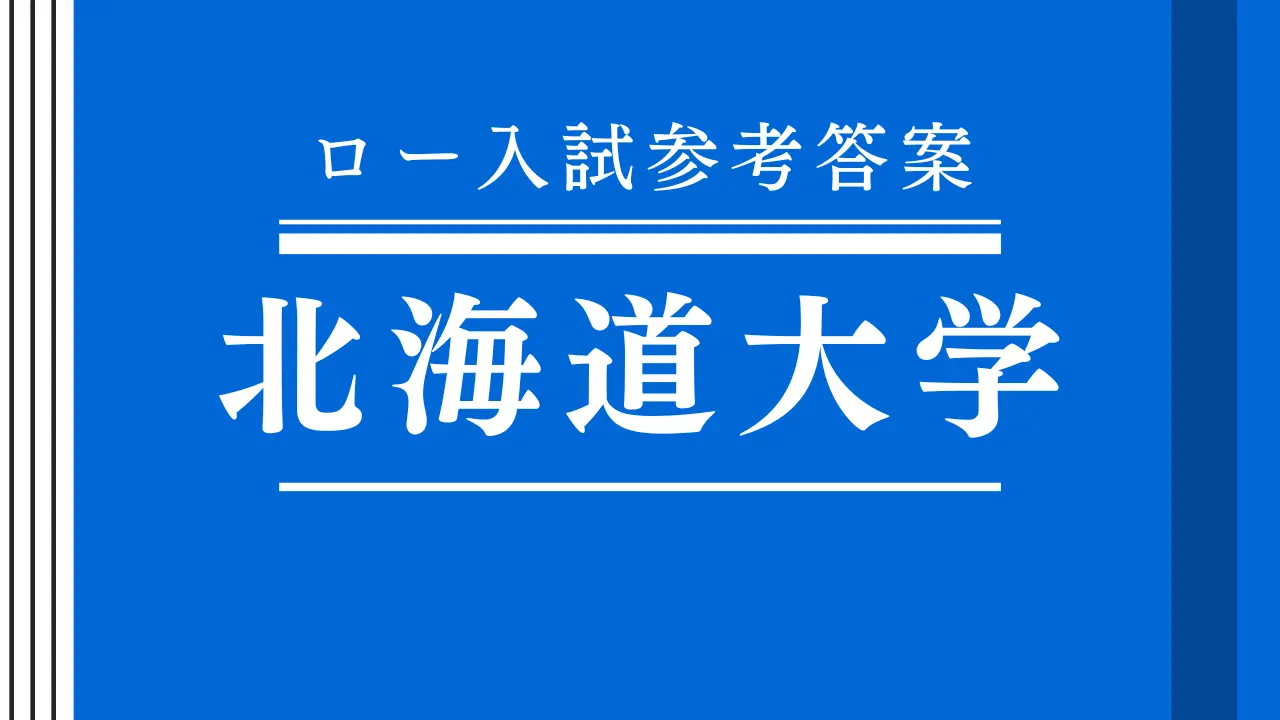
2022年 行政法 北海道大学法科大学院【ロー入試参考答案】
10/26/2023
The Law School Times【ロー入試参考答案】
北海道大学法科大学院2022年 行政法
問1
1. まず、Xは本件処分が懲戒処分の指針に反するものであるから、S市長の裁量権を逸脱するものであって違法である旨の主張を行うべきである。
⑴ 前提として、S市長は本件処分につき裁量を有するか。
裁量の有無は処分の性質、根拠法令の文言から判断する。
本件処分の根拠法令は地方公務員法(以下法)29条1項2号であり、同号では「職務を怠った」という抽象的な文言が用いられており、柱書においても「できる」という文言が用いられている。このような文言となったのは「職務を怠った」かどうかの判断は、職の種類や具体的な状況等を踏まえた専門的な考慮を要するものであり、行政庁に対してかかる処分ついての裁量を与えるべきだからである。
よって、S1市長は本件処分について要件・効果裁量を有する。そして、本件処分には懲戒処分の指針が規定されているが、かかる指針は行政庁が上記の裁量に基づき、処分をするにあたっての基準を定めたものなので、裁量基準にあたる。
⑵ では、裁量基準に従わない処分は違法といえるか。
ア 確かに、裁量基準に法的規範性はなく、あくまで行政規則たる内部基準であるから、それそのものが国民の権利義務を直接形成することはないし、裁判所を拘束することもない。
しかし、行政庁が自ら裁量基準を定め公開した以上は、それを適用しない合理的理由がない限り平等原則を介して行政機関を拘束するのであって、合理的理由を欠く場合には裁量権の逸脱濫用として違法となる。
⑶ 本件では、指針第2の1(4)にて勤務態度の不良につき定めているものの、かかる規定は減給と戒告にとどめているのであり、退職処分までは規定されていない。また、積極的に上記指針に反する合理的理由も存在していないのであるから、本件処分は違法である。
2. 次に、Xは本件処分が比例原則に反するものであるから、S市長の裁量権を逸脱するものであって違法である旨の主張を行うべきである。
⑴ 上記の通り、本件処分には行政庁の裁量が認められる。
⑵ そこで、判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法(行訴法(以下略)30条)となる。
⑶ 本件では、確かにXは職務時間にまで及びパチンコをしている。しかし、パチンコの開始時間は休み時間であって職務中ではなく、実質的に職務時間中のパチンコは40分程度に過ぎない。また、Xは反省し、過去にもこのような懲戒事由を発生させたこともないのであり、悪性は低い。さらに、配偶者と高校生の子供がいるXの職を奪うことはXの収入を途絶えさせ家族の生活を困難にすることを意味する。そうだとすれば、他にXの行為の悪性を示すような事情もない本件で、懲戒免職という、今後の公務員としての地位を失わせる重大な処分を行うことは比例原則に反するものであり裁量権の逸脱濫用としてとして違法である。
3. さらに、Xは、本件処分を行うにあたって提示された理由が不十分であり、行政手続法14条1項に反するとして違法と主張すべきである。
⑴ 14条1項の趣旨は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。
⑵ そうだとすると、理由提示の程度としては、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がなされたのかを、その記載自体から了知しうる程度のものが要求される。また、本件のように処分基準が定められているような場合には、処分基準によりさらに処分の複雑性を増しているのであるから、より詳細な理由提示が求められる場合がありえる。
そこで、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮して、必要な記載の程度を決定すべきである。
⑶ 本件では、処分基準たる指針が存在し、その内容は根拠法令よりも詳細であるし上、処分量定も総合考慮によるものとされており、十分な説明がなければ自らのいかなる行為が量定上強く考慮されたのか分からず、不服申立てが困難である。また、根拠法令は上述の通り一義的な確定が困難な性質を持ち、それ自体として明確でない。本件処分は懲戒免職という公務員に対する最も厳しい処分のひとつであり、特に不服申立てや慎重性を担保する必要も高い。よって、本件処分に当たっては処分基準の具体的適用関係まで示されなければ理由の提示としては不十分である。本件では、指針に関して一切の記述を欠き、また「職務怠惰」などと根拠法令に当たった理由すらも不明確であり、理由提示が不十分である。そして、理由提示の欠如は重大な手続き違反であり、取消事由として違法と言える。
問2
1. Xとしては本件処分の無効確認訴訟(3条 4項)を提起することが考えられる。
2. 無効確認訴訟を提起するためには「当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分又は裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないもの」にXが該当する必要がある。後段については、処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えが可能な場合であっても 、無効等確認訴訟による方がより直截的で適切な紛争の解決になる場合を含む。
3. 本件において、Xは本件処分の名宛人であり、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する。しかし、本件では、確認の訴えの提起により、現在の公務員の地位及びその他公務員の地位を有することによって生じる債権等も存在することを確認できるのであり、無効確認訴訟と同様の拘束力を有する(行訴法41条1項、33条1項)ことに鑑みると無効確認訴訟の方がより直截的で適切とは言えない。
4. よって、本件では当事者訴訟を提起するべきである。
以上





