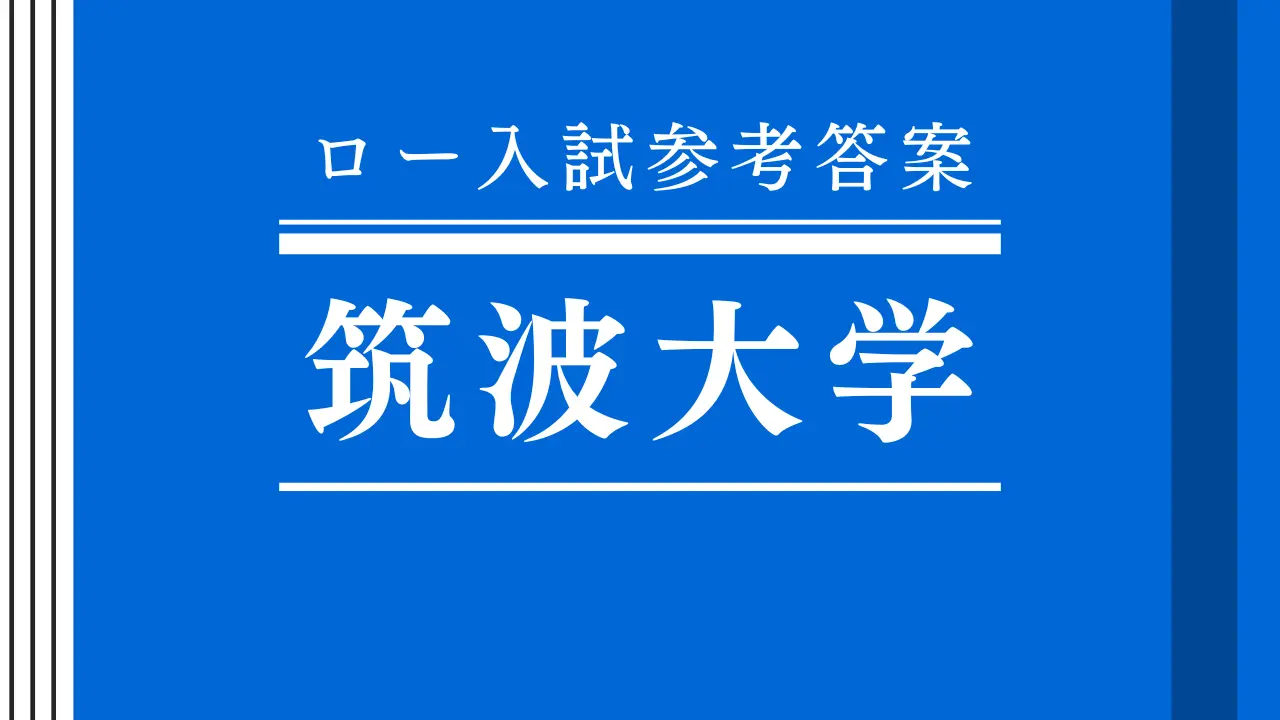
2021年 刑事法 筑波大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
筑波大学法科大学院2021年 刑事法
刑法
第1 甲の罪責
1. バイクに乗ったままAの有する手提げ袋の紐を引っ張り、同手提げから手を離さなかったAをバイクの速度を上げて引きずった行為(1において、本件行為とする。)に、強盗致傷罪(刑法(以下、略)240条前段)が成立するか検討する。
⑴ 「強盗」(同条前段)とは、強盗罪の実行行為に着手したものをいう。そして、「暴行又は脅迫」(236条1項)とは、財物奪取に向けられた相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫をいうものと解する。
本件行為は、「他人の財物」(同項)たる上記手提げ袋の奪取を目的として行われている。そして、本件行為を受けたAは、上記手提げ袋から手を離さず抵抗し、これを受けて甲はバイクの速度を上げている。一般的に、このような行為を受けて手提げ袋から手を離さなければ、生命・身体に危険が及ぶことは明白である[1]。そのため、本件行為は非常に危険性の高い行為と評価できる。このような危険性の高い行為を受ければ、通常、恐怖で抵抗することが困難になる。そこで、本件行為は相手方たるAの反抗を抑圧するに足りる程度のものといえ、「暴行」(同項)にあたる[2]。
したがって、甲は「強盗」にあたる。
⑵ 強盗の手段たる本件行為によって、Aは身体の生理的機能に対する障害たる打撲傷や擦過傷を腕や膝に受けている。そのため、本件行為によって「負傷」(240条前段)結果が生じたといえる。
⑶ 甲は、上記事実を認識しているから故意(38条1項本文)が認められる。また、袋にはいいている大金を領得する意思であるから不法領得の意思も認められる。
⑷したがって、本件行為に強盗致傷罪が成立する。
2. 甲が乙の顔面めがけて拳を振り上げた行為は、乙の身体に向けられた違法な有形力の行使であるため、「暴行」(208条)にあたる。そして、同行為によって、乙は何ら負傷していないことから、「傷害するに至らなかった」(同条)といえる。甲は上記事実を認識して、あえて本件行為に及んでいるので、甲には暴行の故意が認められる。
したがって、同行為に暴行罪が成立する。
3. 乙による防衛行為を受けた甲は、Bにぶつかり、これによってBは頭部を強打するなどして失神している。そこで、同行為は、Bの身体に対する違法な有形力の行使といえ、「暴行」にあたる。もっとも、同行為は、甲が意図して行ったものではないため、同罪の客観的構成要件該当事実に対する認識・認容が認められない。したがって、同行為に傷害罪は成立しない。
また、たとえ、甲による上記暴行行為に端を発しているとはいえ、乙から一本背負の要領で投げ飛ばされ、その結果第三者にぶつかり怪我を負わせることまでも予測することは非常に困難である。そこで、「傷害」(209条1項)結果及びこれに至る因果関係の基本的部分に対する予見[3]が可能であったとはいえず、同行為につき「過失」(同項)は認められない。そこで、本件行為に過失傷害罪(同条)も成立しない。
4. 以上より、強盗致傷罪及び暴行罪が成立し、両罪は併合罪(45条前段)となり、甲はかかる罪責を負う。
第2 乙の罪責
1. 甲の胸ぐらを掴み、一本背負の要領で同人を投げ飛ばして甲を負傷させた行為(1において、本件行為とする。)に傷害罪(204条)が成立するか検討する。
⑴ 本件行為は、甲の身体に向けられた違法な有形力の行使であるため、「暴行」に当たる。そして、本件行為によって、甲は身体の生理的機能に対する傷害たる全治10日間の打撲傷を背中等に負った。そこで、本件行為によって、「傷害」(204条)結果が生じたといえる。
⑵ 上記事実を認識してあえて本件行為に及んでいる以上、乙に故意が認められる。
⑶ 本件行為は自己の身を護るために行われている。そこで、本件行為に正当防衛(36条1項)が成立し、その違法性が阻却されないか検討する。
ア 本件行為の当時、乙は甲から上記暴行行為を受けている。そのため、乙の身体という法益に対する違法な侵害が現に存在しているといえる。そこで、「急迫不正の侵害」(同項)が認められる。
イ 「やむを得ずにした行為」(同項)とは、防衛手段として必要性及び相当性を有する行為をいうものと解する。
まず、本件行為を行えば、これによって甲を怯ませることができ、更なる暴行行為から逃れることが容易になる。そこで、本件行為には、防衛手段としての必要性が認められる。
次に、甲と乙は背格好が酷似していることから、両者の体格差はほとんど無かったといえる。そして、本件行為は、素手で殴り掛かってきた甲に対して、素手で応戦するものである。そこで、本件行為が防衛行為として過剰なものとは評価し得ず、防衛行為としての相当性も認められる。
したがって、本件行為は「やむを得ずにした行為」にあたる。
ウ 乙は、身を護るために、咄嗟に本件行為に及んでいる。そのため、本件行為当時に、上記急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態にあったといえる。そこで、乙には、防衛の意思が認められる。
したがって、乙は、「自己…の権利を防衛するため」(同項)に本件行為に及んだといえる。
エ よって、本件行為に正当防衛が成立し、その違法性が阻却される。
⑷ 以上より、本件行為に傷害罪は成立しない。
2. 甲を上記の通り投げ飛ばして、同人をBに接触させ、それによりBを負傷させた行為に(2において、本件行為とする。)傷害罪が成立するか検討する。
⑴ 本件行為は、甲を投げ飛ばしてBに接触させるものであるため、Bの身体に対する違法な有形力の行使にあたる。そこで、本件行為は「暴行」にあたる。
⑵ Bは、頭部を強打するなどして失神しているため、身体の生理的機能に対する障害を負ったといえる。そこで、「傷害」結果が発生したといえる。そして、本件行為が無ければ甲がBに接触することはなかったため、本件行為と上記結果との間に条件関係が認められる。そして、本件行為の上記傷害結果への寄与度は高く、本件行為の有する危険性が直接結果に現実化したものと評価できる。
したがって、本件行為と上記結果との間に因果関係が認められる。
⑶ 乙は、本件行為を甲から身を護る目的で行っており、甲がBに接触することは想定していなかった。そこで、本件行為に故意犯は成立し得ないのではないか。
ア 故意責任の本質は、反規範的人格態度に対する道義的非難である。そして、主観と客観との間に齟齬が存するとしても、両事実が構成要件の範囲内で符合している以上、道義的非難を加えることができる。そこで、当該場合であっても故意犯が成立するものと解する。また、故意は構成要件の範囲で抽象化されることから、故意の個数を観念する余地はない。そこで、発生した犯罪事実の個数分の故意犯が成立し得るものと解する。
イ 乙は、甲の身体という「人の身体」を「傷害」する意思でBの頭部という「人の身体」を「傷害」しているから、主観と客観の齟齬は暴行罪の客観的構成要件内で符合する。
ウ したがって、乙には傷害罪の故意が認められる。
⑷ ここで、Bは「不正の侵害」(36条1項)を行う者ではないから、正当防衛の成立はない。正である者に反撃することで「現在の危難」を回避したとみることができ、防衛の意思には「避難の意思」も含まれるから、緊急避難(37条1項)が成立し得るも、「やむを得ずにした」(37条1項)といえるには、危難を避けるための唯一の方法である必要があり、Bに石を当てなければ危難を避けられなかったとはいえないのでこの要件を満たさない。よって緊急避難にもあたらず、違法性阻却はない。
⑸もっとも、乙は、甲に対する防衛行為として本件行為に及んでいることから、違法性阻却事由に対する錯誤が認められ、責任が阻却されないか。
ア 故意責任の本質は、上記の通りである。そして、違法性阻却事由に関して錯誤が存する場合には、道義的非難を加えることができない。そこで、主観面において違法性阻却事由が成立する場合には、責任が阻却されるものと解する。
イ 上記1と同様の理由により、乙の主観面では正当防衛が成立する。
ウ したがって、本件行為について、乙の責任が阻却される。
⑹ 本件行為は、駅につながる地下街への入り口という人通りの多い場所で行われていることから、投げ飛ばした人が第三者に接触することで同人が負傷する可能性を予測することは十分に可能である。そこで、「過失」(209条1項)によって、Bを「傷害」(同項)したといえる。
したがって、本件行為に過失傷害罪(同項)が成立する。
3. 乙が、Cの胸ぐらを掴んで一本背負の容量で同人を投げ飛ばした行為(3において、本件行為とする)に公務執行妨害罪(95条1項)が成立するか検討する。
⑴ 本件行為は、「公務員」(同項)たる警察官Cに向けて行われた不法な有形力の行使たる「暴行」(同項)といえる。
⑵ 「職務」は適法になされたものであることを要する。Cは、Aから通報を受けて付近を警戒していたところ、Aが証言した犯人像と酷似している乙を発見したことから、「君、そこで何をしている。」と申し向けている。そのため、Cによる同行為時に、「疑うに足りる相当な理由」(警察官職務執行法2条1項)が認められる。そこで、同行為は適法な職務質問(同項)といえ、本件行為は「職務を執行するにあたり」(同項)行われたものといえる。
⑶ 上記時事を認識してあえて本件行為に及んだ以上、乙には公務執行妨害の故意が認められる。
⑷ したがって、本件行為に公務執行妨害罪が成立する。
4. 以上より、過失傷害罪と公務執行妨害罪が成立し、両罪は併合罪となり、乙はかかる罪責を負う。
刑事訴訟法
第1 証言①
1. 判所が証言①を証拠とするためには、証言➀に証拠能力が認められることを要する(317条)。証言①は供述証拠であることから、伝聞証拠(320条1項)にあたれば、原則として証拠能力が否定される。
⑴ 供述証拠は、知覚、記憶及び叙述の過程を経て作成されるところ、各過程には誤謬が介在するおそれがあり、証拠の評価を誤るおそれがある。そのため、その内容の真実性を吟味する必要があるところ、公判期日外の供述を内容とする証拠はこれを行い得ない。そこで、同項は、当該証拠の証拠能力を否定している。そこで、伝聞証拠とは、①公判期日外の供述を内容とする証拠であって、②当該供述内容の真実性を立証するために使用されるものをいうと解する。そして、内容の真実性は、要証事実との関係で決せられるものと解する。
⑵ まず、証言①の内容たるXの供述は、公判期日外たる〇〇月××日に為されている。そのため、証言①は、公判期日外の供述を内容とするものである(①充足)。
次に、検察官は立証趣旨の一つとして犯行態様を挙げており、Xが無罪主張をして犯行態様を全面的に否認してこの点が争点になっていることからすれば、草原➀の最終的な立証命題は、立証趣旨通り犯行態様である。そして、恐喝罪の実行行為たる「恐喝」の態様である。そして、証言➀から、被告人が、「修理代の件、これ以上俺を待たせ量ならば、お前の家に火をつけてやる」と怒鳴ったことが証明されれば、「恐喝」の態様が立証されることから、要証事実は、被告人が上記のように怒鳴ったことである。そうすると、Xの発言内容の真実性が問題となる余地はなく、証言①は供述内容の真実性を立証するために使用されるものとはいえない(②不充足)。
⑶ したがって、証言①は伝聞証拠にあたらない。
2. よって、証言①の証拠能力は認められるから、裁判所が証言➀を証拠とすることは許される。
第2 証言②
1. 証言②が伝聞証拠であれば、原則として証拠能力は否定され、証拠採用できない。
2. 証言②の立証趣旨は、Pの意見から、犯行の経緯及び動機である。これは、情状上重要な事実であり、また、被告人が認めていない事実であるから立証する意義がある。そうすると、要証事実は、立証趣旨通りであるといえる。すなわち、証言②から、Vが、修理代を工面した旨述べてから、数日経っているという犯行の経緯・動機を立証する趣旨であり、かかる要証事実との関係で、証言②は、その内容の真実性が問題となる。
よって、証言②は、「公判期日外における他の者の供述を内容とする供述」であり、320条より、原則として証拠能力が否定される。
3. もっとも、324条1項の準用する322条の要件を満たすから、伝聞例外に当たり証拠能力が認められる。すなわち、犯行の経緯・動機にあたる事実の承認という「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」であって「任意になされたものである疑い」はないから、伝聞例外にあたるのである。
4. よって、裁判所は、証拠採用できる。
以上
[1] 平野龍一=松尾浩也編『刑法判例百選Ⅱ各論〔第2版〕』74−75頁
[2] 最決昭和45年12月22日(刑集24巻13号1882頁)
[3] 札幌高裁昭和51年3月18日(高刑集29巻1号78頁)





