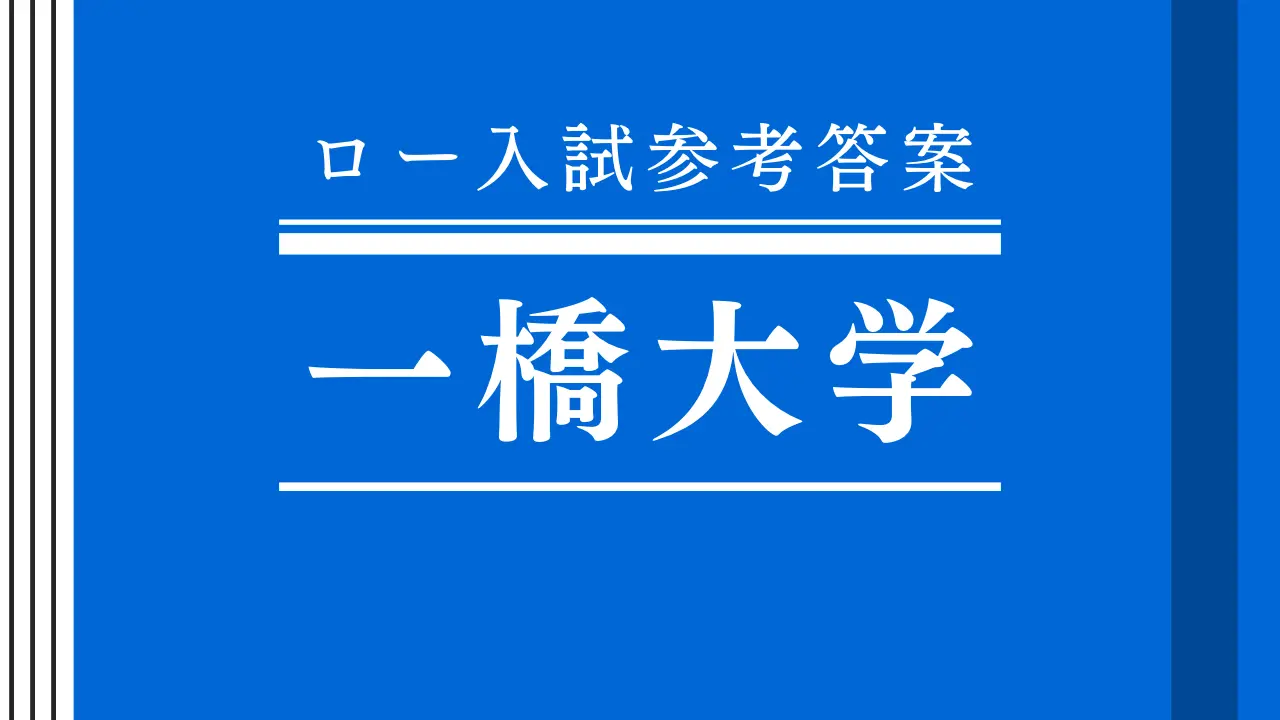
2025年 民法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2025年 民法
第1問⑴
1. 債務者ではないCがした弁済は有効か。
⑴第三者が債務者の意思に反してする弁済が有効であるためには、第三者が正当な利益を有していることを要する(474条1項、2項)。
⑵BはAの意思に反することを知りながら弁済しているから、「正当な利益」を有しているかが問題となる。
ここで、BとCとの間には直接の契約関係がないが、α債権を被担保債権とする抵当権が乙に設定されており、これが実行されてしまうとCは退去して買受け人に乙を引渡す義務を負う法律関係が生じる。したがって、Cは自らの乙の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益があるといえ、「正当な利益」を有すると言える。
よって、Cの弁済は有効である。
2. そして、有効に弁済の効果が生じることにより、CはAに対して弁済額と同額の求償権を取得する。
3. また、弁済による代位によりCは債権者Yに代位し(499条)、求償の範囲内において、債権の担保として債権者が有していた物的・人的担保などの一切の権利を行使できるため(501条1項、2項)、抵当権を行使できる。
4. さらに、Cは求償権を自働債権として、賃料額が求償権の額に達するまで、賃料債権を受働債権として相殺(505条1項本文)することができる。
第1問⑵
1. Bによる物上代位権(372条、304条)の行使は認められるか。
2. Bは、Aに金銭を有効に貸し付け、どう契約に基づく貸金返還請求権を担保するために、設定者Aが所有する乙建物に抵当権を設定し、登記を備えているから、乙建物について抵当権を有効に取得し、第三者対抗要件も備えている。
3. もっとも、本件債権は、Dに譲渡され、Dが対抗要件(467条2項)を備えている。それでも、「差押え」をして物上代位をすることができるか。債権譲渡が「払渡し又は引渡し」(304条1項但書)に含まれるかが問題となる。
⑴372条の準用する304条が「差押え」を要求する趣旨は、弁済のあて先が不明確になることによる二重弁済の危険から第三者を保護する点にある。一方、第三者については、抵当権の効力が物上代位の目的債権についても及ぶことは抵当権設定登記により公示されているとみることができるから、「差押え」によってこれを保護する必要はない。また、債権譲渡が「払渡し又は引渡し」に含まれると解せば、設定者は債権譲渡をして、容易に物上代位を潜脱しうる。そこで、債権譲渡は「払渡し又は引渡し」にあたらないと解する。
⑵AのDに対する債権譲渡は、「払渡し又は引渡し」に含まれないので、Bは債権譲渡の前にβ債権を差し押さえておく必要はない。
4. したがって、Bによる物上代位権の行使は認められる。
第2問⑴
1. CはAに対し、本件契約に基づき履行請求をする。
甲はBの所有物であるから、本件契約は他人物売買であり、他人物売買の売主は、権利を取得して買主に移転する義務を負う(561条)。
2. ここで、Bが死亡した(882条)ことにより、Bの子であるA、Dがそれぞれ2分の1ずつの法定相続分によりAを相続することで、甲について2分の1ずつの共有持分権を取得するに至った(887条1項、900条4号本文、896条、898条1項・2項)。
まず、無権代理人と他人物売買は、追認により法律行為に基づく権利変動の根拠である財産管理権が事後的に補充されるという点で本質的に同一であるとの理由から、他人物売買には116条類推適用による遡及効のある追認が認められると解される。
次に、無権代理において本人が死亡した場合の無権代理人の地位については、本人の地位と無権代理人の地位は併存すると解される。そして、自らした無権代理行為を、後になって相続によって得た本人の地位に基づいて追認を拒絶するのは禁反言の法理に抵触するから、無権代理人は信義則(1条2項)上追認を強制させられると解する。
そこで、他人物売買の売主が所有者を相続した場合についても、他人物売買の売主が所有者から相続した追認拒絶権を行使することは、禁反言の法理に抵触し、信義則上追認を強制させるべきと考える。
3. よって、Aは自己の持分の限度で履行の拒絶をすることができない(899条の2)。
第2問⑵
1. まず、BはCに対し、所有権(206条)に基づく甲の返還請求をする。
甲はBの所有物であり、Aに甲を売却する権限はないから、Cは甲を権原なく占有しているといえる。
よって、Bの返還請求は認められる。
2. 次に、BはCに対し、、不当利得(703条)に基づく使用利益の返還をする。
Cは、1年間に渡り権原なく甲を使用しているから、かかる使用利益は「法律上の原因がない」利得といえる。そして、Bはそれに対応して1年間使用利益を享受できていないから、損失と因果関係も認められる。
よって、BのCに対する使用利益の返還請求も認められる。
但し、CがAに対して使用利益の返還をした場合には、「受益」が認められないので、BのCに対する使用利益の返還請求は認められない。
3.CはAに対して、債務不履行解除(542条1項1号)と解除による原状回復請求(545条1項本文)として代金及び利息(545条2項)の返還請求をする。
⑴Bの甲の返還請求は認められるので、小問⑴で論じた他人物売主の義務の履行は社会通念上不能になっていると言えるから(412条の2)、本件売買契約の「全部の履行が不能となった」(542条)といえる。
よって、Cは、本件契約を解除することができ、Aに対する代金及び利息の返還請求が、原則として認められる。
⑵但し、Aは解除による原状回復義務として、①甲の返還請求との同時履行、又は、②使用利益の返還請求(545条3項)との同時履行ないし相殺を主張することが考えられる。甲の返還請求については、CがBにすでに返還している場合には、履行不能により消滅しているから、①の反論は失当である。②についても、CがBに対して使用利益を返還した場合には、同額につきAの債務不履行と相当因果関係が認められる損害が生じているから、損害賠償請求権(415条1項)が発生し、これとの相殺が認められるため、失当となる。
⑶以上から、Aに対する代金及び利息の返還請求は原則として認められるが、Bに対して校の返還をしていない場合には、Aに対する甲の返還と同時履行の関係に立ち、Aに使用利益を弁済するまでは、Bに対する使用利益の返還と同時履行の関係に立つ。
以上





