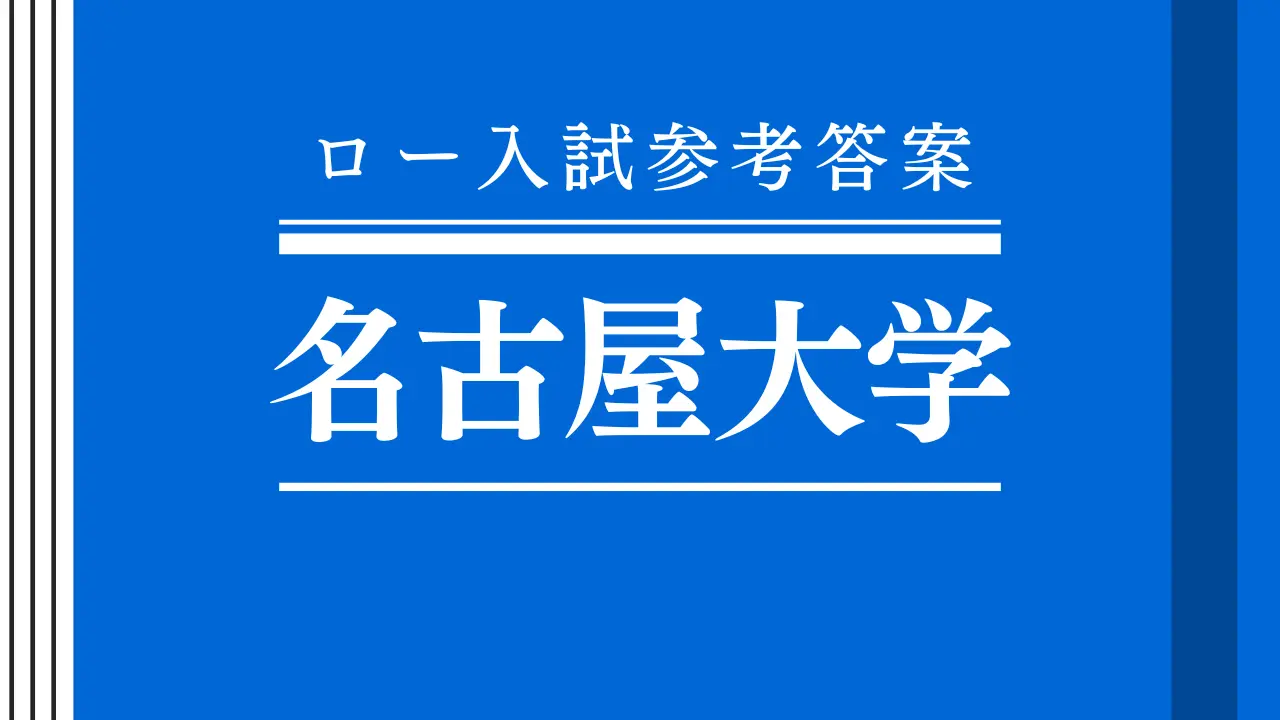
2024年 憲法 名古屋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
7/2/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
名古屋大学法科大学院2024年 憲法
問Ⅰ⑴
憲法は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と定め(4条)、具体的な行為を6条、7条に列挙している。
「おことば」のように、国事行為とも純粋な私的行為ともいえない行為については、天皇の象徴としての地位に基づく行為として、憲法上許容される第三の類型に位置づけるとする象徴行為説、公人としての地位に伴う当然の社交的・儀礼的行為であるとする公人行為説、7条10号の「儀式を行ふ」に含まれるとして、また、国事行為に密接に関連する準国事行為として憲法上許容する国事行為説がある。
問Ⅱ
1. 本件条例はBの「財産権」を侵害するものとして憲法29条1項に反し違憲ではないか。
2. 29条1項は、私有財産制のみならず、個人が現に有する具体的な財産上の権利を「財産権」として保障している。
3. 「財産権の内容は・・・法律で・・・定め」られるものであり(29条2項)、財産権は法律に従属した権利であるが、いったん法律に基づいて取得した具体的財産権を国家が剝奪すれば、財産権の制限にあたる。
Bは、民法に基づき、Bの土地につき所有権という具体的「財産権」を有していた。所有権は地下にも及ぶ(民法207条)から、本条例は、土地所有権という具体的財産権を不利益に変更することにより、これを制限するものである。
4. 財産権は、「公共の福祉」に適合するようにその内容を「法律」で定められるものだから(29条2項)、29条2項の「法律」には条例が含まれるなどとして、「法律の範囲内」(94条)でありさえすれば、条例によって財産権を制限することは許されると解され、「公共の福祉」のための制約に服する。ここにいう制約には、内在的制約のほか、社会全体の利益を図る必要から立法により加えられる制約も含まれる。
⑴(a)立法の規制目的が前示のような社会的理由ないし目的に出たとはいえないものとして公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、(b)規制目的が公共の福祉に合致するものであっても規制手段が目的を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであって、そのため立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えるものとなる場合に限り、当該規制立法が29条2項に反するものとして、その効力を否定することができるものと解する。
⑵ 本件条例の目的は、地下水の水質を保全すること、及び、地下水をかん養し、水量を保全することにより、市民の健康と生活環境を守ることである。日本では、ミネラルウォーター・ビジネスの展開によって、大規模な地下水開発が行われており、地域の水資源として安定的に利用されてきた地下水に新たな問題が生じている。地下水は水資源として、国民のために限られた貴重な資源であるし、国民が生活するために不可欠のものであるから、これらを守るという目的は、社会生活上のやむを得ない必要があるといえる。
よって、この目的は、公共の福祉に合致しないことが明らかとは言えない。
⑶また、地下水の開発を広く認めた場合、大量に採取する業者が増加して、市民に水道水の供給がいかなくなるおそれがあり、その結果、市民の健康や生活環境が害されることになるから、井戸の設置を原則不許可にする必要性がある。
A市地下水保全条例施行規則20条1号2号では、水道水その他の水を用いることが困難である場合、その他井戸を設置することについて市長が特に必要と認めるときには例外的に井戸の設置が許可されるのであるから、土地所有権の不利益変更の程度は軽微である。
そして、Bは生活用水として利用するために井戸を設置しようとしているが、Bの所有地は水道を敷設することが困難な土地とは認められず、また、特に設置を認める必要性もないから、Bは水の利用に関して受ける不利益も小さい。
よって、手段が必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかとはいえない。
5. したがって、本件条例は29条に反さず合憲である。
以上





