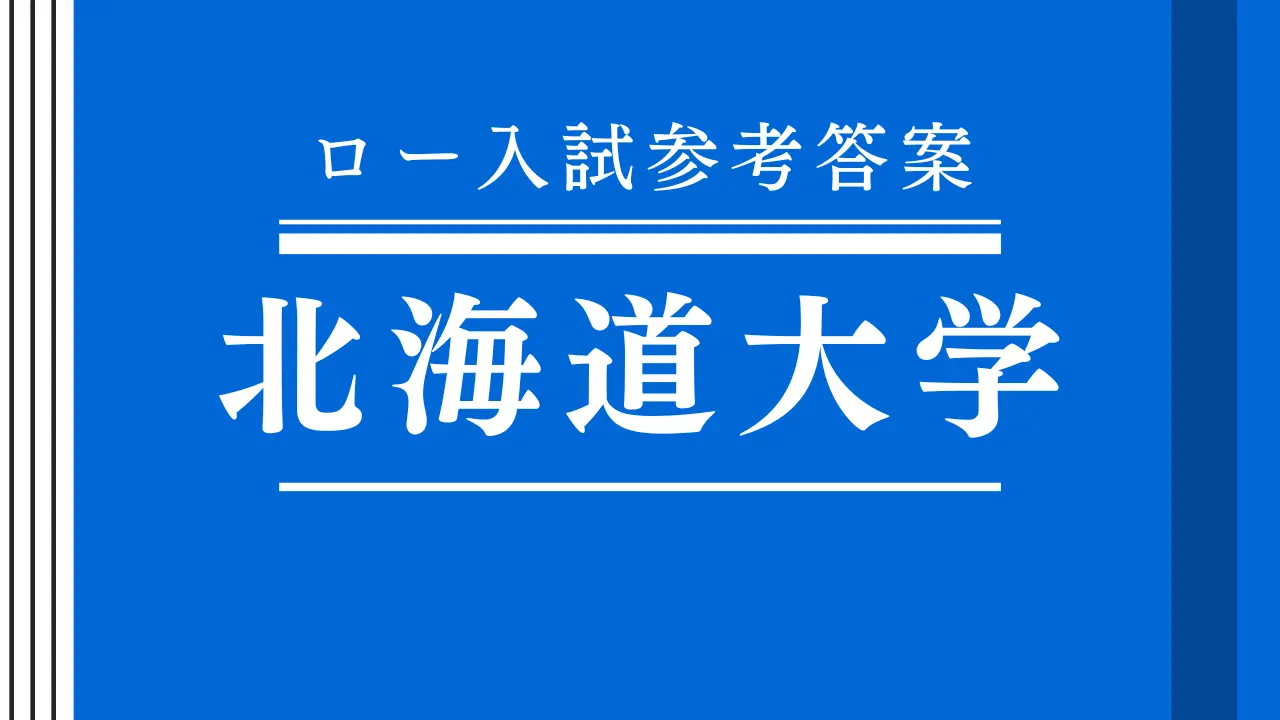
2024年 民法 北海道大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/2/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
北海道大学法科大学院2024年 民法
問1
1. AC間の法律関係
⑴AはCに対して、所有権(民法(以下法令名省略)206条)に基づき、本件土地の明渡請求をすることが考えられる。
ア まず、AはABの売買契約の解除による原状回復で本件土地の所有権を有している。
また、Cは賃貸人として、Dを介して間接占有しているので、Cの占有も認められる。
イ これに対して、Cは自己が「第三者」(545条1項ただし書)にあたり、解除の効力を対抗できないと主張することが考えられる。
この点について、同項の趣旨は、権利者であると信じて、取引関係に入った第三者を解除の遡及効から保護することにあるため、「第三者」とは、解除前の第三者をいうところ、本件でCは、令和4年7月1日に本件土地を購入しており、解除は同年9月15日に行われていることからも、「第三者」に当たるといえる。
ウ もっとも、Cは登記を有していないがその場合でも、第三者として保護されるか。
この点について、同項は、なんら帰責性のない解除者に対して、第三者保護のために、不利益を甘受させるものであるから、第三者は権利保護要件としての登記が必要であると解する。
本件では、C登記を有していないため、権利が保護されない。
⑵したがって、AのCに対する請求は認められる。
2. AD間の法律関係
⑴AはDに対して所有権(民法(以下法名省略)206条)に基づき、建物収去土地明渡請求をすることが考えられる。Aは本件土地の所有権を有している。また、Dは本件建物を建築することにより、本件土地を占有している。
⑵ここで、Dとしては自身が「第三者」(177条)にあたり、Aは登記なくして本件土地の所有権を対抗できないと主張することが考えられる。
本件で、Dは本件土地を賃借しており、新たに独立の法律関係を有するに至っているといえ、「第三者」にあたる。
したがって、Aは本件土地の登記なくしてDに所有権を対抗できない。
⑶よって、保護、Aの請求は認められない。
問2
1. 未登記の場合
⑴CE間
EはCに対して、所有権に基づき土地明渡請求をすることが考えられる。
Cは本件土地について新たに独立の法律関係を有するに至った者であり、「第三者」(177条)に該当する。したがって、Eは登記なくして本件土地の所有権をCに対抗できない。
したがって、Eの請求は認められない。
⑵DE間
ア EはDに対して、所有権に基づき土地明渡請求をすることが考えられる。
まず、DはCとの関係で賃借権を有しているにすぎないが、Cは前述のように無権利者であり、Eに対して所有権を主張できない。
もっとも、Dは本件建物について登記を有しており、第三者に対抗することができる(借地借家法10条1項)。
したがって、Eの上記請求は認められない。
イ また、登記移転がなされてなくとも、賃貸人としての地位は移転するが(605条の2参照)、土留めの工事は必要費にあたり、必要費の償還請求は、支出時の賃貸人に対して行うべきであるため、当然にその債務は移転しない。
したがって、Eは新賃貸人として、賃料の請求はできるが(601条)、Dの必要費の償還請求はEに対して行うことはできない。。
2. 登記移転済みの場合
⑴CE間
EはCに対して、所有権に基づき土地明渡請求をすることが考えられる。
Eは本件土地について登記を具備しており、「第三者」に該当するCに対して所有権を主張できる。
したがって、Eの請求は認められる。
⑵DE間
ア EはDに対して、所有権に基づき土地明渡請求をすることが考えられる。
Dは本件建物について登記を有しており、第三者に対抗することができる(借地借家法10条1項)。Eは本件土地について所有権移転登記を経ているため、「第三者」(177条)に該当するDに対して、本件土地の所有権を対抗することができる。もっとも、Eの所有権移転登記より、Dの本件建物の登記のほうが先立つため、DはEに対して本件土地の賃借権を対抗できる。
したがって、Eの請求は認められない。
イ また、所有権が移転した結果、賃貸人としての地位は移転するが(605条の2参照)、土留めの工事は必要費にあたり、必要費の償還請求は、支出時の賃貸人に対して行うべきであり、当然にその債務は移転しない。
したがって、Eは新賃貸人として、賃料の請求はできるが、Dの必要費の償還請求はEに対してはできず、Aに対して行うべきである。
以上





