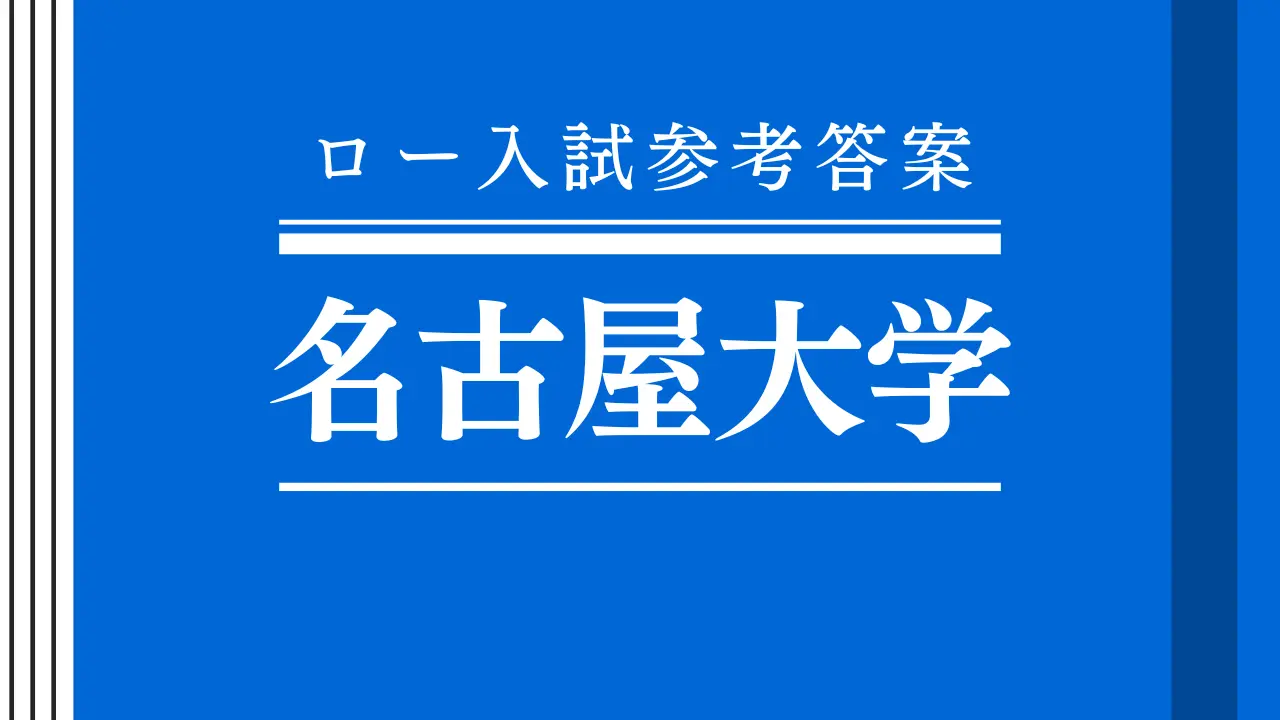
2024年 民法 名古屋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
7/2/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
名古屋大学法科大学院2024年 民法
Ⅰ⑴
共有とは、同一の目的物に対して、それぞれ持分を有し、かつ、その持ち分を自由に処分し得る状態をいう。
合有とは、一定の権利につき、各権利者がそれぞれ持ち分を有するものの、その持分の自由な処分権はなく、かつ持ち分の分割請求が否定される形態の共有のことをいう。
Ⅰ⑵
生来嫡出子とは、正式な婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のことをいう。
準正の嫡出子とは、子ができてから生まれるまでの間に夫婦の間に婚姻関係はなかったものの、子の生後、その子を認知して親子関係を確定させた後に、夫婦が婚姻を行う、もしくは父母が婚姻したのちにその子を認知した子をいう。
Ⅱ⑴
1. CのBに対する本件目的債権300万円の履行請求は認められるか。
2. まず、AC間で将来発生する債権を譲渡する契約が行われている。将来発生すべき債権についても譲渡すること自体は可能である(466条の6第1項、2項)。そして、譲渡された債権はAのBに対する本件基本契約に基づく債権であって、2021年4月28日を弁済期とする分から、2023年3月28日を弁済期とする分までと特定されており、公序良俗に反するところもないから、AのCに対する本件代金債権の譲渡は有効である。
3. Bは、Cの請求に対して、売買目的物の契約不適合により売主に対して有するに至った損害賠償請求権を自働債権とする相殺をもって譲受人に対抗する。かかる反論は認められるか。
⑴Cが譲渡担保契約として譲り受けた債権は、売買契約の代金支払請求権である。ここで、損害賠償請求権と代金支払請求権は同時履行の関係にある(533条かっこ書)から、自働債権に抗弁権が付着しているものとして、相殺は許されないものとも思える。
確かに、原則として自働債権に抗弁権が付着しているときは相殺することはできない(505条1項但書)。もっとも、自働債権と受働債権が互いに同時履行の関係にある金銭債権のときには、同じ原因に基づく金銭債権であるから現実に履行する必要はないし、両債権の相殺は実質的に代金減額請求の意味を有し、相殺を認めた方が清算方法として合理的なので、相殺が許されると解する。
⑵本件の損害賠償請求権と代金支払請求権は同時履行関係にある金銭債権なので、損害賠償請求を自働債権として、代金支払債権を受働債権とした相殺の抗弁が認められる。
4. これに対しCは、損害賠償請求権は対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であるから、相殺は認められないと再反論する。
⑴ここで、対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権であれば、譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(469条1項、2項2号)。
⑵Cは、AからAB間の請負契約の報酬請求権を取得しており、BのAに対する損害賠償請求権は、請負契約に基づいて生じたものである。よって、BはCに対して、損害賠償請求権を自働債権とした相殺を対抗することができる。
Ⅱ⑵
1. CのBに対する本件目的債権300万円の履行請求は認められるか。
Aは有効に本件目的債権を取得しており、Cは譲渡担保権を設定しているものの、代金債権を第三者に譲渡することを禁止する旨の定めが置かれている。
ここで、原則として債権譲渡禁止特約があったとしても、債権譲渡の効力は妨げられず(466条2項)、譲渡制限特約につき悪意又は重大な過失がある譲受人に対して、債務者は履行を拒絶できるのみである(同条3項)。
よって、Cは譲渡担保権の実行により、有効に本件目的債権を取得している。
2. もっとも、Eの支払請求に応じたことによる当該代金債権の消滅をCに対抗することができないか。
⑴債権が二重譲渡され、両譲受人が確定日付ある通知(467条2項)を備えた場合、いかにして優劣を決定すべきか。条文上明らかでなく問題となる。
確定日付の先後をもって優劣を判断すれば、後に到達した通知が優先し得ることとなり法律関係の早期安定の要請に反する。そもそも、法が対抗要件として、通知を要求した趣旨は、債務者による譲渡の認識を通じて債権譲渡を公示する点にある。第三者対抗要件として確定日付が必要なのは、譲渡人と債務者が通謀して、通知の日時を遡らせて第三者の権利を害することを可及的に防止するためと考えられる。
そこで、通知が債務者に到達した日時の先後をもって優劣を決する。
⑵Eの差押命令が送達されたのは、2023年3月19日で、Cによる譲渡担保契約の通知がされたのは、2021年4月3日である。よって、Cが優先する。
3. 債務者は、決定した優劣に拘束されるため、劣後譲受人に弁済しても無効な弁済にすぎない。もっとも、債権の劣後譲受人に対して善意で弁済した場合、478条の適用によって当該弁済が有効とされることがあるのではないか。
劣後譲受人も、「受領権者・・・以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に当たる可能性は否定できない。また、467条は債権の帰属に関する規定なので、弁済の効力を規定する478条を適用しても、対抗要件主義を害しない。
ただし、467条2項の基準がある以上は、優先譲受人の債権譲受行為又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど、劣後譲受人を真の債権者であると信じるにつき相当な理由があることが必要であると考えるべきである。
譲渡担保権が一度有効に設定された以上、いつ実行されてもおかしくない。そのため、Bに、Cが優先しないと誤信してもやむを得ない事情があったとはいえず、Eを真の債権者であると信じるにつき相当な理由もないから、BのEへの弁済は無効である。
4. 以上から、CのBに対する本件目的債権300万円の履行300万円の支払請求は認められる。
以上





