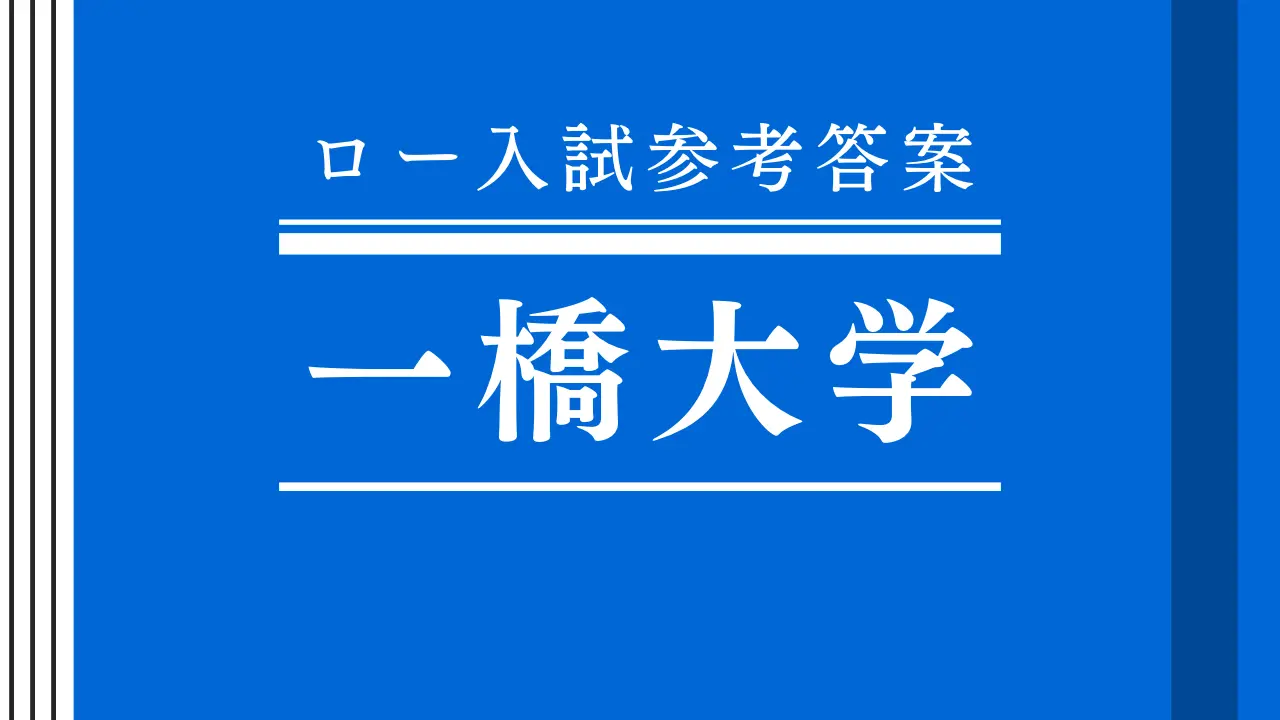
2025年 憲法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2025年 憲法
小問1
1. 本件条例はビル用水法、 工業用水法との関係で「法律の範囲内」(94条)の条例とはいえないから違憲である。
条例は「法律の範囲内」で制定し得る。法令に違反するかは、条例と法律それぞれの文言、趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者に矛盾抵触があるか否かをもって判断する。
まず、法律と規制対象が異なる場合でも、規制をせずに放置する趣旨である場合は、条例は制定できない。一方、ある事項について既に法が定立されており、法律と条例の目的が同一の場合でも、その法が別段の規制を許す趣旨である場合は、同事項についての条例を制定できる。また、ある事項について既に法が定立されているが、法律と条例の目的が異なる場合には、条例が法律の目的効果を侵さないならば条例を制定できる。
上記各法律は、過剰な趣旨による地盤沈下等を防ぐことを目的とする。一方、本件条例は、「地下水の水質保全、地下水の涵養、水量の保全」を目的とする(条例1条)。そうすると、ビル用水法、工業用水法と目的を同じくしていると言える。ビル用水法や工業用水法は、地下水の公共性に鑑み、所有権の制限の最大限を示すものといえ、それを上回る規制を許容する趣旨ではない。
よって、上記各法律よりも重い取水制限を定める本件条例は、「法律の範囲内」の条例とはいえず違憲である。
2. ⑴憲法29条は、私有財産制のみならず、個人の具体的財産をも保障していると解する。
⑵土地所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ(民法207条)ため、地下水は所有権の一内容として保障されるといえる。
3. 「財産権の内容は…法律で…定め」られるものであり(29条2項)、財産権は法律に従属した権利であるが、いったん法律に基づいて取得した具体的財産権の内容を不利益に修正すれば、財産権の制限に当たる。 本件条例39条は新規の井戸の設置を原則として禁止しており、本件規則19条に当たらない場合には井戸の設置をできなくするものだから、土地所有者の所有権という民法207条によって具体化された財産権の内容を不利益に修正するものだから、財産権を制約するものといえる。
4. 財産権は、「公共の福祉」に適合するようにその内容を「法律」で定められるものだから(29条2項)、「公共の福祉」のための制約に服する。ここにいう制約には、内在的制約のほか、社会全体の利益を図る必要から立法により加えられる制約も含まれる。
かかる財産権の制約の合憲性は、⒜いったん定められた法律に基づく財産権の性質、⒝その内容を変更する程度、及び⒞これを変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものであるかどうかによって判断する(国有農地特措法事件)。
5. ⑴所有権は、今日において最も基本的な財産権である。地下水は土地の所有権の構成部分であって、地下水を利用することは、個人が自律した生を全うするために必要である。また、 所有権は排他的で絶対的な権利として具体化されており、このことは地下水の利用にかかる部分についても同様である。そのため、極めて重要な権利と言える。
⑵ そして、新規に井戸を設置することを禁止することで、今後地下水の利用を新たに始めることができなくなるから、制約の程度は大きい。地下水を利用できない者は、水道水を利用せざるを得ないところ、とりわけ給水区域外に居住する者にとっては、莫大な費用を投じて自費で水道を設置するか、水道を利用しない、あるいは、給水地区に居住することのいずれかを選択する他なく、酷な選択を迫ることになる。
本件条例19条は地下水の水量保全を目的としている。Y市の地下構造が、T山地から流れ込む雨水や盆地内の雨水を貯めておく天然の水がめとなっており、Y名水と称される良質な地下水が地下に蓄えられてきたこと、地下水は、Y 市の水道水源の 75%以上を占めてきた他、自然の湧水や個人及び企業所有の井戸による地下水の汲み上げによって、市民に広く利用されてきたことを踏まえると、新規の井戸の設置を一律に禁止することと均衡のとれた目的とは到底いえない。かかる目的は重要な目的と言えず、公共の福祉に合致しているとは言えない。また、取水量を調整することで水量をする保全は達成できる。
6. よって29条に反し、違憲である。
小問2
1. まず、ビル用水法、 工業用水法は全国一律の規制を施す趣旨ではないことから「法律の範囲内」であるとの反論が想定され、妥当である。
ビル用水法、 工業用水法は、あくまで水量の保全のために最低限必要なものを定めたものに過ぎず、地域の実情に応じて条例をもってさらなある取水制限をすることを規制する趣旨までは含まない。特に、適用地域外について別段の規制をすることは、広く認めていると解される。よって、本件条例は、ビル用水法、 工業用水法と矛盾抵触せず、「法律の範囲内」の条例と言え、94条には反しない。
2. 次に、広範な立法裁量が認められることから、明白性の原則が妥当するとの反論が想定されるが、妥当でない。
確かに、経済的自由に対する制約は、一般に、内容が多種多様で、専門的技術的性格を有し、裁判所の審査能力との関係からしても、精神的自由と比べて、立法裁量に委ねられるべき要請が強い。もっとも、そのことから直ちに明白性の原則を採用することはできない。原告の主張するように合憲性を判断するのが妥当である。
3. すでに設置した井戸の撤去を求めるものではなく、従前通りの地下水利用はできるのであるから、制約の程度は軽微であるとの反論が想定される。確かに、従前通りの地下水の利用は可能である。しかし、これまで、市民に広く利用されてきたにもかかわらず、新規に井戸を開設することができなくなるのであるから、私人の予測可能性を大きく害し、行動の意思決定を歪めるものといえ、制約態様は重大と言える。
4. ⑴最後に、以下のような反論が想定される。すなわち、地下水の広い地域にわたって流動するという性質上、何か問題が生じると、広範囲にわたって損害が生じるため、地下水に対する保護の程度は相当程度大きい。そして、Y市では、一時、揚水量が自然涵養量を超え、水位の低下や一部の井戸の枯渇が生じたという事実もある。以上の理由から、井戸の設置を原則禁止とする本件条例39条は、条例目的達成のため合理的であり、29条に反しない。
⑵確かに、井戸の設置を禁止することは地下水の水量保全に資するし、水量を保全する必要がある点については立法事実の支えがあると言える。しかし、大規模な取水のみを制限する法律と比較して過度な規制と言わざるを得ず、それがY市の個別的な実情に基づくものとは評価できない。
5. 以上から、本件条例39条は憲法29条に反し違憲である。
以上





