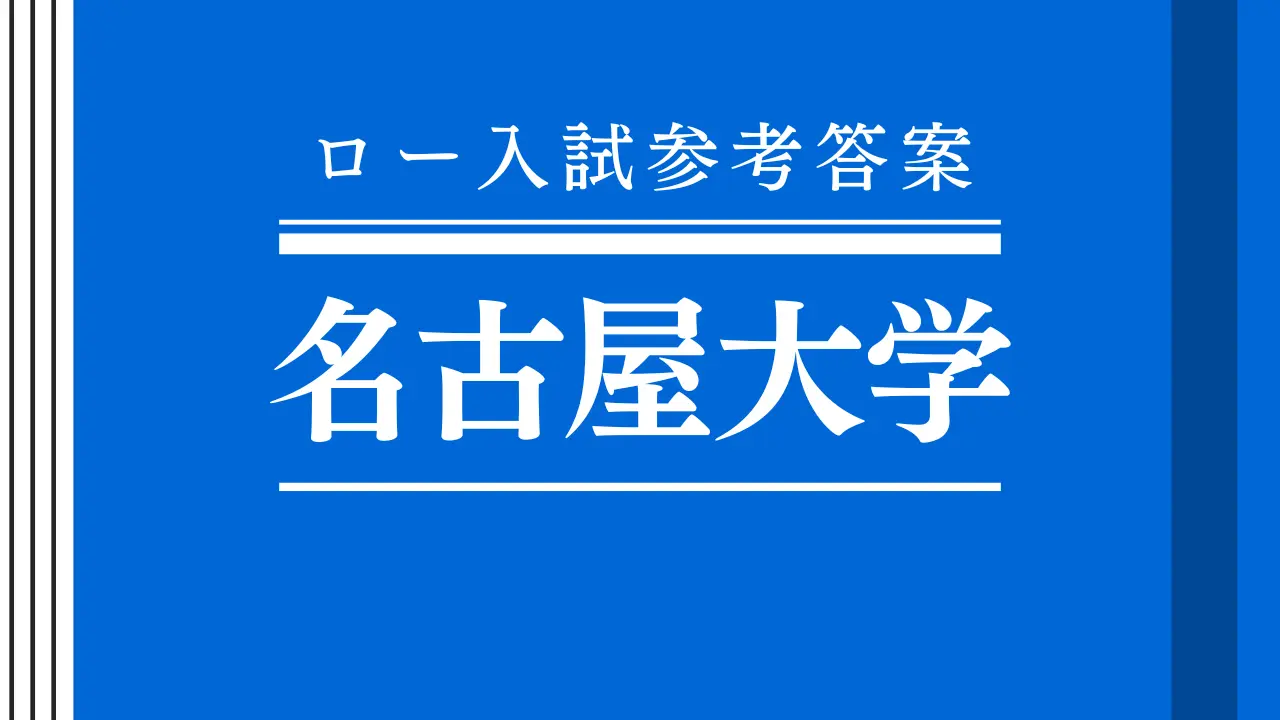
2025年 憲法 名古屋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
名古屋大学法科大学院2025年 憲法
問Ⅰ⑴
まず、国家賠償責任における公務員の個人責任は否定されるべきだから、国会議員の行為が「議員で行った演説、討論又は表決」に該当するかを問わず、国会議員が「職務」上の行為について個人的に損害賠償責任を負うことはない。
次に、国会における質疑等には国会議員に政治的判断を含む広範な裁量が認められるから、国会議員が国会で行った質疑等により個別の国民の名誉や信用を低下させる発言をした場合に国家賠償法上の「違法」が認められるのは、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を適示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を適示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特段の事情がある場合に限られる。
問Ⅱ
1. 組合員の知事選挙への協力要請は、労働組合活動の「目的の範囲」(民法34条)外であるとして無効とならないか。
⑴「目的の範囲内」か否かは、①当該法人の目的・性格、②強制加入性の有無、③問題となる人権の性質等を総合的に考慮する。
⑵南九州税理士会事件判決は、税理士会が法律上の設立義務、目的の法定、官庁の監督に服していること、強制加入団体で実質的には会員に脱退の自由が保障されていないことから、「目的の範囲内」にあるか否かについて厳格に判断したと解される。一方、八幡製鉄事件判決は、株式会社の「定款・・・で定められた目的の範囲内」の行為については、客観的・抽象的に観察して、目的を遂行する上で直接又は間接に必要であるかによって判断しており、これは、会社が公益性の乏しい私的な団体であり、強制加入性が認められないことから、緩やかな判断をしたものと解される。
甲組合は設立義務もないし、官庁の監督に服しておらず、過半数組合であるが加入が強制されているわけではない。組合の新規設立等も認められていることからすれば、労働基本権との関係を踏まえても、実質的な強制加入性を認めることはできない。そうすると、南九州税理士会よりも、八幡製鉄事件に類似しているといえ、同判例の基準に従って判断すべきである。
⑶労働組合は、労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体である。そして、今日においては、その活動の範囲が本来の経済的活動の域をこえて政治的活動、社会的活動、文化的活動など広く組合員の生活利益の擁護と向上に直接関係する事項にも及び、さらに拡大の傾向を示している。
そうすると、C党の所属議員Dの任期中は、甲組合の経営が順調であり、甲組合の組合員の生活環境も安定していたことからすると、知事選挙への協力要請が直接労働条件の維持改善に関わる事項ではないとしても、組合の経営が良くなればより組合の力が強くなり、それにより労働条件の維持改善もされるから、Dを支持することは労働組合の目的を遂行する上で間接に必要であるといえる。
⑷よって、目的の範囲内といえる。
2.目的の範囲内だとしても、公序良俗(民法90条)に反するなどの会員の協力義務を否定すべき特段の事情がある場合には、そのような協力要請は許されない。
組合に加入していることが労働者にとって重要な利益であるし、団体交渉の実効性等の観点から、組合脱退の自由は事実上大きな制約を受けている。そのため、労働組合の組合員には様々な思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されているから、会員の協力義務にも限界がある。
⑵選挙における投票において誰に投票するかは、各人は個人的な政治的思想・見解・判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。
そうであるにもかかわらず、D以外の者を応援した組合員に対しては、1年間の組合の総会に参加して決議に参加する権利を停止するという制裁を科すことは、公序良俗に反する。
3. したがって、会員に協力要請をすることはできない。
以上





