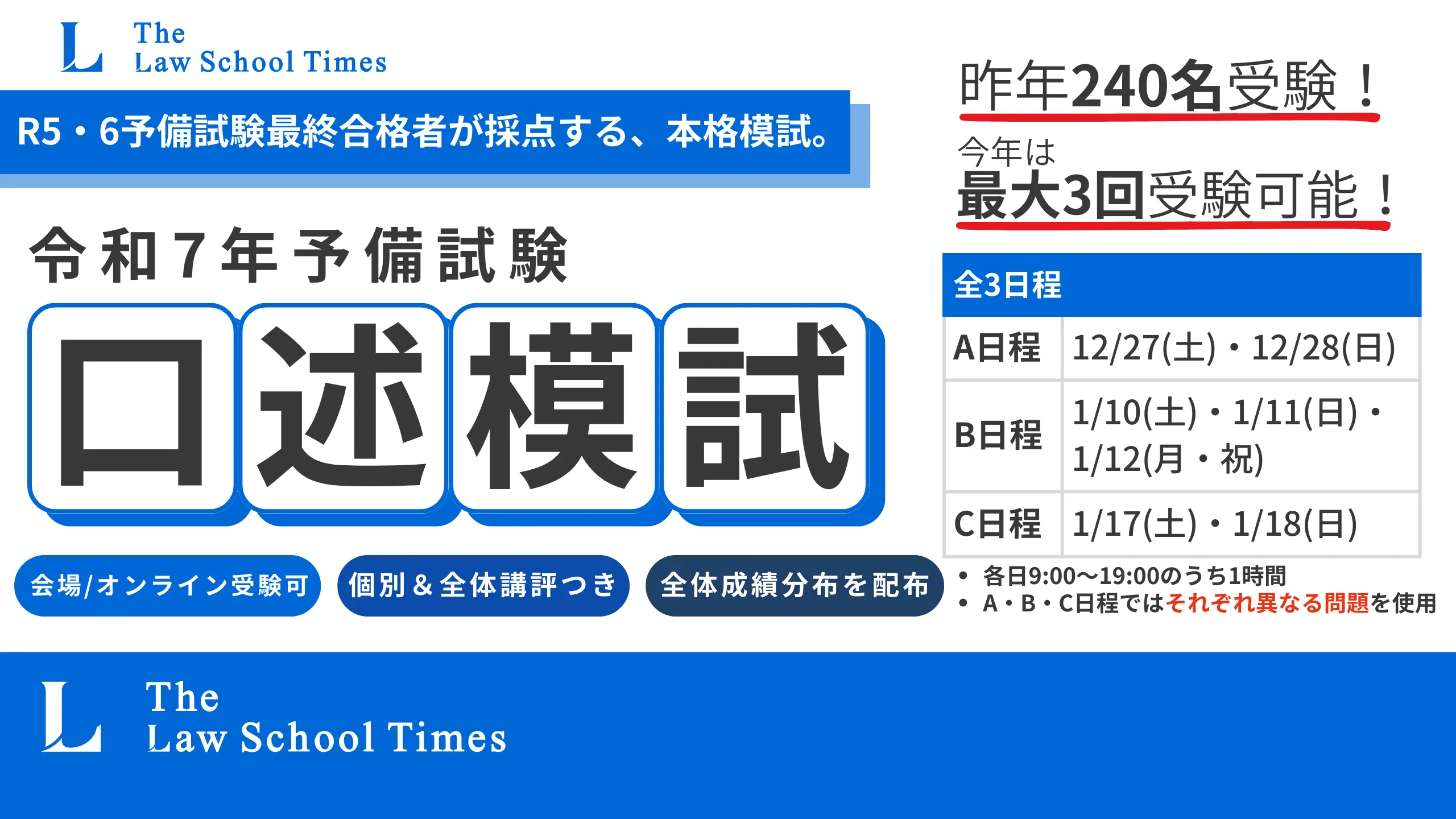【独占】第二東京弁護士会主催の修習生向けイベント潜入レポート!
3/25/2024
第二東京弁護士会(二弁)が3月1日(金)に、77期司法修習予定者向けイベント「修習のギモンに元教官がお答えします!」を開催しました。
【イベントの事前記事】
第二東京弁護士会主催77期修習予定者向けイベントの主催者に、イベントと二弁の良いところを聞いてみた!
本イベントでは、第1部の講演会にて、司法研修所元教官の横田高人弁護士(元民事弁護教官)と高津尚美弁護士(元刑事弁護教官)、及び5名の76期弁護士が登壇し、青木美佳弁護士の進行の下、修習生の不安や疑問点に回答しました。第2部の懇親会では、参加者である77期修習予定者総勢46名と弁護士たちが和気藹々と会話や食事を楽しみました。
今回は、講演会の概要や、懇親会の雰囲気などをレポートします。

元刑事弁護教官の高津弁護士(左)と元民事弁護教官の横田弁護士(右)
(ライター:阿部/The Law School Timesライター)
◇導入修習って何?◇
――導入修習の流れ、導入修習での過ごし方を教えてください
元教官・横田弁護士
民事弁護の導入修習では、3週間という短い期間で、その後の実務修習に最低限必要なことを座学と演習を中心に詰め込みます。
元教官・高津弁護士
刑事弁護では、演習に加え、刑裁教官室・検察教官室とのコラボカリキュラムを通じて、実践的な内容を学びます。演習では、模擬接見・尋問・量刑が争点となる事件の弁護活動などを扱います。
――元修習生の目線で、講義の内容や難易度はどうでしたか
76期・板橋弁護士
事前にあまり勉強をしないと講義内容が全くわからず、大変です。ただ、講義の中でしっかりと勉強をすれば、なんとか追いつくことも出来るので、あまり気を張らなくていいと思います。

修習の講義についてアドバイスを送る、76期・板橋弁護士
◇実務修習では積極的になんでも見て、経験せよ◇

会場には46名、Zoomには36名の77期修習予定者が参加。オンラインでの質疑応答も行った
――実務修習に向けて元教官からのアドバイスはありますか
横田元教官
教官の立場にいた者として、実務修習では何でも見てやろう、経験してやろうという意識を是非持ってほしいです。
――修習での実体験やアドバイスを教えて下さい
76期・岩井弁護士
裁判修習について、多くの修習生にとって裁判官室に入れるのは最初で最後の機会になります。そこで、裁判官室の本棚を見て、どんな本を使って裁判官がリサーチしているかを調べてください。また、裁判官に質問をして、自分の心証と裁判官の心証のズレを理解した上で、裁判官の心証に近づける訓練を積極的にしてください。

修習の過ごし方についてアドバイスを送る、76期・岩井弁護士
――実務修習中のコツなどはありますか
76期・佐薙弁護士
弁護修習で、事務所に行く際、多くの方が手土産を持っていくと思います。その時に、先生方への手土産だけでなく、弁護修習中にお世話になるパラリーガルや事務員の方の分も持って行くといいと思います。このような姿勢を見せることが、実務修習では重要です。
◇弁護士バッジを得るために。司法修習最後の関門、二回試験◇
――教官の立場から見た良い起案・落とされない起案のコツはなんですか
横田元教官
集合修習から二回試験にかけての、最重要のテーマは起案です。民事弁護の起案に関しては、司法試験を経たばかりの修習生は、裁判官的目線の起案をするクセがあります。しかし、民事弁護の起案の目的は、自身の依頼者のために裁判官を説得することにあるので、依頼者のストーリーを証拠に基づいて説得的に論じれば十分です。
集合修習において、仲間の書いた優秀な起案を読む機会があれば、ぜひ手に入れて、目を皿のようにして読みましょう。必ず勉強になります。
高津元教官
刑事弁護の起案は、想定弁論を扱います。想定弁論とは、証拠調べの前に証拠調べを想定して作成する弁論のことです。想定弁論を扱うのは、求める判決を得るためにどのような弁論をするのか、その弁論をするためにはどのような事実を公判に顕出することが必要か考えて公判準備をするためです。否認事件の想定弁論においては、本当は何があったのか、なぜ事実とは異なる証拠が存在するのかについて、一貫した、合理的で自然なストーリーを提示する必要があります。
――修習生の目線で、二回試験の注意点等はありますか
板橋弁護士
二回試験自体は、講義を聞いて、講義外での復習をやれば、心配する必要はないと思います。ただ、周りで二回試験に落ちてしまった人は、当日に体調を崩したことが原因で落ちていたので、体調管理は特に気をつけましょう。
◇修習生へのメッセージ◇
――最後に、修習生に向けて一言ずつメッセージをお願いします
佐薙弁護士
修習生も社会人ですので、社会人としての意識を持って修習に臨んで欲しいです。頑張ってきてください。
高津元教官
弁護士になった後、修習中にもっと積極的に取り組んでおけばよかったと後悔することもありました。修習生の方は、つまらなそうだなと思うことでも積極的に参加すると良いと思います。
横田元教官
与えられた時間は有限ですので、大いに仲間を作り、大いに遊び、大いに勉強してください。
(なお、秘伝ということで掲載できませんでしたが、実際の講演会では、上記内容に留まらず、教官から見た優秀な起案・二回試験に落ちてしまう起案の傾向や、修習の過ごし方のより詳しいコツなど、役に立つ情報が満載でした。本イベントは次年度以降も開催予定とのことですので、ぜひご参加ください。)
◇総勢30名の二弁所属弁護士との懇親会◇
1時間程度の講演会が終わった後は、会場参加の修習予定者と弁護士による懇親会が行われました。和気藹々とした雰囲気の中、第二東京弁護士会所属弁護士の仕事の話や講演会では聞けなかったことなど様々な話をしました。

76期・佐薙弁護士。懇親会は、弁護士と修習予定者らが分け隔てなく話せる雰囲気のもと行われた

職人が握るお寿司など、豪華な料理やお酒とともに交流を楽しんだ

司会進行を行ったのはアナウンサーでもある青木美佳弁護士
懇親会が終わった後も、修習予定者は、二次会に参加したり、さらに先生方と食事に行ったり飲みに行ったりと大変充実した様子でした。

二弁副会長の大森弁護士と77期修習予定者。懇親会は朗らかな雰囲気で行われた
◇第二東京弁護士会◇
第二東京弁護士会のホームページはこちら